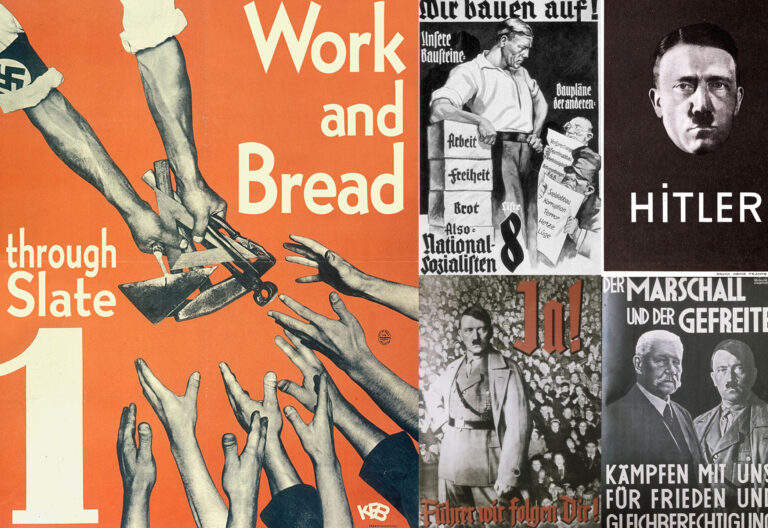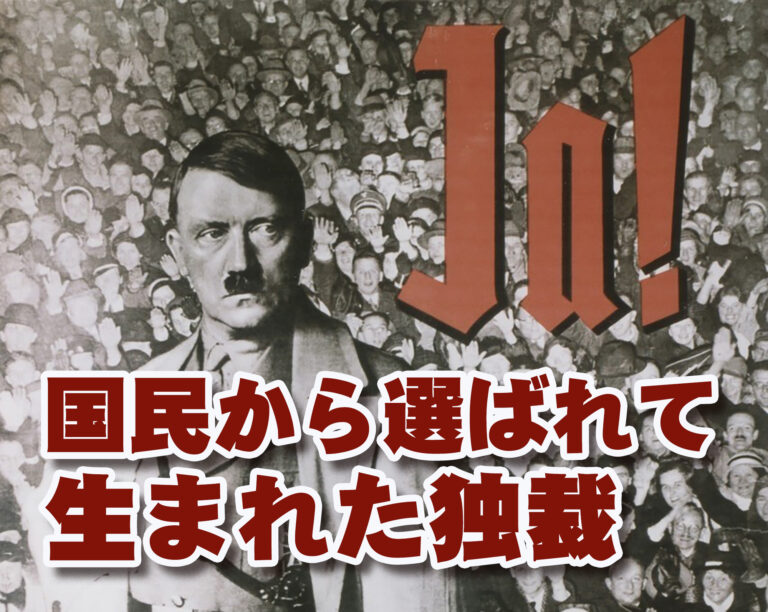12月8日、井手よしひろ県議は、茨城県信用保証協会に根本会長、堤専務理事を訪ね、緊急保証制度の利用実績やその課題について意見交換しました。
緊急保証制度は、金融危機による信用収縮による銀行の貸し渋りを防止するために、導入された中小企業支援策です。
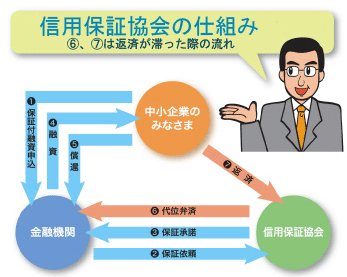 しかし、実際の中小企業の現場では、本当に資金繰りに窮している企業の支援にはつながっていない、との落胆の声が聞こえてきます。
しかし、実際の中小企業の現場では、本当に資金繰りに窮している企業の支援にはつながっていない、との落胆の声が聞こえてきます。
一番の問題は、保証協会の審査基準は、今までの一般保証とほとんど同じであるということです。確かに2期連続赤字でも門前払いしない等の条件緩和策が講じられましたが、今まで貸し渋りにあっている企業を救う、という本来の目的を達するには程遠い状況です。
認定事業者であれば、たとえ債務超過であっても、総合的に判断し、融資できるようにする。今までの融資枠とはまったく別枠で融資を実行するなどの思い切った制度導入が必要です。
現状で保証承諾された企業は、財務内容に特段の問題がなく、他の融資を受けられる企業です。金融機関が、責任共有制の枠外であるこの緊急保証制度を薦め、自らのリスクの軽減のために使っているだけとの陰口も聞こえてきます。(もちろん保証料の一割を県が負担するという大きなメリットがあります)
全国で1ヶ月間に約1兆円の保証承諾実施となりましたが、本来、緊急保証制度が無くても、融資を受けられた企業への実行であり、既存の制度では融資不可能であった企業への支援がどれだけ伸びたかは疑問が残ります。
なお、茨城県の11月28日現在の実績は、申請が1176件(1176億2098万円)、保証受諾が804件(102億7854万円)となっています。
今回の緊急保証融資制度は、1次補正において、将来の損失補填(信用保証協会が債務者に代わって支払いを行う=代位弁済)に充当するため、約4600億円を予算化を行っています。信用保証協会経由で銀行から融資を受けた企業が破綻し、債務不履行となると、保証協会はその残債全額を連帯保証人として金融機関に返済(代位弁済)します。保証協会は、代位弁済の80%を日本政策金融公庫における保険として受け取ります。残り20%のうち8割を国が負担し(全体の16%)、2割を県保証協会が負担(全体の4%)します。
今回の国の1次補正で確保された9兆円の貸出枠は、その量的拡大を行った訳です。保証協会としては自己負担分の2割は変わりはないので、よりリスクのたか企業への保証拡大への動機付けには全くなっていません。つまり、今まで貸渋りにあった企業に、緊急保証で融資をしようという構造になっていなのです。審査基準を下げて保証すれば、当然、代位弁済は増加し、保証協会の財務内容が悪化してしまいます。
ではどうせれば良いのかというと、代弁資金の責任分担割合を、国を90%程度に拡充すれば良いと提案します。(保証協会の負担は2%と半減します)
バブル崩壊後に実施された特別保証は3年間で約20兆円実施されました。これは、国100%であったため、モラルハザードを起こし、様々な問題を残しました。
したがって、保証協会に一定の責任を持たせることも必要です。その上で、保証協会自体のリスクを軽減できれば、審査の基準を緩和し、中小零細の最も資金を必要とする、まじめに働く企業に資金が回るようになるはずです。
この際、政府の予算に限度があるなら、2次補正で貸出枠を敢えて30兆円まで確保する必要はないのではないかと考えます。貸付枠拡大を第一義にするのではなく、資金を真に必要とする零細中小企業者をどれだけ救済できたかを最重要視すべきです。