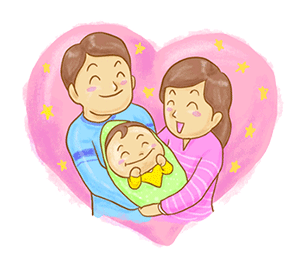12月16日に投開票された衆議院総選挙での各党の獲得議席は、自民294、維新54,民主57、公明31、みんな18、未来9、共産8、社民2、大地1、無所属5という結果になりました。
しかし、小選挙区の自民党の得票率はわずか43%と過半数にも達していません。この43%で79%の議席を獲得してしまったのです。小選挙区で落選候補に投じられ有権者の票数は、いわゆる死票は3730万票にのぼり、全得票に占める「死票率」は実に56%に達しました。
過半数の国民の声が選挙結果に反映しないという制度は、果たして民意を具体化する選挙制度といえるのでしょうか?
前回総選挙の「死票率」は46.3%でしたから、今回は前回に比べ9.7%も「死票率」は増加してしまいました。民主党の分裂により、日本維新の会や日本未来の党など新党の参入で、12もの政党が割拠したことで、得票が分散してしまった結果です。
そこで、かなり乱暴な手法ですが、政党に対する民意を比較的忠実に反映すると言われている比例区に寄せられた各党の得票を、ドント方式で480議席に配分してみました。
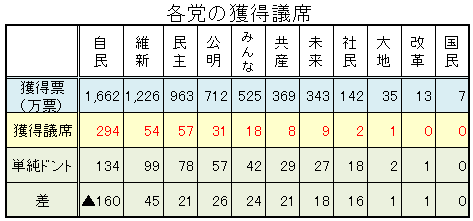
(各党の比例区得票をもとに、衆議院の総議席480議席にドント方式で配分してみました。クリックすると表の全体をご覧になれます)
すると、各党の得票試算は、自民134(▲160)、維新99(+45)、民主78(+21)、公明57(+26)、みんな42(+24)、未来27(+18)、共産29(+21)、社民18(+16)、大地2(+1)、改革1(+1)となり、小選挙区比例代表制の結果とは大きく異なってきます。
衆議院選挙を政党を選ぶ選挙とするならば、二大政党に集約できない日本には、小選挙区制度はやはりなじまないと結論できるのではないでしょうか。
国会改革は中選挙区制度の導入!
さらに言えば、政党を選ぶとした小選挙区制度の発想も、結果的に国会議員のそれ自体の劣化に繋がってしまったのではないでしょうか。小泉チルドレン、小沢ガールズ、橋下ベビーズと揶揄される国会議員の誕生はその典型です。選挙直前の党のイメージ(=まさに“風”)で当落が決まるため、政党を渡り歩いたり、ほとんど何の経験や実績のない新人候補が当選してしまうという傾向が強くなりました。逆に、その風が止むと、今回の日本未来の党のように61人の国会議員が9人という大惨敗を喫することになります。
小選挙区で落選しておきながら比例区で復活当選するという制度も、理解に苦しむ制度です。
こうしたことを考慮すると、次期国会で課題となる議員定数の削減問題は、単なる数字あわせだけの問題ではなく、小選挙区制度の是非を問う本質的な議論を行うべきです。定数3の中選挙区を全国に150作るという案などを、本気で検討すべきだと提案します。