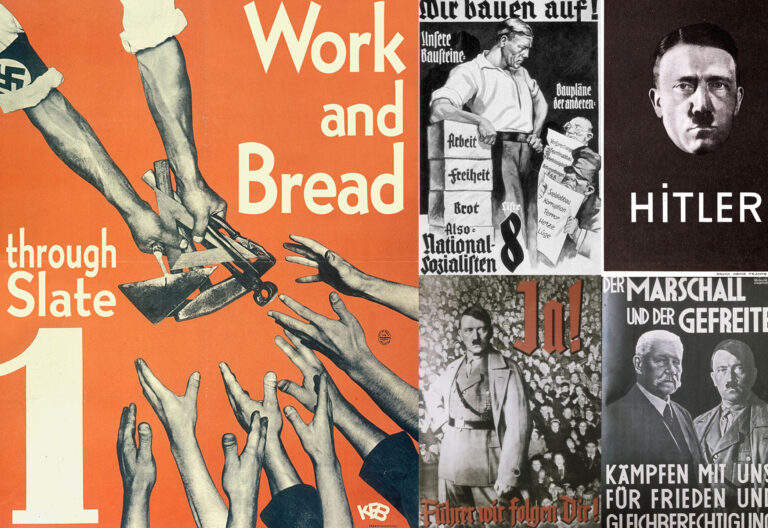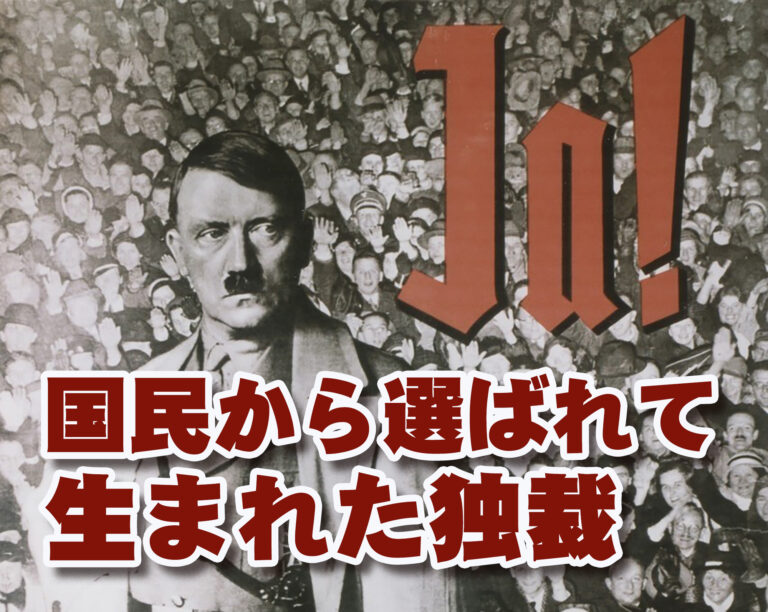なぜ、今、踏み込まなくてはならないのか――。
その一言に、多くの国民が息をのんだ。
11月7日、高市首相が衆議院予算委員会で、「台湾有事が武力の行使を伴うものであれば『存立危機事態』になりうる」と述べた発言は、これまでの日本政府が慎重に避けてきた線を越えたものでした。たとえ首相自身が「従来の立場の範囲内」と強調しても、聞く側にはまったく違う印象を与えたのです。
歴代の首相たちは、台湾情勢に関しては一貫して慎重な言葉を選んできました。高市首相が師とする安倍元首相は国会答弁で、「台湾海峡の平和と安定は、我が国の安全保障にとって極めて重要である」と述べつつも、「個別具体的な事態について、存立危機事態に該当するかどうかを一概に申し上げることはできない」と繰り返していました。同様に、菅首相も「台湾問題は当事者間の対話によって平和的に解決されることを期待する」と語り、政府として「想定の段階で踏み込んだ評価は差し控える」と明確に距離を置いてきました。
それは、単に外交辞令ではなく、戦後日本が守ってきた「抑制の知恵」でした。台湾有事という言葉を軽々しく使えば、中国を刺激し、東アジア全体の緊張を高める。だからこそ、あえて曖昧さを残すことが、平和を守るための戦略だったのです。
しかし高市首相の発言は、その均衡を軽率にも壊しました。
「戦艦を使って武力の行使も伴うものであれば存立危機事態になりうるケースだと考える」。この言葉は、たとえ理屈の上では安保法制の範囲内でも、現職総理が台湾を具体的に念頭に置いて発した点で、従来の答弁とは明らかに異なります。
官房長官は「従来の政府見解を変えるものではない」と火消しに回りましたが、外交というのは“どう受け取られるか”がすべてです。中国や周辺諸国がこの発言を、「日本が台湾防衛のために集団的自衛権を行使する可能性を公然と示した」と受け止めれば、平和の秩序は一気に揺らぎます。
安倍政権下での2015年の安保法制審議でも、政府は「どのような事態が存立危機事態に該当するかは、個別具体的に判断するものであり、一概に申し上げることはできない」と明言していました。高市首相の発言は、まさにこの“個別具体的に判断する”という抑制の原則を、自らの言葉で崩したことになります。
発言の背景には、国内向けに「強い日本」「毅然とした外交」を印象づけたいという思惑も見え隠れします。しかし、外交は強気の姿勢だけで成り立つものではありません。リーダーの一言が、意図せぬ形で緊張を高め、軍事的な誤算を呼ぶこともあるのです。
戦後の日本外交は、挑発よりも沈黙を、威嚇よりも対話を選んできました。小渕恵三元首相は「静けさの中にこそ信頼が生まれる」と語り、福田康夫元首相は「戦わない知恵こそがアジアの平和を築く」と言いました。そうした知恵が、今まさに試されています。
高市首相の言葉は、覚悟ではなく軽率さを感じさせました。国家の安全保障とは、声を荒げることではなく、危機を遠ざけるために冷静さを貫くことです。外交の舵を握る者が、自ら波を立ててどうするのか。
「なぜ、今、踏み込まなくてはならないのか」。
その問いに、明確な答えを示せない限り、この発言は「戦略的発言」ではなく「不用意な挑発」として歴史に残るでしょう。
いま求められているのは、「覚悟」を語る力強い言葉ではなく、深い「思慮」です。そしてその思慮こそが、平和を守る最大の力であることを、私たちは忘れてはならないと思います。
参考:存立危機事態とは
「存立危機事態(そんりつききじたい)」という言葉は、少し難しく聞こえますが、簡単に言えば――
「日本が直接攻撃されていなくても、日本の安全と国民の命が重大な危険にさらされたとき」 のことを指します。
2015年の安保法制(安全保障関連法)で導入された概念で、日本が「集団的自衛権(味方の国が攻撃されたときに、一緒に守る権利)」を行使できる条件として定められました。
「どんな場合でも助けに行ける」というわけではなく、次の3つの条件をすべて満たすときに限って、自衛隊が武力を使うことが認められます。
① 日本と“密接な関係にある国”が攻撃されたとき
たとえば、アメリカやオーストラリアなど、日本と安全保障で協力関係にある国が攻撃された場合です。
「他国の戦争に勝手に参加する」ということではなく、日本の安全に深く関わる国が危険にさらされたケースを想定しています。
② その攻撃によって、日本の存立(国としての生き残り)が脅かされる
つまり、「放っておけば、日本の国民の命や暮らしが根底から覆されるような危険がある」と政府が判断した場合です。
たとえば、海上輸送路(シーレーン)が封鎖されて日本にエネルギーが届かなくなるとか、日本周辺で同盟国の艦船が攻撃され、次は日本が標的になる可能性が高い――そんな状況です。
③ それを防ぐために、ほかに適当な手段がない
外交や経済制裁など、他の平和的な手段をすべて尽くしても危険を止められない場合に限って、自衛隊が武力を使うことができる――という「最後の手段」という位置づけです。
この3つをまとめると、「日本が攻撃されていなくても、放っておけば日本そのものが危険にさらされるときに、自衛隊が味方の国と協力して行動できる」というのが「存立危機事態」です。
ただし、「存立危機事態」の判断は政府が勝手に決めるのではなく、国会の承認が必要です。つまり、総理大臣が「存立危機事態だ」と言えば即座に戦争になる、というものではありません。
身近な例で言えば、家族や隣人の家が放火されて燃え広がり、自分の家にも火の粉が飛んできそうな状況――その火を止めなければ自分たちも危ない、という場面に少し似ています。
自分の家が燃えていなくても、「このままでは家族の命が危ない」と判断すれば、協力して火を消す――それが「存立危機事態」の考え方です。
しかしこの考え方には、「どこまでが“危機”か」「どの国が“密接な関係”にあるのか」といった線引きがあいまいな部分もあります。
だからこそ、政府の判断が恣意的にならないように、国会での説明責任と透明性が強く求められているのです。