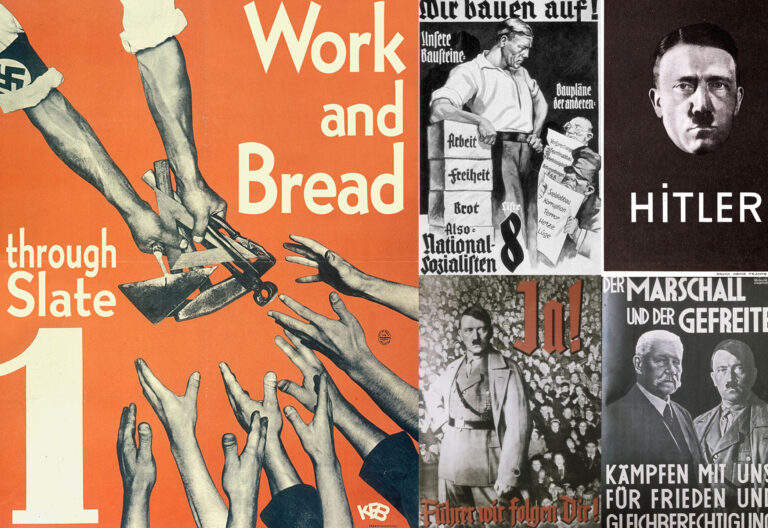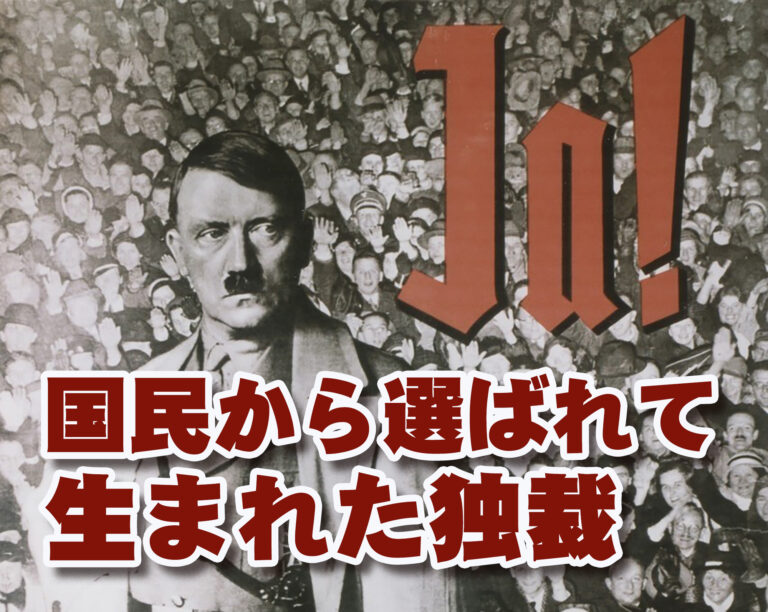日本の安全保障をめぐる議論が、いま大きな転換点に差し掛かっています。長く続いた自民・公明の連立が終わり、安全保障政策の“歯止め役”を担ってきた公明党が政権枠組みから離れたことで、日本は新しい防衛政策の針路を探る局面に立たされています。こうした状況だからこそ、公明党がこれまでどのように日本の安全保障を支え、どんな役割を果たしてきたのかを改めて見つめ直す必要があると感じています。
戦後日本の安全保障は、吉田茂が打ち出した「吉田ドクトリン」を軸に歩んできました。経済復興を優先し、安全保障はアメリカの軍事力に依存するという選択です。自民党はこの路線を維持しつつも、憲法改正や再軍備を主張する強硬派も抱え、対する社会党は自衛隊違憲論を掲げるなど、55年体制のなかで両者は安全保障をめぐって激しく対立してきました。その綱引きの中で、日本は「抑制された安全保障」という独自のスタイルを育てました。武器輸出三原則、非核三原則、必要最小限度の防衛力――いずれも憲法9条の範囲内で防衛をどう位置づけるかを慎重に判断してきた結果です。
この「抑制の哲学」を冷戦終結後も支え続けてきたのが公明党です。1999年に連立へ参加して以来、公明党は日米同盟を重視しながらも、武力行使には一貫して慎重であり続け、憲法との整合性に細心の注意を払ってきました。2015年の安保法制では、政府が当初想定していた幅広い集団的自衛権を大きく絞り込み、「限定的な行使」にとどめたのは公明党の調整の成果とされています。公明党は単なる“反対勢力”ではなく、現実的な防衛と憲法理念の間をつなぐ、きわめて重要なバランス役として存在してきたのです。
しかし今、その均衡が大きく揺らいでいます。中国の軍拡、台湾海峡の緊張、ロシアの侵攻、そしてアメリカの対外関与の揺らぎ。国際秩序は不安定さを増し、国内でも高市政権は防衛費の大幅増、反撃能力の前倒し整備を強調し、新たに連立に加わった維新の会は憲法9条2項の削除や集団的自衛権の全面容認を掲げています。
こうした政策の動きは、これまで公明党が果たしてきた“安全保障政策のブレーキ”が外れつつあることを意味します。防衛力の強化そのものが否定されるべきではないにせよ、節度を欠いた大幅転換はむしろ日本の安全保障を危うくしかねません。
その象徴が、高市政権が見直しを示唆する三つの柱――非核三原則、台湾有事に関わる「存立危機事態」、そして武器輸出5原則です。
まず、非核三原則の緩和です。核持ち込みや核シェアリングを議論する動きがありますが、日本は唯一の被爆国として、核を持たない国だからこそ国際的な信頼を得てきました。これを揺るがせば、日本外交の基盤が崩れ、アジア諸国の不信を招きます。核は抑止力の象徴であっても、日本が踏み込むべき領域ではありません。
次に、台湾有事を「自動的に存立危機事態とみなす」かのような発言です。従来政府は、存立危機事態の認定はあくまで“個別具体的な状況で判断する”と明言してきました。これを曖昧にすれば、日本が紛争のエスカレーションに巻き込まれる危険が一気に高まります。外交の柔軟性も失われ、「巻き込まれ回避」という国家戦略上の要点も揺らいでしまいます。
そして、武器輸出5原則の緩和です。武器輸出を広げれば、日本が“紛争当事国に加担する国”と見られるリスクが高まります。アジア諸国の信頼を失い、日本製の兵器が第三国で火種になる可能性も否定できません。公明党が慎重姿勢を貫いてきたのは、単に平和主義からではなく、日本の外交的立場を守る合理的な戦略でもあったのです。
こうしてみると、公明党が積み重ねてきた「抑制の安全保障」とは、決して時代遅れの理念ではありません。世界が不安定になるほど、節度と対話の政治が必要になります。力と力のぶつかり合いでは平和はつくれません。誤ったエスカレーションを防ぎ、冷静な判断を保つことこそ、日本の安全保障の本当の強さにつながると思います。
戦後80年の節目に立つ今、日本は新たな安全保障の時代へ踏み出そうとしています。その荒波の中で、公明党が担ってきた「抑制と現実をつなぐ政治の作法」をどう継承していくのか。その問いは、公明党自身だけでなく、この国の未来を考えるすべての私たちに向けられていると感じています。

公明党が高市政権に「質問主意書」提出
こうした節目にあって、公明党・斉藤鉄夫代表が提出した「質問主意書」は極めて重要な意義を持っています。
質問主意書は形式的な文書のやり取りではありません。国会が政府の姿勢を正し、国の基本方針が揺らいでいないかを厳しく点検するための、極めて重要な国政監視手段です。
斉藤代表は、高市首相が非核三原則の堅持を明言しなかった点、台湾有事が「存立危機事態になり得る」と踏み込んだ点に深い懸念を示しました。非核三原則は被爆国・日本の道義的基盤であり、周辺国の信頼を築くための土台です。これを曖昧にしたまま政策転換を進めることは、国際的な信用を損ねかねません。
また、「存立危機事態」の認定は、日本が武力行使に踏み出す重大な判断です。首相が個別事例に踏み込む発言を行えば、国民も周辺国も「日本が巻き込まれる覚悟を固めている」と誤解する恐れがあります。だからこそ斉藤代表は、従来の認定基準を本当に維持しているのか、見直しを想定しているのか、個別事例を挙げる答弁は誤解を生まないか、こうした点を一つひとつ問いただし、政府の姿勢をただす必要があると訴えたのです。
質問主意書は、国会が果たすべき「国民の安心を守るためのチェック機能」そのものです。安全保障政策が大きく動こうとしている今だからこそ、立法府が行政の暴走を防ぎ、国の基本方針に揺らぎがないかを確認することが、これまで以上に重要になっています。
国際秩序が不安定さを増す時代に、節度ある安全保障をいかに守り抜くのか。その答えは、政府の姿勢を丁寧に問いただし、国民に見える形で明確にしていくことにあります。斉藤代表の質問主意書は、そのための第一歩です。
戦後80年、日本の平和を支えてきた「抑制の知恵」を次の時代につなぐためにも、この問いかけが果たす役割は計り知れないと感じています。
【注釈:武器輸出5原則とは】
武器輸出5原則とは、日本が防衛装備品をどの国へ、どのような条件で移転できるのかを定めた重要な基準です。2014年に「武器輸出三原則」を発展させたもので、国際社会の平和と安定に資するため、次の5つの抑制的ルールが設けられています。
- 国連安全保障理事会決議で武器禁輸措置の対象となっている国・地域には輸出しないこと。
- 紛争当事国や、紛争が継続している恐れがある国・地域には輸出しないこと。
- 国際平和・協力に資する場合や、日本の安全保障に役立つ場合など、限定された目的にのみ輸出を認めること。
- 輸出した装備品が第三国へ再移転されないよう、事前に厳格な管理措置を確保すること。
- 輸出の可否は国家安全保障会議(NSC)が個別に審査し、政府として責任を持って判断すること。
これらの原則は、日本が紛争に加担するリスクを避け、アジアをはじめとする国際社会の信頼を維持するための“安全保障上のブレーキ”として機能してきました。公明党が一貫して、この枠組みの堅持を訴えてきた理由もここにあります。