児童手当の創設、出産一時金増額など結党以来、ブレずに実現
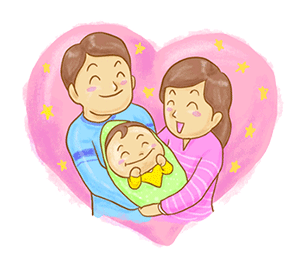 衆院選の公約に、どの政党も子育て支援を掲げています。その中で結党以来、子育て支援の充実をブレずに訴え続け、多くの実績を積み上げてきたのは公明党です。いわば「子育て支援の“元祖”」です。
衆院選の公約に、どの政党も子育て支援を掲げています。その中で結党以来、子育て支援の充実をブレずに訴え続け、多くの実績を積み上げてきたのは公明党です。いわば「子育て支援の“元祖”」です。
教科書の無償配布をはじめ、児童手当の創設・拡充、出産育児一時金の増額や妊婦健診の14回公費助成などは子育て世帯に喜ばれています。これらは公明議員が庶民に寄り添う中で育んできた実績です。例えば、今や国の制度として定着している児童手当は、1968年に公明党が主張して千葉県市川市で実現したのが始まりです。
先の通常国会で民主、自民、公明の3党が主導した社会保障と税の一体改革では、子育て分野に新たに1兆円が増額されることになりました。公明党の主張が反映され、待機児童解消のための認定こども園の拡充、保育士の待遇改善が進みます。
子育て安心社会へ幼児教育無償化、いじめ対策強化などめざす
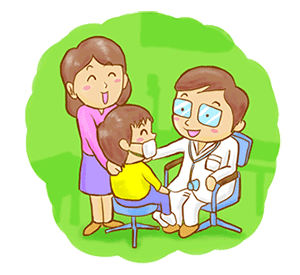 子どもがいる人に子育てへの不安を聞くと、常に「経済的負担の増加」が上位に挙がります。そこで公明党は、安心して子どもを産み、育てられる社会とするため、衆院選重点政策(マニフェスト)に各種の負担軽減策を掲げています。
子どもがいる人に子育てへの不安を聞くと、常に「経済的負担の増加」が上位に挙がります。そこで公明党は、安心して子どもを産み、育てられる社会とするため、衆院選重点政策(マニフェスト)に各種の負担軽減策を掲げています。
具体的には、出産育児一時金の42万円から50万円への増額や妊婦健診14回分の公費助成の恒久化、就学前3年間の幼児教育の無償化、大学生や高校生のための給付型奨学金制度の創設などです。
一方、深刻化するいじめ問題については、各小中学校へのスクールカウンセラーや児童支援専任教諭の常時配置に取り組み、いじめなどで悩む子どもたちが相談しやすい環境をつくります。
公明党の重点政策について、“夜回り先生”こと水谷修氏は「今、教育の現場で、最も求められていることが、約束されている」と声を寄せています。
一体改革の3党協議で1兆円の財源確保を約束させた公明党
民主党政権は、子育て支援の指揮を執る少子化担当相がわずか3年余で10人も代わる始末。また、看板政策だった「子ども手当」は財源を確保できずに迷走を続け、結局は児童手当が復活しました。
民主党は「一体改革で子育て支援を充実させた」などと主張していますが、とんでもありません。一体改革で政府が示した子育て支援の予算は7000億円。これに対し「これでは足りない。1兆円に」と民主、自民との3党協議で最後まで財源確保を主張し、約束させたのは公明党です。
一方、多くの民主党離党者が参加する日本未来の党は、前回衆院選の民主党マニフェストの政策を踏襲して、性懲りもなく「子ども1人当たりの中学卒業まで年間31万2000円の手当を支給」を掲げています。
明確な財源を示さず甘言を述べるだけの政党に子育て支援を語る資格はありません。
- 18歳まで医療費負担を1割に
現在就学前まで2割となっている医療費の窓口負担について、18歳まで1割への軽減を目指します。 - 出産費用の負担軽減
出産育児一時金を現在の42万円から50万円に引き上げます。また、妊婦健診14回分の公費助成を恒久化します。 - 不妊治療や不育症への支援の充実
不妊治療への公的支援を拡充します。流産や死産を繰り返す不育症の方を支援するために、適切な治療体制の整備や経済的負担の軽減を図ります。 - いじめ対策、不登校対策
各小中学校にスクールカウンセラーや、児童支援専任教諭等を常時配置し、いじめなどで悩む子どもたちが相談しやすい環境づくりを推進します。 地域全体で学校教育を支援する体制づくりを進める「学校支援地域本部」の設置や、不登校児童生徒を受け入れ、学校復帰等を支援する「教育支援センター(適応指導教室)」の全市区町村への設置を進めます。 - 通学路にもっと安全対策を
学校、PTA、警察、道路管理者等が一堂に集まり、通学路を点検する体制を確立し、計画的に通学路の安全確保を図ります。 - 学校施設の耐震化と長寿命化対策
学校施設の耐震化(非構造部材を含む)100%を達成します。予防保全という考え方で、劣化状況調査を実施し、学校施設の長寿命化を図り、維持費を圧縮します。 - 防災・防犯などの安全教育を教科に
災害や犯罪等から自分の身を守る力を養うため、防災教育や防犯教育を含めた安全教育の教科化を進めます。 - 幼児教育の無償化を推進
就学前3年間の幼稚園・保育所・認定こども園等の幼児教育の無償化を進めます。 - 奨学金制度をさらに拡充
大学生、高校生のための給付型奨学金制度を創設します。また、無利子奨学金や返還免除制度など奨学金制度の拡充を図ります。 - 全中学校に給食を導入
全公立中学校への給食導入を目指します。(公立中学校における完全給食導入率:82.4%(2010年5月1日現在)) - 教育行政の抜本的見直し
いじめや不登校問題など学校現場には様々な問題が起こっています。 これらの問題に迅速かつ的確に対応するため、委員選定や委員会の権限をはじめとする教育委員会のあり方を抜本的に見直し、その機能強化を図ります。 また、学校ごとの裁量の幅を広げ、教員の創意工夫を奨励する制度を推進します。 - 障がいのある子どものための特別支援教育を手厚く充実
特別支援教育を拡充するため、小学校・中学校・高等学校等に特別支援教室の設置を推進します。 また、発達障がいなどで“読み”が困難な児童・生徒のための「デイジー教科書」を教科用特定図書とし、無償供与します。 - 大学入学制度等を改善・改革
秋入学導入を含め、大学入学制度を抜本的に見直します。 また、学習障がい等の障がいのある生徒が受験しやすいよう、読み上げや時間延長等の合理的な配慮ができる体制を整備するなど大学入試制度を改善します。 - 大学教育の質の向上
学生による授業評価等を通じて大学授業の質を向上させます。障がい者が学びやすい環境を整備します。
大学教員等に若手・女性研究者の積極的な採用を図ります。 - 海外留学を大きく促進。支援制度も拡充
高校生、大学生の海外留学を大きく促進します。 高校生留学支援金や給付型の留学奨学金の対象枠を大幅に拡大するなど、公的留学支援制度を抜本的に拡充します。 また、外国人学生のために、卒業後の就労支援を含む生活支援を充実させます。 - 多様な教育機会の充実
「公立夜間中学校」を全都道府県に1校以上設置するなど、学齢期(満6歳~15歳)に就学できなかった義務教育未修了者や在日外国人などの学習支援の 充実を図ります。さらに、定時制・通信制・単位制高校や、通信教育課程を導入する大学等の増設・拡充など教育機会の一層の多様化に取り組みます。



