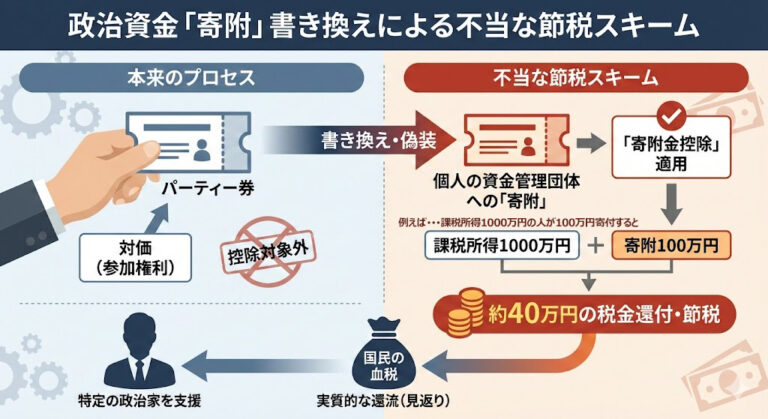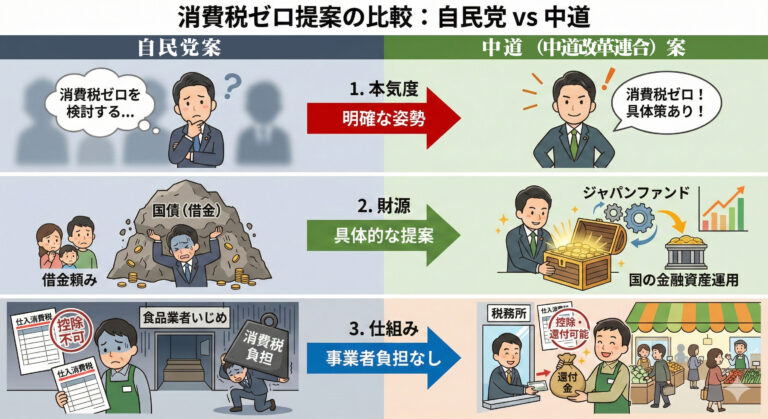自民党が新たに作成したポスター。「日本列島を、強く豊かに。」という言葉に、どうしても拭えない違和感を覚えました。一見すると前向きで力強い表現に見えますが、言葉を丁寧に読み解いていくと、そこには慎重に考えるべき問題がいくつも含まれているように思います。
まず気になるのは、なぜ「国民」ではなく「日本列島」なのか、という点です。政治が向き合うべき対象は、本来、そこに暮らす一人ひとりの人間、すなわち国民のはずです。生活の不安、将来への心配、地域ごとの課題にどう応えるのか。そうした視点こそが民主主義の土台です。それにもかかわらず、今回のポスターでは、人ではなく「列島」という領土概念が前面に出ています。この言葉は、北海道から沖縄までをひとまとめにする便利な表現である一方で、北方領土、竹島、尖閣諸島といった、現在も続く領土問題を否応なく想起させるものでもあります。あえて曖昧な形で領土意識を刺激する、その政治的な意図を感じ取る人がいても不思議ではありません。
さらに、「強く」という言葉には、より強い違和感を覚えます。誰に対して強くなるのでしょうか。何に立ち向かうための強さなのでしょうか。その説明がないまま「強さ」だけが強調されるとき、そこには力や威圧、対立を前提とした発想が透けて見えます。強さが安心や包摂ではなく、競争や支配として語られるならば、それは社会を分断しかねません。その奥底に、どこか傲慢さや強権的なものの見方が潜んでいるように感じてしまいます。
この言葉の組み合わせは、どうしても、かつて日本が掲げた『富国強兵』というスローガンを思い起こさせます。国を豊かにし、強くすることを最優先に掲げたその時代、個々の暮らしや声は、しばしば後回しにされました。もちろん、今の日本が同じ道を歩んでいると単純に言うことはできません。しかし、「人」よりも「国土」や「強さ」を前に出す言葉選びには、歴史の教訓に照らして慎重であるべきだと感じます。
本当に求められているのは、外に向かって誇示する強さではなく、内側から支え合うしなやかな強さではないでしょうか。災害に備える力、困っている人を見捨てない力、地域や世代の違いを乗り越える力。そうした強さは、「列島」ではなく、「人」に目を向けた政治からしか生まれません。
スローガンは、政治の姿勢を象徴します。だからこそ、その主語が何であるのか、その言葉がどんな歴史や感情を呼び起こすのかを、私たちは見逃してはいけないと思います。「日本列島を、強く豊かに。」という言葉が投げかけているのは、単なるキャッチコピー以上に、これからの日本の政治がどこを向こうとしているのか、という根源的な問いなのではないでしょうか。

言葉が国を動かした歴史
――「富国強兵」から総動員へ、暮らしの空気が塗り替えられた道
明治維新以後、日本が「近代国家」へ駆け上がっていく過程では、法律や制度の整備と同じくらい、人々の心の向きをそろえる“短い言葉”が大きな役割を果たしました。いま振り返ると、それは単なるキャッチコピーではなく、国の進路を「疑う余地のない正しさ」に見せかけ、社会の空気そのものをつくっていく装置でもあったように思えます。
そして恐ろしいのは、言葉は便利で、しかも短いほど強いという点です。耳触りのよい四字熟語や標語は、複雑な現実をいったん飲み込み、私たちの思考を“ひとつの方向”へまとめてしまいます。その力が、近代化の推進にも、戦争への傾斜にも、同じように働き得た――ここに、この歴史の核心があります。
近代化の合言葉としての「富国強兵」――合理性と動員のはじまり
明治の出発点で、日本が直面したのは欧米列強の圧力でした。「追いつき、追い越す」ことが国家の最優先課題となり、そこで前面に出たのが「富国強兵」と、それと一体で語られた「殖産興業」「文明開化」です。産業を育て、教育を整え、国家としての体裁を急いで整える。こうした方向性には、当時の国際環境を考えれば一定の合理性がありました。
ただし、この段階からすでに、言葉が持つ“束ねる力”が働き始めます。国家が目指す方向が「富国強兵」の四字に凝縮されると、政策の細部や副作用は語られにくくなります。たとえば西洋式の軍隊を整えるための徴兵制は、制度としては「国家の防衛」を支える骨格でしたが、同時に「国のために人を動員できる」仕組みを社会に根づかせていきました。言葉が旗印になり、旗印があることで、国の総力が一方向へ集まっていく。ここが、近代国家の成立と“動員体制”の起点になります。
そして「富国強兵」は、厳密には“ある一人が言い出した新語”というより、古くからある国家観を四字に圧縮したものが、近代日本の政治的スローガンとして定着した、と捉えるのが実態に近いでしょう。発想の源流は中国古典にさかのぼるともされ、日本でも幕末から明治初期にかけて改革論の語彙として用いられました。つまり当初は、好戦主義の合言葉というより、「開国と近代化の中で国家を保つための設計図」として機能していた面が確かにあったのです。
「発展の目標」から「忠誠の命令」へ――言葉が異論を許さなくなるとき
ところが、時代が下るにつれて、スローガンの性格は変わっていきます。大正デモクラシーの時代には、都市部を中心に自由の空気が広がり、洋服をまとい、カフェで議論し、個人の権利や政治参加を語る雰囲気がありました。この頃、「富国強兵」は一度、過去の遺物になりかけたようにも見えます。
しかし、1929年の世界恐慌を契機に、日本社会は急速に不安定さを増します。農村の疲弊、失業の拡大、生活の行き詰まり。こうした現実に直面した人々が政党政治への不信を募らせ、「強いリーダーシップ」や「国力回復」を求め始めると、そこへ入り込んだのが“国家の危機”を強調する言葉でした。かつて近代化の合言葉だった富国強兵は、昭和に入ると、より重い響きを持つ国家目標へと姿を変え、社会に再び強く浸透していきます。
日中戦争以後は、政府主導の国民運動として国民精神総動員運動が展開され、「挙国一致」「尽忠報国」「堅忍持久」といった標語が強調されました。ここで言葉は、「発展の目標」を示す道しるべから、「忠誠を求める命令」に近いものへと変質していきます。いったん“正しさ”として定着した言葉は、政策を吟味する道具ではなく、反対意見を封じる合言葉として働きやすくなるからです。
そしてこの転換を決定的にしたのが、教育とメディアでした。学校教育は価値観を日常化させ、新聞やラジオは熱狂を共有させます。戦況や国際関係の解釈が、特定の言葉と結びついて繰り返されると、国民はそれを「常識」として受け取りやすくなります。言葉は情報であると同時に、感情と倫理を組み替える装置にもなっていきました。
暮らしを縛る標語、戦争を神話化する理念語――「疑うこと」さえ許されなくなる
総動員の段階になると、言葉はさらに生活の隅々へ入り込みます。「ぜいたくは敵だ」のような標語は、戦争が“国家の政策”であるだけでなく、“日々の暮らし方”そのものを評価する尺度へと変えてしまいました。買い物、食事、楽しみ、服装。そうした個人の判断が、「戦争協力の度合い」で見られる空気がつくられていきます。さらに「欲しがりません勝つまでは」という言葉が流通すると、我慢は美徳を超えて義務になり、生活の苦しさが「耐えるべき正しさ」へと塗り替えられていきました。
加えて、理念語が重なることで、現実の戦争は“神話”や“道徳”の領域へ持ち上げられます。「国体明徴」「八紘一宇」「大東亜共栄圏」「東亜新秩序」「聖戦」「滅私奉公」「一億玉砕」「本土決戦」といった語彙は、戦争のコスト、外交の失策、被害の具体像といった検証を遠ざけます。疑うことが不敬・非国民と見なされやすい空気が生まれると、社会の中で“問い直す力”が急速に弱まります。
ここまで来ると、「富国強兵」そのものがただちに戦争を生む呪文だった、という単純な話ではなくなります。むしろ、国家の進路を一本化する思考の枠として機能し、そこへ総動員、忠誠、そして神話化の言葉が重なっていくことで、社会が戦争へ向かう道を自ら狭めていった――この連鎖として見るほうが、実態に近いのではないでしょうか。
最後に、現代に引き寄せて一言だけ添えるなら、言葉は便利だからこそ危うい、ということです。短い言葉ほど、心地よく、分かりやすく、反射的に受け入れやすい。しかしだからこそ、「その言葉が何を正しいことにし、何を語れなくしているのか」を点検する必要があります。私たちが“空気”に流されないための第一歩は、まさにその言葉の中身を、もう一度ひらいて見ることなのだと思います。