 6月4日、厚生労働省は、長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の対象となる75歳以上の高齢者の保険料について、旧制度で国民健康保険(国保)に加入していた場合との負担額の増減について、全国調査した結果を公表しました。それによると、75歳以上の高齢者がいる国保加入世帯では、その7割の世帯で負担減になると推計しました。
6月4日、厚生労働省は、長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の対象となる75歳以上の高齢者の保険料について、旧制度で国民健康保険(国保)に加入していた場合との負担額の増減について、全国調査した結果を公表しました。それによると、75歳以上の高齢者がいる国保加入世帯では、その7割の世帯で負担減になると推計しました。
今回の調査は、4種類の家族構成に3種類の収入額を組み合わせた12のモデルケースについて、保険料額の増減を、全国すべての市町村で集計しました。さらに、平成18年度国民健康保険実態調査から作成した都道府県別モデル世帯別所得分布をあてはめて、世帯ごとの保険料増減を推計しました。
保険料額の変化を「市町村別」に分析してみると、単身者世帯の場合9割以上の市町村で保険料が減少しました。夫婦世帯や高額所得の世帯でも7~8割の市町村で保険料が減少しました。反面、子供との同居世帯では保険料が増加する市町村が減少する市町村を上回りました。
一方、調査結果を「世帯ごと」にみてみると、全体では69%の世帯で保険料が減少しました。所得区分ごとでは、高所得者(年金の収入が292万円以上)で負担が減った世帯の割合は78%で、低所得者(177万円未満)の61%を上回わりました。これは、国保の保険料が自治体の一般会計から補填され、結果的に「国保料が安く抑えられていた大都市や地方の中心都市で、低所得世帯の減少割合が約2割と低かったためです。また、国保料の算定基準の一つである資産割割が、長寿医療制度ではないために、資産を有する所得の高い人も軽減されるケースがあるためと推測されます。
さらに、厚労省は与党の作業チームがまとめた低所得者への負担軽減策を導入した場合の試算も公表しました。この試算では、全体での減少割合が75%と6%上昇するとしています。
厚労省の調査結果には、都道府県別の保険料の減少傾向がまとめられています。その結果を基に、長寿医療制度創設に伴って、市町村国保の保険料に比べて負担が減少する世帯の割合と、自民公明の与党が取りまとめた新たな負担軽減策による負担軽減世帯の割合を、一つの表に集計してみました。
沖縄を除いて、国保会計を一般財源によって支えていた都道府県で負担の減少率が低いことが如実に表れて結果となりました。与党の軽減策には所得割への軽減も盛られていますが、その効果が前者で負担軽減が進まなかった地位に重点的に配慮されていることがよく分かります。
全体的には、高齢者の負担軽減と住んでいる地域での格差の減少という二つの点で、長寿医療制度の導入と今回の負担軽減策が的を射た対策であることが理解できます。
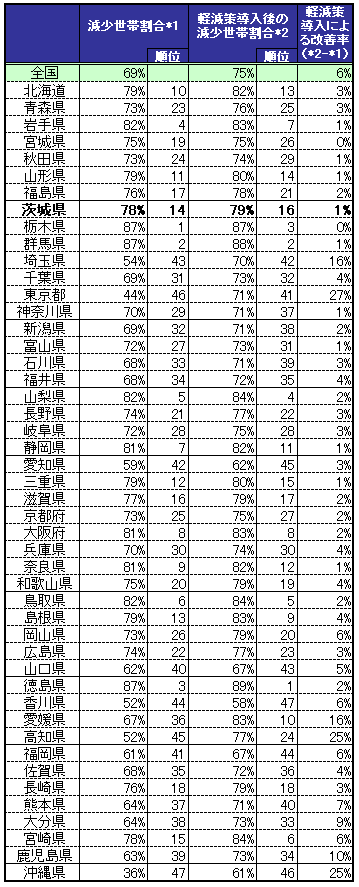
以下に、厚労省が6月4日に公表した「長寿医療制度創設の伴う保険料額の変化に関する調査-結果速報」を入手しましたのでスキャンした内容をPDFでアップしました。ご参照下さい。
 参考:長寿医療制度創設の伴う保険料額の変化に関する調査-結果速報(PDF版)-
参考:長寿医療制度創設の伴う保険料額の変化に関する調査-結果速報(PDF版)-




野党の廃止法案の参議院での審議時間が短く、審議時間か何かは民主党の委員長権限で決定した、みたいなことをネットで聞いたのですが、本当なのでしょうか?
本当ならば、十分な審議と徹底的な議論をと与党を批判する民主党の方針が2枚舌ということですし、国会終盤でテレビ上に、絵になる有終の美を見せたいだけに見えてしまいます。
党別や何かの審議時間や、採決の時系列を、出してくれると助かります。
いつも拝見させて頂いております、井出議員のページは国、県の行政を早く分かりやすく投稿されており大変勉強になります、今後とも記事の投稿と議員の活躍期待します。