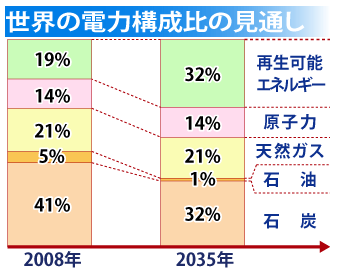 公明党は、日本再建をめざす重点政策(案)の柱に「防災・減災」や「新エネルギー」など7つの政策を打ち出しました。その中でも、成長性に期待が高まる「グリーン経済」の現状について整理してみました。
公明党は、日本再建をめざす重点政策(案)の柱に「防災・減災」や「新エネルギー」など7つの政策を打ち出しました。その中でも、成長性に期待が高まる「グリーン経済」の現状について整理してみました。
公明党が成長戦略の柱として打ち出した「グリーン経済」とは、石油や森林など自然資源の大量消費によってもたらされた産業構造を転換し、“環境保護と経済成長の両立”をめざす考え方です。
石炭など化石燃料が中心の今の「ブラウン(茶色の)経済」と違って、太陽光や風力、地熱、水力といった地球環境に優しい再生可能エネルギー(再エネ)がグリーン経済の中心です。
資源エネルギー庁の「エネルギー白書2011」で、世界の電力量構成比における再エネ(水力含む)の割合が2008年の19%から35年の32%への増加予測が示されているように、大きな成長が期待できる分野でもあります。
事実、国連環境計画(UNEP)の報告書によると、昨年はダムといった大規模な水力発電を除いた再エネ投資が前年比17%増加し、史上最高額の約21兆円でした。
今後、本格的な普及期を迎える再エネ分野は、雇用効果も大きい。非政府組織(NGO)などで構成される国際団体「21世紀のための自然エネルギー政策ネットワーク」(REN21)によれば、全世界で約500万人分の雇用が生み出されたとしています。日本の昨年平均の完全失業者数が284万人であることを考えれば、その数の大きさが実感できます。
また、日本のグリーン経済の裾野は、多方面でも着実に広がっています。
例えば、日本が誇る自動車産業は省エネルギー(省エネ)に優れた次世代自動車の世界市場でも一歩先を行っています。トヨタ自動車は、ガソリン使用を大幅に抑制したハイブリッド車の累計販売台数が、国内外合計で400万台(4月末時点)を突破したと発表しました。特に米国での人気が高く、発売当時は「変わり種扱い」だった自動車が、今や経済を支える主力製品へと成長しつつあることを印象付けています。このほか、省エネと省スペースで食料自給アップに貢献する「植物工場」や、多機能携帯端末(スマートフォン)の省電力化に不可欠な「リチウムイオン電池」などもグリーン経済を担う注目の分野です。
さらに、再エネの代表的存在の太陽光発電も「グリーン経済」の主力として成長しています。日本各地で大規模な太陽光発電施設「メガソーラー」の建設が、大手企業を中心に進められており、雇用も含めた地域経済の活性化への期待が高くなってます。また、7月から始まった再エネの固定価格買い取り制度が一般家庭での太陽光発電設置を促しており、全国的な再エネ利用の拡大とともに大きな経済効果も見込まれています。
「省エネ経済」は実現可能
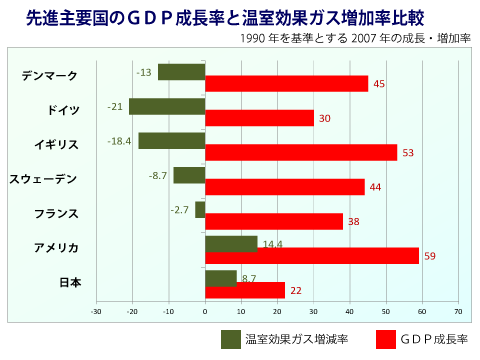
東京電力福島第1原発事故や原油高騰によるエネルギー不足が、経済に深刻な影響を与えると懸念されています。その理由は、経済成長にはエネルギー消費を増やすことが不可欠という考えが根強いからに他なりません。
その一方で、千葉商科大学の三橋規宏名誉教授は、そうしたイメージとは異なった事実を示しています。
三橋名誉教授は、1990年から2007年までの間における主要先進国の国内総生産(GDP)の伸び率と、化石燃料使用による温室効果ガス排出量の増加率の関係を分析。それによると、グリーン経済先進国のデンマークやドイツ、スウェーデンなどではGDPが成長しても、温室効果ガス排出量は逆に少なかった事実を示しています。
例えば、デンマークでは、この期間のGDPが45%増加したのに対し、温室効果ガスは13%減少しました。これは再エネ利用の拡大で、企業の生産活動が化石燃料に依存しなくてもよくなったからです。
逆に、再エネや省エネ普及が遅れる日本や米国では、経済成長とともに温室効果ガスが増える関係にあります。ただし、重要な点は日本も1980年代に、エネルギー消費の増加に頼らず経済成長を実現した時期があるという点です。
これは、1970年代から80年代にかけて2度の石油危機が発生したことで、収益圧迫を避けようとした企業が、エネルギー消費を抑えた生産を意識したことで実現したものです。ところが、90年代に入り原油価格が再び安くなり始めたことで、省エネ型生産は割高になり姿を消してしまいました。
80年代のような省エネ型経済成長の再現に疑問を投げ掛ける声も、確かにあります。しかし、エコ住宅や電気自動車、LED(発光ダイオード)照明など優れた省エネ性能を発揮する製品や技術開発が格段に進んだことを踏まえれば、不可能とは言い切れません。
グリーン経済の構築には、発電効率に優れた高効率火力発電の推進なども合わせて、具体的に政策を進めることが必要です。



