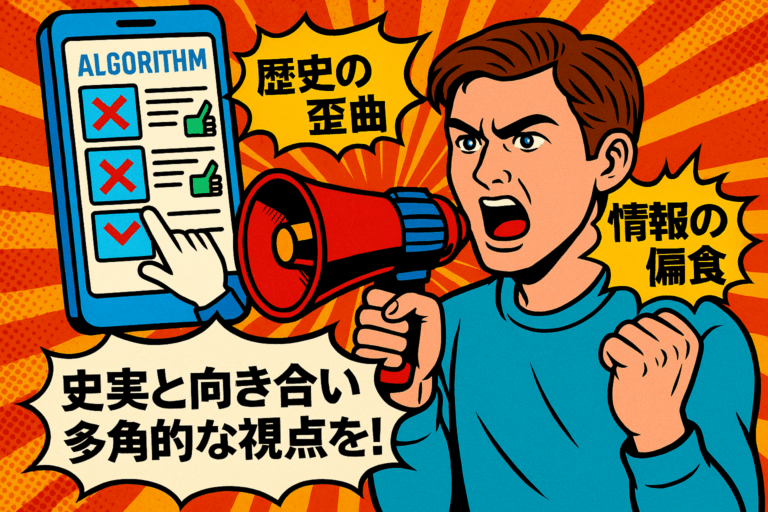岐路に立つ企業城下町・日立市
日立市が進めている「常陸多賀駅周辺地区整備事業」は、市の将来ビジョンを象徴するプロジェクトです。老朽化した駅舎を刷新し、バス専用線(BRT)との接続を強化、さらには飲食・交流・情報発信といった機能を加え、市民の暮らしと来訪者の利便性を飛躍的に向上させる構想が描かれています。
しかしその一方で、2025年夏(8月5日)、私たちの地域経済の根幹を成してきた日立製作所が、家電事業を担う子会社「日立グローバルライフソリューションズ(GLS)」の売却を検討しているとの報が駆け巡りました。その買収候補にはサムスン電子やLG電子といった国外資本が名を連ねており、将来的に経営方針の変更や拠点再編が行われる可能性も現実味を帯びています。
こうした状況の中で、常陸多賀駅整備という“前提”と、GLS売却という“現実”の間に、深刻な「時間的・構造的なズレ」が生じていることに、私たちはいま真剣に向き合うべきではないでしょうか。
GLS売却がもたらす「5年後の崖」
日立GLSは、売却直前の2024年度に売上高3,676億円、営業利益392億円を計上する優良企業です。これは決して不採算による切り離しではなく、日立製作所本体がBtoC事業から撤退し、高収益なBtoB事業へ集中するという戦略転換の一環として進められているものです。
売却の条件には「5年間の雇用維持」と「日立ブランド使用許可」が含まれていますが、これは言い換えれば「5年後の構造的変化」を予告する時限措置でもあります。
新たな所有者が5年間の“執行猶予”を終えた後、グローバルな競争原理に基づいて拠点統廃合を進めることは想定に難くありません。特に、老朽化が進んだ国内の製造拠点が、最新鋭のスマートファクトリー(たとえばLGの「灯台工場」)に置き換えられた場合、雇用の喪失、研究開発部門の流出、さらにはサプライチェーンの海外移転という形で、地域全体の経済循環に深刻な影響を及ぼす可能性があります。
つまり今、私たちは「表面上は変わらないが、5年後に一気に変わるかもしれない未来」の只中にいるのです。
整備事業の根拠を支えていた「安定」はすでに崩れている
常陸多賀駅整備事業は、2025年(令和7年)3月に基本設計が完了しました。その直後、8月にGLS売却の報道が出たことから、この整備計画は売却前の経済前提をもとに立案されていたことになります。
具体的には、日立製作所多賀事業所の持続的な稼働を前提とした通勤需要や人流、地元商業圏の購買力が計画の根幹に据えられています。駅構内に設けられる予定のカフェや情報発信スペースも、そうした安定した人口・経済活動の存在があることを前提としています。
しかし、GLSの将来的な縮小・撤退リスクが現実味を帯びた今、その前提は大きく揺らいでいます。5年後に雇用が大幅に削減されれば、整備した施設の利用者は想定を大きく下回り、“白い巨象”と化す危険も否定できません。
日立市の財政状況も、決して余裕はない
2023年度の決算によると、日立市の経常収支比率は99.8%。つまり、市の収入のほぼ全てが日常的な支出(人件費や借金返済など)で消えており、新たな財政ショックや投資に対応する“余力”が極めて乏しい状況にあります。
この中で進められる数十億円規模のインフラ投資は、「未来への投資」であると同時に、「未来の負担」を後回しにすることにもつながりかねません。人口減少と高齢化が進むなか、将来世代に大きな債務を残すような構造になっていないか、今こそ冷静な検証が必要です。

今、必要なのは「中止」ではなく「一時停止と再構築」
誤解してはならないのは、私は常陸多賀駅整備事業に反対しているのではないということです。むしろ、駅という公共空間を活用してまちを活性化するビジョンそのものは、これからの時代にこそ求められるものです。
ただし、それは「前提条件が変わった今」、その変化に応じて見直されるべきだというのが本質です。GLS売却という「状況の重大な変化」に対し、計画の戦略的再評価(リスコープ)が不可欠です。
たとえば、次のような方向転換が考えられます。
- 商業スペースの一部を、テック系スタートアップのためのコワーキングスペースに転用する
- 茨城大学工学部のサテライトキャンパス、リスキリング拠点、創業支援施設などを導入し、新たな「知の集積地」とする
- 日立のブランド資産を活用し、観光や交流人口を呼び込む「産業遺産×未来技術」型の展示・体験施設を設ける
- 駅東側(海側)の整備、特に国道245号線へのアクセスを再検討する
このように、整備計画を“通勤者の利便性向上”にとどめるのではなく、“地域経済の多角化・再構築”という視点で再設計することが、今後のまちづくりにとって不可欠なのです。
「企業城下町」から「強靭な地域経済」へ
私たちのまち・日立市は、その名の通り日立製作所とともに発展してきました。それは誇りある歴史です。しかし、これからの時代を生き抜くためには、その構造そのものを再定義する必要があります。
「一つの企業に依存しすぎない」「多様な産業・人材が共存できる」「変化に柔軟に対応できる」――そのような新しい都市の姿を描くことが、今回の整備事業の本当の意義であり、使命ではないでしょうか。
いま私たちに求められているのは、過去の延長線上にある整備ではなく、変化を前提とした再設計=“知的で柔軟なまちづくり”です。
市民一人ひとりの「問い」が未来を創る
整備事業を止めるべきだと訴える声ではありません。ただ、「いま本当にこのままでよいのか」と問い直すことこそが、責任ある市民社会の第一歩だと私は考えます。
5年という猶予期間は、ただ静かに過ごす時間ではありません。日立市が、この変化にどう向き合い、どう未来を創るのか。その選択によって、この整備事業は「過去の遺産」になるか、それとも「未来の跳躍台」になるかが決まるのです。
日立というまちの未来を、他人任せにしない。私たち自身の手で考え、選び、創り出す――今こそ、その時です。