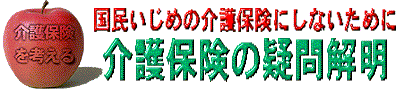
Q16:介護保険制度で市町村の福祉財源はどうなる?
高齢者の介護保険料総額の6倍の財源が生まれる
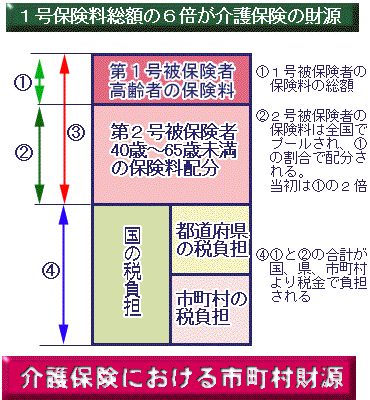 市町村は、独自に1号被保険者の保険料を決めることができる。
市町村は、独自に1号被保険者の保険料を決めることができる。
1号被保険者の保険料に高齢者人口を掛けた総額に、所得格差を調整する調整交付金が加わり、①の財源が確定する。
2号被保険者の保険金は一度、中央基金にプールされる。その保険料は、①の総額の割合で各市町村に比例配分される。介護保険導入当初は、世代間の人口比により、①の約2倍の金額が市町村財源となる。
1号被保険者の保険料①と2号被保険者の保険料②の合計額が、介護保険保険料からの財源③となる。③と同額が税金から負担される。その割合は、国と都道府県と市町村が、2:1:1となる。
これらを単純化すると、1号被保険者の保険料総額①の6倍が、その市町村の介護保険の給付財源となる。
つまり、高齢者の保険料をいくらに設定するかによって、外部(中央基金や国、都道府県の税負担)からの資金を呼び込めるかが決められるという仕組みになっている。
介護サービスの水準が低いから、保険料を下げるという市町村もあるだろう。
市民の理解を得て高めに設定した保険料から、多くの財源を得て、サービスの強化や「横だし」「上乗せ」のサービスの充実に当てる市町村も出るはずだ。
正に、保険料決定については、住民を巻き込んでの議論が不可欠になる。
| このページは、茨城県議会井手よしひろの公式ホームページのアーカイブ(記録保管庫)の一部です。すでに最終更新から10年以上経過しており、現在の社会状況などと内容が一致しない場合があるかもしれません。その点をご了解下さい。 |


