医療費と介護費用の限度額が引き下げられ、負担が半減するケースも
高齢世帯では医療保険と介護保険の二つの負担が著しく高額になることがあるため、その軽減策として、二つの負担を世帯で合算して上限を設ける「高額医療・高額介護合算制度」が、2008年度(平成20年度)に新たに創設されることになりました。
一般所得者の場合、75歳以上は限度額を年56万円、70~74歳は年62万円とするなど、所得に応じてきめ細かく設定します。その結果、75歳以上の一般所得者は、負担が最大で年約42万円も軽減されることになります。現行制度では、75歳以上で一般的な年収の場合、医療が年約53万円、介護が年約45万円の計約98万円が負担限度額です。合算制度が導入されると、限度額は56万円となり半分近くで済む計算です。
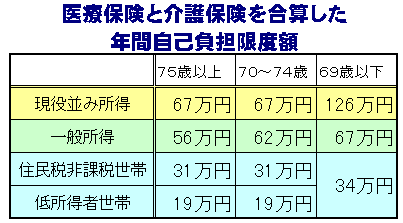
この合算制度は、公明党が負担軽減の必要性を訴えたことにより、実現したものです。
医療費と介護費の合算制度の対象は、健康保険組合や政府管掌健康保険(政管健保)、国保など各健康保険の加入者本人と扶養家族の医療と介護サービスの総額の合計額で計算されます。
しかし、一つの世帯を形成していても異なる健康保険に加入している家族は、事務処理が複雑になるなどの理由から合算が認められません。高齢者の場合、厚生労働省は同じく20年度から後期高齢者医療制度を新設して75歳以上は自動的に加入させることになります。高齢者夫婦のみの世帯では、ともに74歳以下の時は世帯合算の対象になっていたのが、どちらかが75歳に達した時点で加入する健康保険が異なると世帯合算できなくなる懸念があります。子供の扶養家族になっているような場合も75歳になると自動的に合算対象から外されまこれらの世帯では負担額が急増する可能性もあります。
厚労省はこうしたケースについて、個別に医療と介護の合計限度額を設定して対応する考えです。

医療制度改革:高額合算制度、年間上限額定める 厚労省、「アメ」強調
毎日新聞(2007/2/20)
医療・介護保険を合わせた年間自己負担上限額(08年4月~) 08年4月から、医療、介護保険をセットにして自己負担額に上限を設ける「高額医療・高額介護合算制度」がスタートするが、厚生労働省は19日、新制度の収入、年齢別の年間上限額を定めた。70~74歳で一般的な所得(夫婦世帯で年収520万円未満)の人は、現在の年額約103万円が62万円に下がる。
現行制度では、医療、介護とも個別に上限額が設定されている。75歳以上(一般所得)の人の上限額は、医療約53万円、介護約45万円で、年間自己負担額は最高約98万円に達する。しかし、厚労省は昨年、75歳以上(同)の場合、医療、介護を合わせて56万円を超せば、超過分を払い戻す制度を作ることにした。
19日はこの基準を年齢、収入別に11区分。69歳以下で一般所得なら、上限額は今の約109万円から67万円に下がる。収入別(75歳以上)では、▽現役並み所得者(夫婦世帯で年収520万円以上)=67万円▽住民税非課税世帯=31万円▽年金収入80万円以下などの低所得者世帯=19万円--など。同様に70~74歳は19万~67万円、69歳以下は34万~126万円。
厚労省は昨年の医療制度改革で、お年寄りの負担が増える医療政策を相次いで打ち出している。合算制度は、「高齢者いじめ」のイメージを払しょくする狙いもある。



