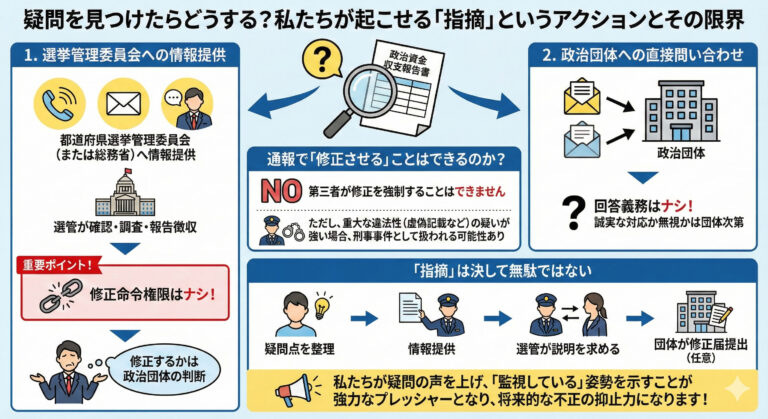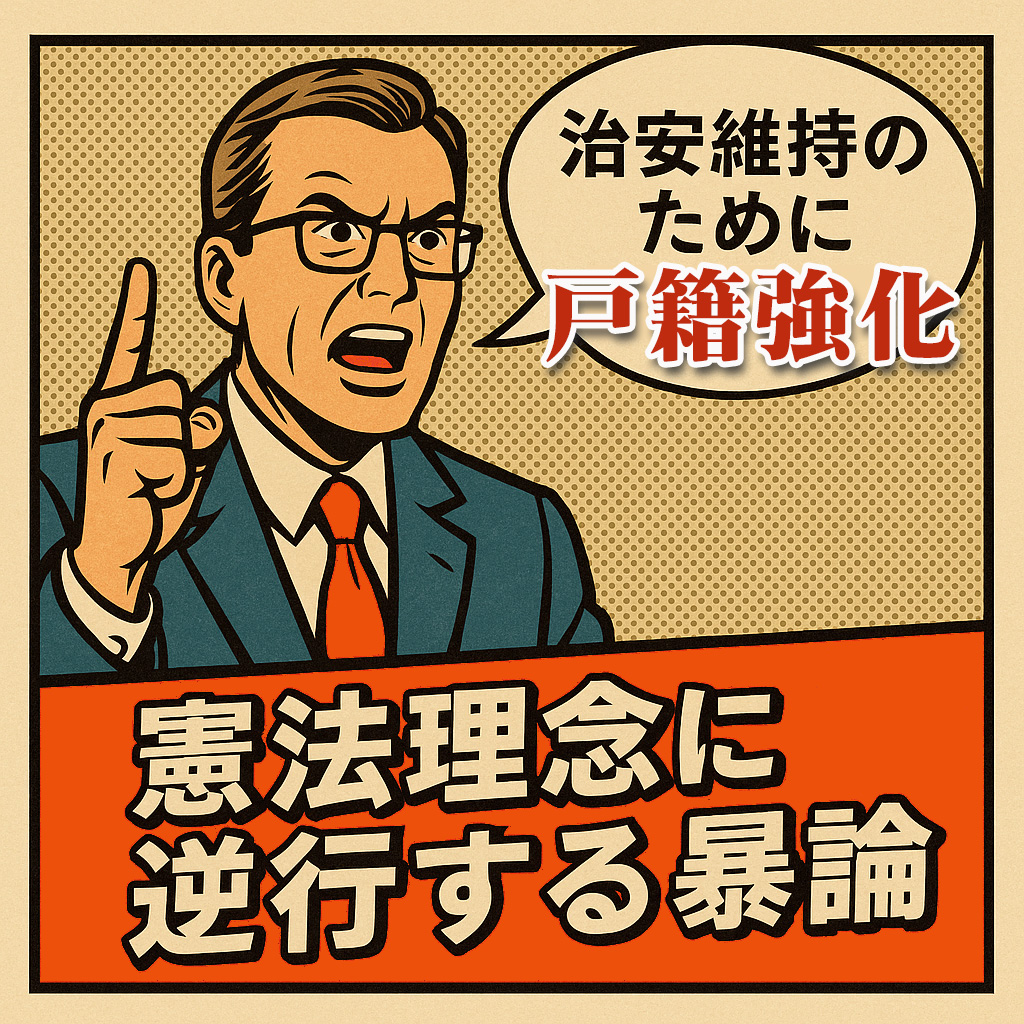
最近の街頭演説やテレビ番組などで、参政党・神谷宗幣代表が戸籍制度や夫婦別姓制度について発言を繰り返し、その内容がSNSなどで大きな波紋を呼んでいます。「戸籍に父親や母親の出生地まで載せるべきだ」「夫婦別姓は治安を悪化させる」などの主張は、一見すると合理的で説得力もあります。
「戸籍制度はもっと厳しくしましょう。 戸籍制度厳しくして、もっと細かい表記をどんどん入れていきましょうよ。
家族関係とかも兄弟とかまで全部乗るようにしましょうよね。
戸籍を電子で取ったらお父さんお母さんの出生地もちゃんと乗ってるような、そういう戸籍をもっと充実して作りましょうよ。
これはね、やっぱり犯罪捜査とかそういうものにすごい役に立ちます」
しかし、立ち止まってよく考えてみると、法制度の根本的な理解や憲法の理念を著しく欠いており、国民の基本的人権や個人の尊厳を軽視した危険な発言であると言わざるを得ません。
(参政党・神谷宗幣代表の街頭演説より)
戸籍に親の出自まで記載し、管理を強めるということは、戦後日本が築いてきた「憲法に基づく人権保障」という基本理念に明確に背くものです。
とりわけ見過ごしてはならないのは、この発言が、日本国憲法第14条で厳しく禁じられている「門地による差別」を事実上容認・助長しかねない性質を持っているという点です。
「門地」とは何か──歴史が教える差別の根
憲法第14条第1項は、すべての国民は法の下に平等であり、「人種、信条、性別、社会的身分又は門地」によって差別されてはならないと定めています。ここでいう「門地」とは、本人には選べない「生まれ」や「家柄」、すなわち親の出自や家庭環境のことを指します。
これは、明治期から戦前・戦中にかけて存在した「家制度」による差別、あるいは被差別部落出身者への不当な扱いといった歴史的経緯を踏まえ、個人の尊厳を保障するために設けられた重要な規定です。誰がどこで生まれ、どのような親のもとに育ったかではなく、すべての人は「個人として」尊重されるべきだというのが、日本国憲法の基本的な考え方なのです。
ここでいう「門地」とは、生まれや家柄、親の出自など、自分の努力ではどうすることもできない「生まれつきの属性」を意味しています。つまり、親の職業、身分、出身地などによって社会的に不利益を受けることがあってはならないというのが、現代日本社会の出発点なのです。
「親の出生地を戸籍に記載する」という発想の危うさ
では、親の出生地を戸籍に記載するという提案がなぜ問題なのでしょうか。
それは、まさに「人がどこから来たか」という情報を国家が記録し、それが「評価の対象」となる可能性を孕んでいるからです。たとえば、ある地方の出身であることが、就職や結婚、さらには治安政策上の「監視対象」に結びついてしまう。これでは、事実上「門地による差別」を制度化することになりかねません。
日本は、「被差別部落」や「特定地域出身者」への差別と長く向き合ってきました。その過程で、「出自を記録しないこと」「出自で人を判断しないこと」が人権尊重の大原則として定着してきたはずです。神谷代表の提案は、こうした歴史的反省を無視し、憲法が禁じる門地差別をあらためて制度の中に組み込もうとするものに等しいのです。
さらに、「なりすまし防止」や「外国人による不正防止」という名目で戸籍制度を強化しようとする姿勢は、「治安維持」を理由に人権を制限してきた歴史的過ちと重なります。戦前の治安維持法や戦時中の国民監視体制がまさにそうでした。
出生地情報を戸籍に記載することの危険性
参政党の親の出生地を戸籍に記載するという提案は、一見して「治安対策」や「本人確認の強化」のように映るかもしれません。しかし、そうした制度が実際に運用され始めれば、「どこの出身か」という情報が社会的評価や差別の温床となるリスクが避けられません。
たとえば、ある地域の出身であることを理由に、就職や結婚の場で不利な扱いを受ける。あるいは、特定の地域出身者が「監視対象」とされてしまう――こうした状況は、まさに「門地による差別」を制度として固定化する結果になりかねません。
私たちの先輩は過去に、出自によって人の価値が決められていた時代を経験し、多くの人々がその偏見と闘ってきました。その反省のうえに立ってこそ、現在の法制度が築かれてきたのです。
治安維持と人権保障のバランスを見失ってはならない
「なりすまし」や「不正入国」を理由に戸籍制度を強化するという議論は、過去にも繰り返されてきました。ですが、治安維持を名目にして人権を制限するという発想は、戦前の治安維持法に象徴されるような国家による監視社会の到来を想起させます。
もちろん、社会の安全は大切です。しかしそのために、すべての人の尊厳やプライバシーを犠牲にしてよいわけではありません。むしろ、個人の自由や人権が尊重されてこそ、健全な社会が成り立つのではないでしょうか。
子どもたちの未来に、差別の再来を残さないために
「親が誰か」「どこから来たか」が記録され、その情報が一生つきまとう社会。そんな未来を、私たちは次の世代に手渡したくありません。
人は、誰の子であるかによって評価されるのではなく、どのように考え、どのように生きているかによって尊重されるべきです。その原点を忘れずに、憲法が守ろうとする人権の理念を、私たち一人ひとりが大切にしていかなければなりません。