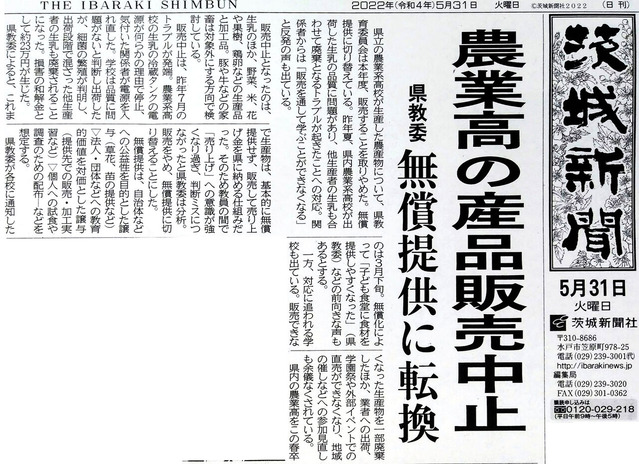大阪の米販売会社「三笠フード」が、工業用に限定された「事故米」を食用として販売した事件で、食の安全がまた揺らいでいます。これらの米には有機リン系の農薬成分メタミドホスや発がん性のあるアフラトキシンB1を含むものがありました。
その後の調査で、米は酒造メーカーや製菓メーカーに売却されたことが分かり、製品の回収騒ぎにまで発展しています。食に対する不安をもたらしたという意味で、米販売会社の社会的責任は大きなものがあります。
繰り返される食品偽装を防ぐ手だてはないのでしょうか?
ミニマムアクセス米の一部が事故米に
日本は世界貿易機関(WTO)に加盟していますが、この協定に基づきミニマムアクセス米といわれる、決められた最低限の量の米を外国から輸入しなければならないことになっています。
輸入された米は国内産のものと比べて食味などが劣るため、国内で売られることはあまりありません。そのほとんどが備蓄に回されますが、このミニマムアクセス米のうち、保管中にカビが発生したり、水濡れ等の被害を受けたもの、または基準値を超える残留農薬等が検出されたものを「事故米」といい、のり(接着剤)などの工業用に使うという条件で農水省が民間に売却しているのです。
報道によれば、事故米を入札する会社はきわめて限られていたようですが、「三笠フーズ」は事故米を積極的に買い入れ、食用米の値段で酒造メーカーや製菓メーカーに販売して利益を上げていたのです。
立ち入り調査には強制力なし
問題の米販売会社に対して、農水省は96回にわたり立ち入り調査を行っていましたが、不正を見抜けませんでした。その原因は立ち入り調査が事前通告のもとに行われていたためです。そもそも農水省の立ち入り調査には強制力がないという問題があったのです。
愛媛県のうなぎ加工業者の例では
たとえば9月6日に警察が強制捜査を行った愛媛県のうなぎ加工業者の場合は、8月に行われた農水省の立ち入り調査で、ひとつのいけすしか調べることができず、この時点では業者の偽装を立証することができませんでした。この業者は中国産のうなぎの蒲焼きを国産と偽っていたのですが、農水省の改善指導には罰則がないため、効果はありませんでした。業者は2001年、2004年と改善指導を受けていたにもかかわらず、不正を繰り返していたのです。
現在のJAS法では、不正を行った業者を公表することはできますが、罰則などはないため実効の薄いものになっています。また相手が悪意を持って不正を隠そうとした場合、強制捜査の権限がないため、真実を突き止めるのは難しいことになります。
このため農水省は警察などにJAS法違反で告発するより方法がないのですが、これまで警察によるJAS法違反の捜査はほとんど行われたことがありません。警察はJAS法違反より厳しい不正競争防止法で食品偽装を取り締まる方針のようですが、このため、農水省の告発でそのまま警察が動くという連携にはなっていないようです。
JAS法の権限強化と警察との連携が不可欠
同時期に、大阪市の業者が中国産のタケノコ水煮を「国産」と偽装表示して販売したという事件も起こり、農水省はこれにも改善指示を出しました。製造した茨城県の業者に対しても、県はJAS法と景品表示法に基づく改善指示を行っています。繰り返される食品偽装に対して、罰則規定がない改善指導というのはあまりに無力なように思われます。食の安全に対してはもう少し強い権限を持って臨む必要があるのかもしれません。
消費者庁創設により食の安全守る体制強化
消費者庁が創設されると、JAS法や食品衛生法は消費者庁に移管されることになっています。
今後は、生産者育成取いう基本的姿勢が、消費者保護へと180度転換されることを期待します。
また、罰則強化も必然的な流れとなっています。
監督官庁である農林水産省の責任も指摘される中、消費者庁設置に向けての建設的な議論を積み重ねていく必要があります。