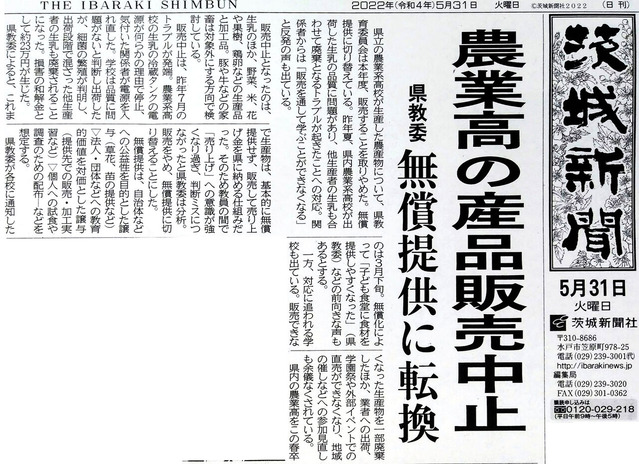7月1日、茨城県のドクターヘリが稼働。最初に出動したのは小美玉市内の農作業中に発生したトラクター転倒現場でした。
7月1日、茨城県のドクターヘリが稼働。最初に出動したのは小美玉市内の農作業中に発生したトラクター転倒現場でした。
日本における農作業中の死亡事故や傷害事故は驚くことに、国全体で、その実態をつかむための調査は行われていません。農作業死亡事故数は、農水省が人口動態調査から拾い出して集計しているというのが実態です。傷害事故に至っては調査対象ではなく、その全容はどこにも把握されていません。
農作業には危険を伴うものが少なくありません。労災保険の加入が欠かせませんが、農業従事者の労災保険の加入状況は低く、加入率に地域間格差があるのも現実です。
事故を未然に防ぐことはもちろんですが、万が一のときの補償も営農・生活の安定にはかかせません。加入率が伸びない理由には、制度そのものを知らない、入りたくても加入窓口がない、などの理由が挙げられています。
これらの点を見ただけでも、農作業従事者の安全を守るための取り組みが、遅れていることが明らかです。
データによれば、農作業事故による死亡者は、農水省が1971年に調査を開始して以降、毎年400人前後で減ることは無く、2008年までの38年間で1万4664人にも上っています。発表されている最新データ(平成20年に発生した農作業死亡事故の概要)を見ると、平成20年の死亡者は374人、65歳以上の高齢者の事故は296人となり、事故全体に占める割合は79%と高くなっています。
農業白書(平成21年度 食料・農業・農村白書)では「高齢農業者の活動状況」の項で、「高齢者の農作業事故が多い要因については、加齢による心身機能や判断力の低下によるものが主なものであると考えられています。このほか、新たな機械への投資意欲が低く、安全性の低い旧型の機械をそのまま使用していること等も農作業事故を多くする要因といわれています」と高齢者に注意を喚起するとともに、万一事故に遭った時のために、労働者災害補償保険に加入することも勧めています。
死亡事故のみならず、後遺症が残った重症事故は死亡事故の何倍にものぼると想定されており、他産業が確実に死亡労災を減らしてきた中で、農業はほとんど変わっておりません。
さらに言うまでもなく、農業は特に高齢化が著しく進展している分野であり、政府はもとより、地方自治体や関連機関・団体に、農業従事者の命を守る取り組みが求められています。
また今年の夏は、熱中症による死亡者が多くなっていますが、農業でも例外ではなく、7月24日付の日本農業新聞に「熱中症 猛暑日なお厳戒を 相次ぎ農作業中死者」と報道されました。農作業中の熱中症による死者の数は毎年10人前後にもかかわらず、今年は既に茨城や栃木、埼玉、石川などから10人近くにも上るという報告が農水省に寄せられています。
本年3月、政府は今後の農政展開の方針を示す「食料・農業・農村基本計画」を閣議決定しました。その中で、農作業安全対策の推進を掲げましたが、農作業事故問題を、基本計画に項目を立てて位置づけたのは初めてのことです。
平成21年度農業白書においても、農作業事故の実態について、初めて踏み込んで表記されました。これまで遅れてきた農作業従事者に対する安全対策は、もう待ったなしの状態です。農水省をはじめとした行政が、予算を措置し事故防止の旗を振り、農業団体や関連産業が一体となって全力を挙げるべきです。「注意しろ」と言うだけで農業者任せでは、危機的状況を改善することはできません。