8月4日、民主・自民・公明の三党は、現行の子ども手当の額を今年10月から見直し、来年度からは、以前の児童手当の内容を復活させて、所得制限を設ける方針で合意しました。
合意では、現行の中学生までの1人当たり月1万3000円の支給額を、子ども手当の「つなぎ法」の期限が切れる10月分から、3歳未満と3~12歳の第3子以降は1万5000円、3~12歳の第1子、第2子と中学生は1万円にそれぞれ変更。所得制限は2012年度から導入し、水準は年収(額面)960万円程度としました。必要な予算額は2.2兆~2.3兆円程度となります。
所得制限の対象となる世帯も、年少扶養控除の廃止により負担増となっているため、軽減措置を検討するとしています。
また、今年10月から半年間の対応については、政府が「子ども手当に関する特別措置法案」を今国会に提出して成立を図り、現金支給を継続します。平成24年度以降については、特措法案の付則に「児童手当法に所要の改正を行うことを基本とする」と明記。子ども手当を廃止して、児童手当制度を復活させることになります。
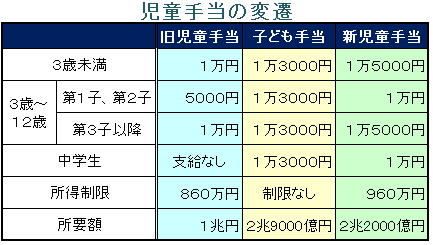
3党合意のポイント
今回の3党合意により、現行の「子ども手当」を来年4月から廃止し、自公政権時代の「児童手当」をベースにして拡充する方向になりました。具体的な支給額ですが、従来の児童手当と比較すると、3歳未満が月額1万5000円(児童手当では1万円、プラス5000円)、3歳から12歳(小学校卒業まで)は第1、2子が1万円(児童手当5000円、プラス5000円)、第3子以降が1万5000円(児童手当では1万円、プラス5000円)。中学生1万円(児童手当では支給なし、プラス1万円)となりました。これは、公明党が2009衆院選マニフェストで掲げた児童手当の支給額倍増を、実質的に満たす内容となっています。
所得制限は、支給対象年齢の子どものいる家庭の9割をカバーしていた従来の児童手当の考え方を踏襲し、夫婦と子ども2人の家庭のケースで、額面年収960万円程度ということで決着しました。
なお、民主党政権は昨年度から16歳未満の年少扶養控除を廃止しました。所得制限に該当する世帯は、控除廃止の上に手当もなくなり負担が大きくなるため、今回の合意では、税・財政上の措置を検討し来年度から対処することとしています。
支給額の変更は今年10月分からですが、支給時期が2、6、10月の年3回なので、実際は、来年1月分が支給きれる来年2月から適用されます。また、所得制限については来年6月分から導入され、6~9月分が支給される来年10月からの適用となります。
現在施行されている「つなぎ」法は、昨年度の子ども手当法をそのまま半年間延長したものです。3党協議で民主党は当初、手当の支給額だけ変えて、さらに半年延長する考えでした。しかし、公明党は単純な延長は認めず、来年度から子ども手当法を廃止し、児童手当法を基本とした制度に移行するための特別措置として新法をつくるよう主張。10月分から来年3月分まではそのための新しい法律をつくって運用することになりました。
来年度以降は恒久的な制度として「児童手当法に所要の改正を行うことを基本とする」ことを確認し、今年10月分からの特別措置法の付則にも、その旨を明記しました。
所得制限を導入し、一部を震災復興に充当
一部の家庭では支給額が減額されたり、所得制限のため支給されなくなるなど、実質的に負担増となります。
しかし、今は東日本大震災という未曽有の災害に見舞われ、復興財源も確保しないとなりません。政府の子ども手当の財源は今年度2.9兆円でしたが、今回の見直しで2.2兆~2.3兆円の規模に改め、年間6000億から7000億円もの財源を生み出し、復興に充当できる形になっています。支給対象から外れる1割の所得の高い世帯には、震災復興のためにご協力いただきたいという考えに立っています。
ただし、年少扶養控除が廃止された上に、子どもへの手当にも所得制限が設けられるので、今回の3党合意にある通り、所得制限対象世帯にも何らかの配慮を検討することとしています。
今回の子ども手当の見直しは、3党とも法的には「児童手当法の改正」ということで合意しています。内容的にも児童手当の実質的な拡充であけ、公明党の山口那津男代表は〝進化〟と述べています。
何より必要な安定財源での運用、民主党マニフェストは完全に破綻
3党協議の中で、特に公明党が主張したことは、何よりも安定した財源が確保された中で制度設計をやらなければならないということです。民主党のマニフェストは、とかく財源があやふやなものが多いのです。
従来の児童手当の所要額は年間1兆円で、財源は「国、地方、事業主」の負担で確保されていました。今回、年少扶養控除の廃止によって、国、地方で計1.1兆円の財源が生み出されます。公明党は、従来の児童手当の1兆円にその1.1兆円を加えた2.1兆円程度を新たな手当の財源規模として考えました。その上で、震災という非常時の中で、一定以上の所得の方には復興財源の創出に協力いただくよう主張し、結果として合意内容の通りに収まったということです。
もともと民主党は、1人当たり一律月2万6000円の子ども手当を支給するとうたっていました。しかし、半額の1万3000円ですら、財源確保に汲々としている状況を見れば、満額支給できる見通しなど全くなかったことは明らかです。さらに、民主党のマニフェストでは、費用を「全額、国費で負担する」としていましたが、実際には地方負担が残ったまま。従来の児童手当の財源の形はそのまま残して、その上積み分だけを全額国庫負担にするという二重構造になっていました。これも民主党政権のゴマカシです。
政権交代の前、国民に、いとも簡単に実現できるかのように言っていた民主党のいいかげんさが、はっきり見えたと思います。




扶養控除廃止を廃止して、増税を先行させたのは民主党の愚策です。
> これに対して、年収400~800万円程度の世帯、約250万世帯が「差し引き増税」になる。
ご指摘の内容も十分吟味して、見直しが行われると理解しています。
扶養控除廃止によって増税となるのは、所得制限を超える世帯だけではありません。
所得制限を超える世帯は100万足らず。
これに対して、年収400~800万円程度の世帯、約250万世帯が「差し引き増税」になる。
自公政権時代より悪くなるのに合意したのでは、自民・公明の責任も重大だということになる。
高額所得者のことだけではなく、こちらの方も忘れずに。