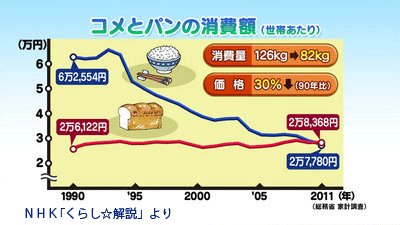これはコメとパンの一世帯あたりの支出が年間でどのくらいあったのか示したグラフです。
まずコメですが、1990年には6万2554円の支出があったのが、年々低下し、去年はついに2万7780円まで下がりました。
一方パンですが、1990年には2万6122円だった支出額は徐々に伸びて2万8368円と、ついにコメの支出額を抜いてしまった。
私たちの食卓は日本型食生活と言われ、ご飯を中心にお味噌汁と副菜で構成されてきたのですが、そういう家庭も少なくなりつつあるということです。
これを見るとパンが伸びたというより、コメが下がったということですね。
ここ20年ほどで食費全体も減っているのですが、パンやめん類は減っていません。コメの一人負けの状況です。
コメの消費額が減った要因を見てみると、まず食べる量が減っている。1世帯あたりのコメの消費量は90年の年間126キログラムから、82キロと3分の2になっています。さらに食べる量が減っているので、価格も下がっている。この間、コメの価格は30%以上下がっています。
消費額というのは食べる量と価格の積算ですから、両方が相まって消費減少に歯止めがかからない状況になっています。
(NHK:くらし☆解説「パンの消費額 コメを逆転」より引用)
今年発表された総務省の家計調査で、昨年の1世帯(2人以上、サラリーマン家庭)当たりのコメ消費額を、パンの消費額が上回ったとの結果が出ました。内訳を見ると、コメが2万7780円だったのに対し、パンが2万8368円とわずかな差ですが、調査開始から初めての結果となっています。
「精米の消費量は確かに下がっているが、スーパーなどで販売されている、おにぎりや弁当など『中食』の消費は増えている。この結果だけでコメがパンに“逆転”されたとは断定できない」と、農林水産省では説明しています。現に、昨年度の1人当たりの中食消費額は、9346円と高い水準にあります。
「めざましごはんキャンペーン」で朝食市場を拡大を
こうした多様化が進む中、農林水産省が新たなコメ消費拡大につながるとして着目しているのが、朝食市場の開拓です。現在、日本人の朝食を抜く割合(朝食欠食率)は約1割にも上ります。仮に1食に掛かる費用を300円として計算すれば、年間約1兆6800億円、約56億食もの新たな市場開拓の余地があるとされています。
このため農林水産省としては、欠食率改善とともに、朝食市場でコメを中心とした日本型食生活が普及できるとし、官民一体で「めざましごはんキャンペーン」を実施しています。レトルトカレーやふりかけなどの関連商品にロゴマークを付けるなど、消費拡大をPRするもので、農林水産省は「コメが日本人の体に合っていることをアピールし、消費者に共感してもらうことが大事だ」と述べています。
「日本食」の文化を次世代へ/世界無形文化遺産への登録めざす
コメを主食とした日本食文化の「ユネスコ無形文化遺産」登録に向けた動きが進んでいます。すでに、(1)フランス美食術(2)地中海料理(3)メキシコの伝統料理などが登録されており、日本食文化も2012年3月に申請され、早ければ来年秋には登録される見込みです。
世界遺産は、有形の文化遺産、自然遺産が対象であるが、このほかに伝統芸能や社会的慣習などの無形文化遺産があります。食に関する文化が登録されたのは画期的なことです。本来、料理は制度の対象外ですが、地中海料理などが登録されたのは、料理そのものではなく人々の生活と密接に関わってきた“社会的慣習”として認識されたためです。
こうした世界的な流れの中、昨年から農林水産省の検討会で登録に向けた議論がスタートしました。寿司などの日本食は、国際会議のレセプションでも提供されるなど人気も高く、登録による輸出拡大効果もありますが、大きな目的は、国民全体で日本の食文化を見直し、次世代に継承していくことにあります。そのため、申請に当たっては格式の高い会席料理などに限定せず、身近な家庭料理や郷土料理まで広げ、日本食文化を「自然を尊重する日本人の気質に基づいた社会的慣習」として位置付けています。
また、食文化を守ろうとする“草の根”の動きも重視されていることから、NPO法人や自治体など約1550団体がこの取り組みに賛同しています。
日本食文化の無形文化遺産登録については、公明党としても、党農林水産部会長代理の横山信一参院議員が、今年6月の参院農林水産委員会で「農水産物輸出のツール(手段)として活用すべき」と述べ、強力に推進しています。横山議員は、「無形文化遺産登録は輸出拡大とともに、国内の農林水産業全体の底上げにもつながる重要な取り組みだ」と強調しています。