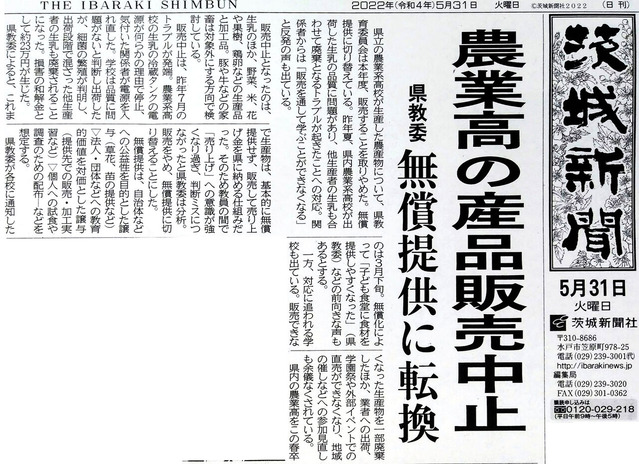情報発信の強化など見直し必要
 2月14日からの記録的な大雪の影響で、農産物関連の被害が関東甲信と東北地方の7県だけで少なくとも約190億円に上ることが18日までに、毎日新聞のとりまとまとめで分かりました。いまだ、茨城県では19日現在で、被害総額を11億2900万円と推計しています。
2月14日からの記録的な大雪の影響で、農産物関連の被害が関東甲信と東北地方の7県だけで少なくとも約190億円に上ることが18日までに、毎日新聞のとりまとまとめで分かりました。いまだ、茨城県では19日現在で、被害総額を11億2900万円と推計しています。
一方、内閣府のまとめによると、大雪のため孤立した集落は19日午前9時現在、山梨県や埼玉県など関東甲信の1都4県の39の市町村で、少なくともおよそ3600人以上に上っています。
懸命の除雪作業が進んでいるとはいえ、日常生活が戻るまでには、まだまだ時間がかかる見込みです。政府や自治体は支援に全力を挙げるべきです。それにしても、政府の対応は遅かったと言わざるを得ません。政府の非常災害対策本部は降り始めから5日後の18になってやと設置されました。初会合は19日昼前、関係省庁の局長などが集まって都内で会合を開き、山梨県庁に設置された国の現地対策本部からテレビ会議システムを通じて報告を受けましという、為体です。
被害が拡大した原因は、普段あまり雪が降らない地域に一度に大量の雪が降ったことにあります。こうした地域では、豪雪地帯と違って大雪の発生は不定期であり、対応に慣れていないのも事実。消雪パイプを備えた道路などのインフラ整備も、費用対効果を考えれば物理的に無理かもしれません。
ただし、地球温暖化の影響などで、集中豪雨や猛暑といった“極端な気象”は増加する傾向にあります。今回の教訓を踏まえ、大雪への「想定外」に備えた取り組みが欠かせません。
まず、「公助」を担う行政は、情報発信を強化していく必要があります。
今回の大雪について気象庁は特別警報を発表しませんでした。「降雪が丸1日以上続くと予想される」との基準を満たさなかったためです。気象予測の難しさはあるかもしれませんが、改善はできないのか。運用の見直しを検討すべきです。例えば、雪国の積雪が予想される場合と、首都圏や通常あまり雪が積もらない地域とでは、特別警報の基準が違ってしかるべきです。
自治体が除雪作業を委託する建設業者の減少も痛手でした。近年の不況や公共事業の削減で、維持費のかさむ除雪用車両を手放した業者も少なくありません。中長期的に建設業界を支援していくことが不可欠になります。ホイールドーザーなどの大型の重機も、建設会社は保有しておらず、必要なときにレンタルしています。これでは緊急時に対応できませんでした。
雪の重みで公共施設や駅の屋根などが崩落するケースも目立ちました。多くの人が集まっていれば大惨事になりかねません。原因の究明を徹底して進めると同時に、早めの除雪など、再発防止策を検討するべきです。
 一方、孤立しやすい中山間地の集落では、自力で雪かきができない高齢者が多くなっています。除雪作業中の転落事故なども起きています。豪雪地帯では除雪ボランティアの受け入れや、安全に配慮した地域一斉の雪下ろしなどの取り組み事例がありますが、そもそも普段はこうした雪害の少ない場所にはどのような仕組みを作るか。人々が助け合う「共助」の仕組み作りを研究する必要があります。
一方、孤立しやすい中山間地の集落では、自力で雪かきができない高齢者が多くなっています。除雪作業中の転落事故なども起きています。豪雪地帯では除雪ボランティアの受け入れや、安全に配慮した地域一斉の雪下ろしなどの取り組み事例がありますが、そもそも普段はこうした雪害の少ない場所にはどのような仕組みを作るか。人々が助け合う「共助」の仕組み作りを研究する必要があります。
今回の大雪では、立ち往生した車が大渋滞を引き起こし、除雪車が入れない道路もありました。国道の通行規制については、規制が後手に回り、通行止めにしたのは大渋滞の発生後となってしまいました。雪がやんだ後も車両の移動に時間を要し、復旧を遅らせ大きな要因となりました。
太田国土交通相は、通行規制のあり方を見直し、今後は早い段階で通行止めにして、集中的に除雪を行う方針を明らかにしました。当然の措置です。
立ち往生した車両を所有者の同意なしに道路上から移動させることも検討して良いのではないでしょうか。
チェーンやスタッドレスタイヤを使わず、普通のタイヤで走行していた車の事故が目立ちました。高速道路や主要国道では、早期の通行規制を行い、ノーマルタイヤでの通行を禁止スべきです。
さらに、自治体の自衛隊要請のタイミングも課題が残りました。今回の雪害では、山梨や埼玉、群馬、長野、静岡、東京、福島、宮城の8都県が自衛隊に災害派遣を要請しましたが、埼玉や静岡県では、自衛隊の出動がなくても自治体で対応できると、一時、要請を躊躇した事例があったようです。予め、都道府県の防災計画の見直しも含めて再検証すべきです。
自治体の情報の出し方も問題があったと思います。孤立状態がtwitterやfecebookでアップされ始めると、その情報は確証がないまま拡大し続けました。必要なのは、自治体や防災関係者が的確に場をつかむことです。そして、自治体などは掴んだ情報を確認して、何らかの危機的状況発生していることを認知したならば、ネットなどでその情報をすみやかに公表すべきです。現に孤立状態に陥っている人は、少なくても自分たちの状況が把握されていることに安堵するはずです。第三者もその情報を持って行動を起こせる場合もあります。
今回の雪害では、対応すべき被災者の情報が最初の3日間程度まったく報道もされず、自治体のホームページやSNSでも発信されませんでした。ゆえに不安が増大してしまったのだと考えます。防災情報の出し方の見直しも必要です。
最後に、大雪の予報が出たら外出を避ける。出かける際には万全の備えを怠らない。孤立した場合を想定して自宅に食料を備蓄するなど、一人一人の心がけ「自助」がもっとも大切であることを強調したいと思います。