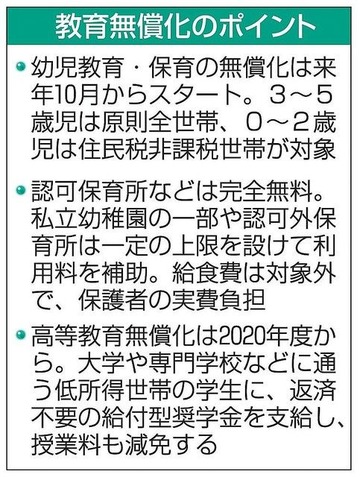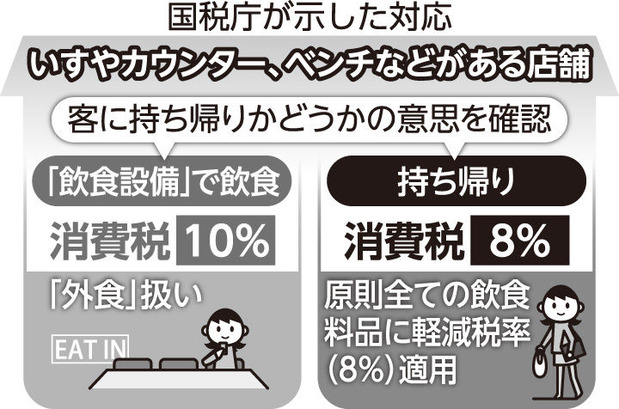6月16日、井手よしひろ県議は、定例の県議会報告をJR大みか駅前で行いました。地域創生の取組と国会における平和安全法制の問題について、報告しました。動画は、平和安全法に係わる部分です。
今回の平和安全法制関連法案は、憲法9条と13条の精神に合致しており、日本の国民と領土を守るためには必要であると強調しました。
平和安全法制の関連法は、憲法の制約があるので、いわゆる日本の武力行使は自国の防衛ためにのみ使えるという限界を画すと同時に、もっぱら他国の防衛のために武力を使うことはやらない、ということをはっきりと決めたものです。
日本の憲法の考え方、政府の考え方は、9条1項で戦争を放棄して、2項で陸海空の戦力を持たないということを規定しています。一見、非武装を規定しているように読めます。 しかし、憲法の前文では平和のうちに生存する権利を示し、また13条では、国民の人権に対して政府は国政上最大の尊重を要する、と規定しています。
国民の人権を最も奪う行為が日本に対する武力の攻撃ですから、これを排除するための力は必要です。しかし9条がありますから、それは最小限のものでなければなりません。こういう考え方で、必要最小限度の自衛力を持つことは許されています。
個別的自衛権とか集団的自衛権という概念は、国際法で言われる概念ですが、その集団的自衛権には、日本の国民の人権が台無しになること以外にも、他国をもっぱら守るために武力を使う概念も含まれております。そうした国際法でいう集団的自衛権は日本の憲法は認められないことは明白です。 他国に対する攻撃がきっかけであったとしても、それが日本に対する攻撃と同様に、日本の国民に深刻・重大な被害をもたらすような攻撃であれば、日本は武力行使で反撃できます。こうした極めて限定的な意味での国際法上の集団的自衛権は認められる、という考え方が今回の平和安全法制の根底に流れています。
日本の自衛権の行使が許されるのは、他国に加えられた攻撃か自国に加えられた攻撃か、ではなく、その攻撃が日本の国民の権利を根底から覆すことが明白なのかどうかという、客観的な考え方で一貫して捉えられているのが日本政府の考え方なのです。
このような考え方は論理的に一貫しているものであり、また、これからも変わらないという、という意味で法的にも安定していると思います。
これ以上の、他国に対する武力攻撃、他国を防衛する武力攻撃を許すような、いわゆるフルスペックの集団的自衛権を認めるようなことは今の憲法下ではできない、それをやるには憲法改正が必要となります。