総務省は、12月26日、「地方公共団体における福利厚生事業の状況について」の調査結果を取りまとめ、公表しました。
この調査は、平成17年の参議院決算委員会で、公明党の山下栄一参議院議員が取り上げた質問がキッカケになり行われたものです。その結果、福利厚生の名のもとに毎年度、多くの自治体で公費をつぎ込んだ職員互助会等において、職員個人への給付が行われていることが明らかになりました。
12月に公表されたフォローアップ調査によると、全地方自治体における16年度決算と19年度予算とを比較すると、互助会等に対する公費の支出額は831億円から309億円と532億円もの減額となっています。
しかし、自治体によっては公費支出を全廃したところと、相変わらず首をかしげるような名目の個人給付を行い、しかも公費が出されているケースなど、見直しが不充分な自治体が多々あります。こうした実態は、給与本体を上げられない世間の目を気にして、労使交渉における職員組合と理事社側(自治体の執行部)の妥協の副産物として生まれたもので、市民感情からみて少なくとも公費投入は廃止すべきものと思われます。
互助会への公費投入を全廃した自治体は21道府県です(宮城県、千葉県、島根県、岩手県、京都府、鳥取県、香川 県、高知県、北海道、長野県、和歌山県、徳島県、福岡県、青森県、鹿児島県、秋田県、山形県、福島県、新潟県、広島県、愛媛県)。政令市では大阪市が全廃しました。市町村では339市区町村が廃止しています。
不自然な形の個人給付としては、「退会給付」、「医療費補助」、「入学祝い金」、「レクレーション補助」、「入院・傷病見舞金」などが上げられます。「退会給付」などは、退会するとき=退職するときに支給される給付金で、裏の退職金といっても過言ではありません。
茨城県では、18年度に制度改正を行い、互助会への公費の投入を減額してきました。平成16年度決算で4億5700万円あった公費からの支出金は、17年度4億5000万円、18年度2億6500万円と減額されていますが、19年度は反対に2億6900万円と増額されました。茨城県の場合、人間ドックや脳ドックなどの検診関連事業への補助金が大きな割合を占めています。
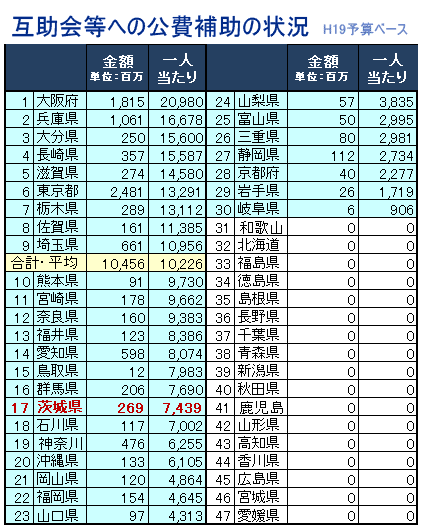
 参考:「地方公共団体における福利厚生事業の状況について」
参考:「地方公共団体における福利厚生事業の状況について」



