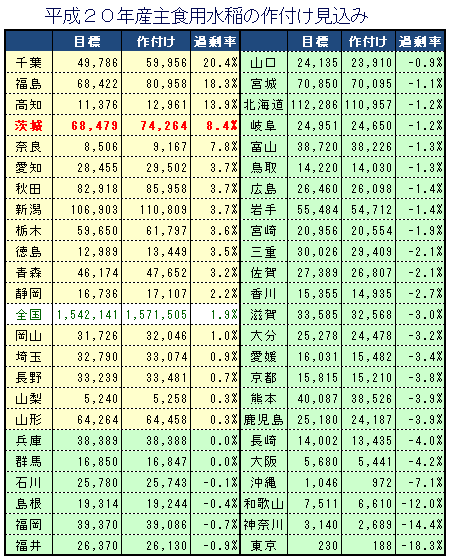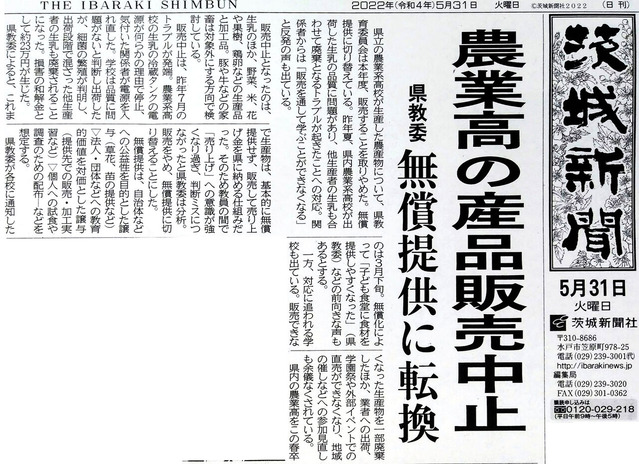7月4日に公表された農林水産省の「米関連政策の実施状況について」で、2008年産米の作付け状況の中間取りまとめ結果が判明しました。それによると、主食用の米の生産目標の154万ヘクタールにたいして、作付け見込み面積は157万ヘクタールとなり、2万9000ヘクタールの作付け過剰となることが分かりました。
7月4日に公表された農林水産省の「米関連政策の実施状況について」で、2008年産米の作付け状況の中間取りまとめ結果が判明しました。それによると、主食用の米の生産目標の154万ヘクタールにたいして、作付け見込み面積は157万ヘクタールとなり、2万9000ヘクタールの作付け過剰となることが分かりました。
茨城県は、目標値68,479ヘクタールに対して、作付け見込みは74,264ヘクタールに達し、5785ヘクタールが過剰作付けとなる見込みです。これは、千葉、福島、高知についで目標達成率でワースト4となっています。
今年産の対策は、過剰生産で価格が低迷した昨年の生産結果を踏まえて決定されています。政府は緊急対策として、一定期間生産調整することを前提に拡大分や新規取り組み分に対し、一時金を支払うことにしました。単価は07年産の生産調整実施者に10アール5万円、未達成者に3万円とし、生産調整に協力的な農家に加算措置を執りました。
今年度は、既存の技術や水田を活かして生産に取り組める飼料米やホールクロップサイレージ(稲発酵粗飼料)による生産調整に力を入れています。飼料米はJA全農が一元集荷して、飼料会社の販売するルートづくりも行われました。産地作り交付金なども加えて、主食用米水準の所得が得られる仕組みも構築されています。
輸入飼料価格が高騰する中で、飼料用米をはじめとした非主食用米の必要性が強調されています。既に作付けが終わった主食用米を飼料用米などの非主食用米に転用することも出来ます。生産調整を達成して、コメの価格の回復に取り組むことが重要です。