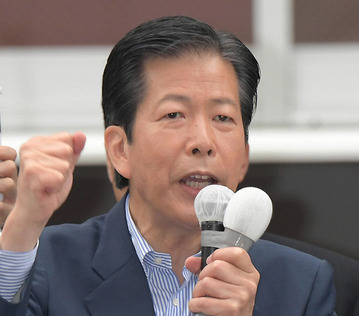低い生産性を温存し“バラマキ”、農家の不安に取り入った民主党マニフェスト
(民主党マニフェスト2009より)
○農畜産物の販売価格と生産費の差額を基本とする「戸別所得補償制度」を販売農家に実施する。
○所得補償制度では規模、品質、環境保全、主食用米からの転作等に応じた加算を行う。
○畜産・酪農業、漁業に対しても、農業の仕組みを基本として、所得補償制度を導入する。
○間伐等の森林整備を実施するために必要な費用を森林所有者に交付する「森林管理・環境保全直接支払制度」を導入する。
 民主党がそのマニフェストに掲げる「戸別所得補償制度」は、すべての農家の所得を補償するという“甘い言葉”で支持を集めたいようだが、逆に「これでは日本の農業がつぶれてしまう」と危ぐする声が次第に高まっています。
民主党がそのマニフェストに掲げる「戸別所得補償制度」は、すべての農家の所得を補償するという“甘い言葉”で支持を集めたいようだが、逆に「これでは日本の農業がつぶれてしまう」と危ぐする声が次第に高まっています。
民主党のいう「戸別所得補償制度」は、すべての販売農家を対象に生産費と市場価格の差額が生じた場合、その差額分を各農家に直接支払うというものです。例えば、コメの市場価格が60キログラム5000円まで下がっても、1万円を補償して農家の収入を1万5000円にするということです。必要な予算は1兆円程度としています。
すでに民主党は、この制度を法案化し、国会に提出しましたが、制度の骨格について何一つ具体的に説明できず、廃案になっています。
中でも大きな問題になったのは、単に農家にお金をばらまくというだけで、日本農業の将来像がまったく見えない、ということです。農家の高齢化や後継者難が深刻化し、耕し手のいない耕作放棄地は約39万ヘクタールに達しています。高齢化・人口減少による農村集落の衰退も始まっています。
こうした中で、農地をどのように保全・集積し、担い手をどのように確保・育成していくのか。民主党の農業政策は根本的な問題に何も答えていません。現状を固定化してしまうだけです。
減反は継続し選択制に!? 日本は共産主義農業国に!!
民主党は従来からコメの生産調整を廃止するとうたっていましたが、今回のマニフェストからその公約が消えました。現行のコメの生産調整(減反)を抜本的に見直し、参加するかどうかの判断を農家に任せる「選択制」へカジを切ったのです。今こと自体、今までの政策を簡単に変更する、政策のブレとして看過できるものではありません。
政府が農家に農産品の生産費と販売価格の差額を穴埋めする「戸別所得補償制度」と組み合わせ、農家ごとに設けるコメの生産量の上限に従った農家に限って所得補償の対象とする考えです。すなわち、減退の応じない農家は所得補償の対象にならず、今まで以上に統制経済の様相が強くなってきました。
コメ以外にも麦・大豆、牛肉、乳製品など多岐にわたる農産物の生産数量を、すべて国がコントロールすることはできるのでしょうか?仮にこうした農業統制が実現すると、農家は作りたいものを自由に作ることができなくなり、地域農業の主体性が大きく損なわれてしまことになります。
「1兆円」の財源、その積算根拠も不明。農業土木費を大幅に削って、耕作放棄地問題はどのように解決するのか
民主党は、戸別所得補償に必要な財源を「約1兆円」としていますが、その積算根拠をいまだに説明できません。そもそも、農産物の販売価格が大きく下落すると財源も膨らむ仕組みのため、「果たして1兆円で済むのか」という疑問には、全く答えていません
仮に予算を1兆円としても、そのお金をどこから持ってくるのか、財源があいまいです。以前、衆院本会議の代表質問で小沢一郎前代表は、財源について「個別農産物補助金4000億円、農業土木費7000億円などを見直す」と述べましたが、農業土木費を大幅に削減すると、農業に不可欠な用水路などの維持管理が難しくなります。大きな問題となっている耕作放棄地の再生にはどこから予算を持ってくるのでしょうか?
世界的な貿易自由化の流れと齟齬
自由貿易協定(FTA)や世界貿易機関(WTO)による農産物市場の自由化という潮流の中で、将来にわたり、日本だけが高い関税で農産物市場の保護を続けることができないのは明らかです。しかも、民主党案はWTOの協定違反になる可能性が強く、補助金を削減せざるを得ない状況が必ず来るという指摘があります。WTOは、政府の政策に基づく内外価格差支援、直接支払いなどの「最も貿易歪曲的な国内助成」を「黄の政策」として削減対象としています。民主案は、まさにこの「黄の政策」に該当するものです。
仮に該当しないとしても、WTOは余剰生産を行う農家への補助金を禁止している。安価な農産物が輸入され、国内需要が満たされても、所得補償を受けるために余剰生産を続ける農家が出てくる可能性も指摘されています。それはWTOの協定違反となり、結局、補助金を打ち切られる農家が出てくることになりまする。
アメリカとのFTA締結をマニフェストに掲げ、農産物の関税自由化を主張する大いなる矛盾
(民主党マニフェスト2009より)
○米国との間で自由貿易協定(FTA)を締結し、貿易・投資の自由化を進める。
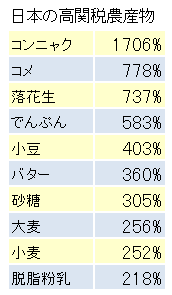 さらに、民主党マニフェストには、アメリカとの自由貿易協定(FTA)を締結し、貿易・投資の自由化を進める。という内容が明記されました。何という矛盾した政策でしょうか。日本とアメリカとの関税問題の多くは、農産物の問題です。
さらに、民主党マニフェストには、アメリカとの自由貿易協定(FTA)を締結し、貿易・投資の自由化を進める。という内容が明記されました。何という矛盾した政策でしょうか。日本とアメリカとの関税問題の多くは、農産物の問題です。現在、日本が高い関税を掛けて国内生産農家を守っている品目に、右のようなものがあります。民主党は食料自給率を高めると言っておきながら、戸別補償を実施し農家の収入を守ると言っていながら、農産物の関税をゼロにしてアメリカから安い農産物が一挙に流入することを認めているのです。これ以上矛盾した政策はありません。
この点、日本農業新聞の7月27日付社説と共産党の機関紙「しんぶん赤旗」の論調は非常に分かりやすく、民主党の暴論を見事に斬っています。やや長い引用になりますが、全文そのまま掲載させていただきます。
民主党政権公約/許されない日米FTA
日本農業新聞(2009/7/29)
民主党は衆院選のマニフェスト(政権公約)で、日米間の自由貿易協定(FTA)締結を掲げた。FTAは相互の関税を撤廃するのが原則で、関税率の引き下げを交渉する世界貿易機関(WTO)の交渉と大きく異なる。公約通りに協定を締結すれば、日本農業への打撃は極めて大きい。農政を重視し、主要穀物などの完全自給を目指すとする政策目的と矛盾するちぐはぐさを見せている。同党は詳しく説明する必要がある。
2008年の貿易をみると、日本の総輸入額は79兆円弱で、うち米国は8兆円である。農産物の輸入額は5兆9821億円で、最大の輸入先が米国で1兆9435億円となっている。品目ごとにみると豚肉は輸入額の41%、小麦は61%、牛肉は14%、米は62%を米国産が占めている。
これらの品目は日本の地域農業と経済にとって重要だからこそ一定の関税で国内産を守っている。農水省はすべての関税を撤廃すれば、内外価格差が大きい米麦や牛肉・豚肉などは市場を失って、農業生産額は3兆6000億円(4割)減り、食料自給率は現在の40%から12%まで下がると試算している。巨大な農産物輸出国である米国1カ国だけでもこれらの品目の影響は極めて大きい。石破茂農相は、「米麦や畜産物が壊滅的な被害を受ける」としている。食料供給を輸入に頼らざるを得ない日本は、輸入先の多元化が求められている。米国とのFTA締結は米国依存を強め、食料安保上の危険さえある。
同党が農業政策の目玉として掲げる戸別所得補償制度は、販売農家を対象にし、対象品目の販売価格が生産費を下回った場合に補てんする。関税撤廃によって国内農畜産物の販売価格が下がれば、現在のマニフェストで想定するより多くの財源が必要になる。どう対応するのかその説明もしてもらいたい。
両国のFTAは国際経済の観点からも問題がある。多国間貿易体制を形だけにしかねない懸念だ。WTOには輸入品を国産品と同様に扱う「内外無差別」とともに、すべての加盟国に同等の貿易条件を与える「最恵国待遇」という2つの基本原則がある。日米両国の国内総生産(GDP)を合わせると世界の3割を占める。この2カ国による排他的な経済統合は世界の貿易を大きくゆがめる懸念がある。発展途上国を中心に批判を浴びよう。FTAが無秩序に拡大する恐れもある。
同党は小沢一郎代表時代、戸別所得補償制度の創設とともに農産物輸入の「全面自由化」を打ち出し、その後「自由化促進」に後退した経緯がある。マニフェストが同党の本音であれば説明する必要がある。自民党は民主党との討論会で配布した資料で「米をはじめ重要品目は自由化しない」としており外交交渉の農産物貿易の取り扱い方針が総選挙の大きな争点になった。
民主党マニフェスト“日米FTA締結”明記
農業壊滅 批判に大あわて
しんぶん赤旗(2009/7/31)
民主党が27日発表したマニフェスト(政権公約)に「米国との間で自由貿易協定(FTA)を締結」すると明記したことが、農業関係者の反発を呼び、各党から批判を受けるなど、大きな波紋を広げています。批判の強さに驚いた民主党は、対応に追われています。
日本農業新聞は28、29両日、民主党マニフェストを大々的に報じ、「許されない日米FTA」と題した29日付の論説は、「米国とのFTA締結は米国依存を強め、食料安保上の危険さえある」と警告しました。
日本共産党の志位和夫委員長は28日、記者団の質問に答え、「米国とのFTAは日本農業を壊滅させる。絶対に反対だ。そんな道に踏み込んだら食料自給率がかぎりなくゼロに近づくことになりかねない」と批判しました。
農林水産省の試算によると、経済連携協定(EPA)やFTAで関税などの国境措置が撤廃された場合、日本の農業総生産額の42%に相当する3兆5959億円が失われ、食料自給率が12%に低下します。米国とのFTAが、日本の農業に大打撃を与えることは必至です。
批判に対し、民主党の29日の声明は、「日本の農林漁業・農山村を犠牲にする協定締結はありえない」と釈明しました。菅直人代表代行も同日の記者会見で、「米などの主要品目の関税をこれ以上、下げる考えはない」などと述べました。
しかし、世界最大の農産物輸出国であり、金額でみて日本の農産物輸入の32.5%(08年)までを占める米国とのFTAが、農産物抜きで成り立つはずがありません。実際、日本経団連アメリカ委員会と在日米国商工会議所(ACCJ)が21日発表した共同声明も、「FTAプラス」の協定として日米EPAを求め、実施すべき非関税措置の中に農業分野を含めています。
民主党はこれまで、「あらゆる分野で自由化を推進する」(「政権政策の基本方針」2006年12月)という立場で、“自由化”を前提に、「米がたとえ一俵5000円になったとしても、中国からどんなに安い野菜や果物が入ってきても」(07年の政策ビラ)、「所得補償制度」を導入すればよいとしていました。