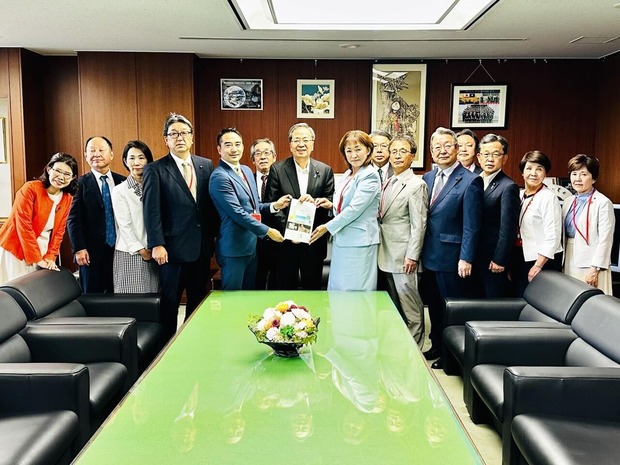1月23日、井手よしひろ県議はPHP地域経営塾主催のセミナーに参加しました。このセミナーのテーマは「学校から始まる『施設整備から機能確保へ』のパラダイムシフト」。公共施設の中でも、小中高等学校は多くの割合を占めています。単に教育施設を確保するという時代から、その機能を見据えて効率的で有効な活用を目指す時代になってきました。
1月23日、井手よしひろ県議はPHP地域経営塾主催のセミナーに参加しました。このセミナーのテーマは「学校から始まる『施設整備から機能確保へ』のパラダイムシフト」。公共施設の中でも、小中高等学校は多くの割合を占めています。単に教育施設を確保するという時代から、その機能を見据えて効率的で有効な活用を目指す時代になってきました。
首都大学東京大学院の上野淳教授(建築領域)は、東日本大震災の陸前高田市立第一中学校の事例などを通し、避難所となった学校の地域社会に果たした役割を具体的に講演しました。
陸前高田一中は、高台にあったため津波被害を免れ、当日夜には1000人以上の市民が体育館に避難しました。それから丸5ヶ月、8月12日に避難した最後の数家族が体育館を離れ、避難所は解消されました。
上野教授は、高田一中が被災者の命を守り、通常の生活を取り戻すまでに大きな役割を果たしたことを強調した上で、その過酷な状況を説明しました。
 子どもたちと避難者を守るために、校長は学校に48日間泊まり込んだ。当初、体育館には石油ストーブ2台しかなかった。子どもたちは、教室のカーテンをはずして2~3人で体に巻いて寒さを防いだ。水の供給が途絶し、給水タンクに残った水を、一人一日茶碗一杯分け合った。グランドに溝を掘り、板を渡し、周囲をベニヤ板で囲う仮設トイレを設置した。食糧は2日目にパンが1個だけ配給された、炊き出しは3日目から、発電機が届いたのも3日目だった。など、上野教授は、17年前の阪神・淡路大震災の教訓が全く活かされなかったことに、無念の心情を吐露していました。
子どもたちと避難者を守るために、校長は学校に48日間泊まり込んだ。当初、体育館には石油ストーブ2台しかなかった。子どもたちは、教室のカーテンをはずして2~3人で体に巻いて寒さを防いだ。水の供給が途絶し、給水タンクに残った水を、一人一日茶碗一杯分け合った。グランドに溝を掘り、板を渡し、周囲をベニヤ板で囲う仮設トイレを設置した。食糧は2日目にパンが1個だけ配給された、炊き出しは3日目から、発電機が届いたのも3日目だった。など、上野教授は、17年前の阪神・淡路大震災の教訓が全く活かされなかったことに、無念の心情を吐露していました。
その上で、コミュニケーシュン・シェルターとしての学校施設の重要性を強調。マンホールトイレや自家発電施設の整備、水や食糧の確保、情報が途絶することへの対応の重要性を指摘しました。
さらに、後半のパネルディスカッションでは、学校施設に他のコミュニティ施設との共存を図ることの重要性を訴えました。生涯学習、図書館、スポーツ施設、子育てや高齢者施設など、多機能化することで、住民の利便性が高まり、防災の拠点としても機能すると語りました。
また、新規の建設に当たっては、耐震性能が高い、一般的に柱と柱のスパンが長い、天井高が高いなど、他の施設に比べての特長があり、リモデルの可能性を十分に活かした設計にすべきと提案。その歳に、教室ごとの耐震壁は構造的に転用が難しいので、配慮が必要とも語りました。
学校は、地域住民の大事な宝物です。その運営や整備については、今まで以上の柔軟な発想が不可欠であることを、強く認識させられたセミナーになりました。
(写真上:セミナーで講演する上野淳教授、写真下:陸前高田市立第一中学校)