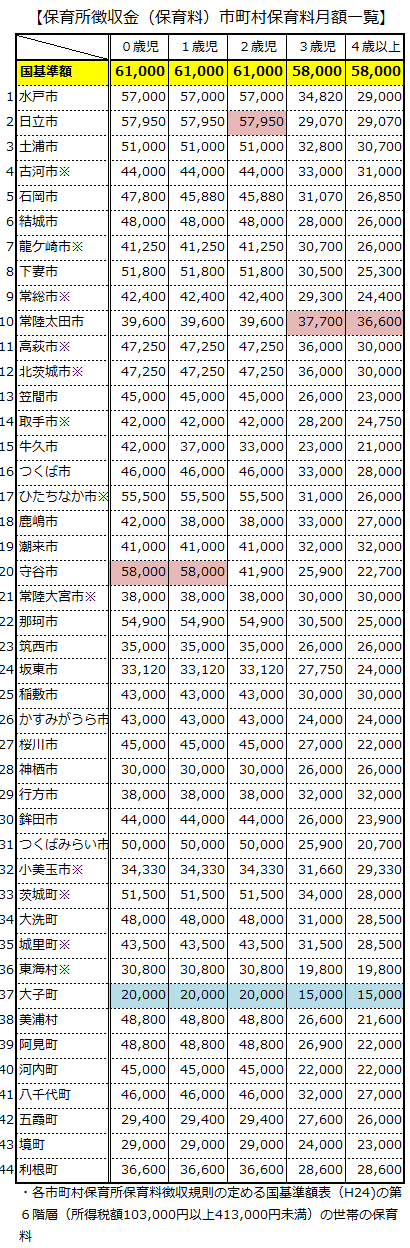県内市町村の保育料に3倍近い格差
 昨年末の自公政権の発足にあたり、公明党と自民党は、12月25日、8項目にわたる連立政権合意を交わしました。その中でも、「幼児教育無償化を財源を確保しながら進める」との一文は、非常に重みがあるものです。
昨年末の自公政権の発足にあたり、公明党と自民党は、12月25日、8項目にわたる連立政権合意を交わしました。その中でも、「幼児教育無償化を財源を確保しながら進める」との一文は、非常に重みがあるものです。
2012年の日本の「人口減少幅」は過去最大の21万2000人になり、6年連続しての自然減となっています。昨年は出生数103万3000人に対して、死亡数は124万5000人で、人口の減少幅は前年より、さらに1万人も増加しています。今後も人口減少と少子高齢化は、さらに加速度を増してきます。厚労省によると、47年後の2060年には日本の人口が8674万人にまで減少し、人口数でみると関東地方の1都6県(人口約4200万人)が消失するに等しい深刻な“人口減少社会”が到来しようとしています。
こうした中、わが国の社会保障に対する信頼が揺らげば、現役世代は将来の不安に備えて貯蓄に走り、消費活動が抑制され、まさに経済は負のスパイラルに陥ります。
日本が世界に誇る「国民皆保険」や「皆年金」といった社会制度を守り、維持するためには何よりも“支え手”である若い世代、働
きざかりの世代を拡大することが重要です。子どもを安心して産み育てられる社会環境の構築が急務です。
そのために必要な施策が、子育ての負担軽減であり、幼児教育の無償化の取組みです。諸外国でもイギリスやフランス、韓国などのように無償化を進めている国が増えています。
こうした幼児教育は、現在市町村の事業として展開されており、その負担の重さや格差拡大が問題となっています。
その一例として、茨城県議会公明党は、県内市町村の保育料調査を実施しました。
保育料は所得に応じて異なるため、国基準の第6階層(所得税額103,000円以上413,000円未満)の保育料を比較しました。3歳児の場合、最も高い常陸太田市と最も安い大子町との差は2.5倍となっています。(常陸太田市37,700円、大子町15,000円、なお日立市は29,070円)。0歳児の場合は、その差はさらに広がり、守谷市と大子町の差は2.9倍となっています。(守谷市58,000円、大子町20,000円、日立市は57,950円)
保育料は市町村の財政力と子育て支援への取組みの強弱に左右されています。日立市と境を接している東海村を比べてみるとその差は顕著です。0~3歳児が日立市は57,950円なのに対して東海村は30,800円。3歳児以上が日立市34,820円、東海村は19,800円と倍近い差がみられます。
本来子育て支援策は、国策として進められるべきです。日本の百年後の未来を見すえて、幼児教育の無償化は是非とも実現すべき課題です。