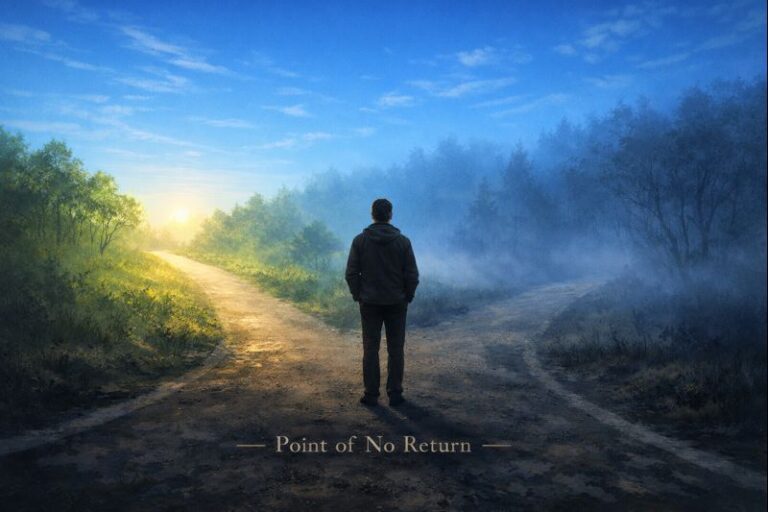9月26日、映画「ある町の高い煙突」で知られる松村克弥監督が千葉県一宮町を訪れ、馬淵昌也町長と面会しました。松村監督は、最新作「ぼくは風船爆弾」を一宮町で上映する提案を行いました。
この作品は、戦後80年という節目に合わせて制作された、松村監督の「戦争・平和・命」をテーマとするシリーズの一つです。前作「祈り」が戦後75年記念事業として全国で上映されたことを思えば、今回の新作もまた、歴史を見つめ直すための大切な機会になることでしょう。
一宮町は、太平洋戦争末期、日本軍がアメリカ本土に向けて放った「風船爆弾」の打ち上げ地のひとつとして知られています。茨城県北茨城市や福島県いわき市と並び、この地にも戦争の記憶が深く刻まれています。松村監督は、こうした地域の歴史を掘り起こし、未来の世代に平和の尊さを伝える場にしたいと語りました。

馬淵町長は、風船爆弾の歴史をより多くの人に知ってもらうこと、そして平和への強いメッセージを発信することはとても重要だと述べました。そのうえで、教育委員会と連携しながら丁寧に検討したいとの考えを示しました。
特に印象的だったのは、町長の率直な歴史観です。馬淵町長は、風船爆弾を「狂気の兵器」と呼び、「嫌がらせ以外の何ものでもない」と厳しく批判しました。人命を奪いながら何の成果も得られなかったその行為は「無意味」であり、旧日本軍の発想には「根っこから共感できない」と語りました。その言葉には、歴史から学ぶべきだという強い意志が込められていました。
この対話を通して、戦争の記憶が少しずつ風化していく今だからこそ、私たちはもう一度「戦争とは何だったのか」「平和とは何か」を考える必要があると、改めて感じました。一宮町での上映が実現し、多くの方がこの映画を通して歴史と平和について思いを巡らせるきっかけになることを願っています。
一宮町の海辺を歩くと、潮の香りの向こうに、かつて“太平洋の向こう側”へ向けて放たれた風船爆弾の記憶が、静かに横たわっていることに気づきます。九十九里浜の南端に位置する一宮町は、太平洋戦争末期、日本陸軍が実施した「ふ号」作戦の発射基地(放球基地)のひとつでした。
この作戦の基地は日本にわずか三か所――千葉県一宮町、茨城県北茨城市大津、福島県いわき市勿来――に設けられ、いずれも太平洋に面した海岸砂地でした。発射は1944(昭和19)年11月に始まり、翌年3月ごろまで続きます。合計でおよそ9,000~9,300個の風船爆弾が放たれ、その一部、300個前後が実際にアメリカ大陸に到達したとされます。
風船爆弾(当時は「気球爆弾」と呼ばれました)は、和紙をこんにゃく糊で貼り合わせた直径約10メートルの気球に水素ガスを充填し、焼夷弾や爆弾を吊り下げて、偏西風に乗せて太平洋を横断させるという、前例のない兵器でした。作戦は川崎の陸軍登戸研究所で開発され、運用は三つの大隊に分かれて行われました。第1大隊(本部・大津)、第2大隊(一宮)、第3大隊(勿来)の編成で、各地の海岸に複数の発射点を設け、天候の良い日には1日200発規模での放球を想定していたといいます。

一宮の発射基地は、現在では目に見える構造物がほとんど残っていませんが、町教育委員会が設置した解説板と小さな石碑が往時を伝えています。看板のある地点(一宮町一宮6-35付近)から道を挟んだ海側一帯が発射区域で、上総一ノ宮駅からは資材搬入のための引込線が敷設されていました。戦後、基地は破壊されましたが、コンクリート土台の破片や球皮の欠片が住民の手で大切に保管され、後に教育委員会へ寄贈されています。
町内には直径10メートル超の円形コンクリート製の発射台が12か所あったとされ、発射時には風の影響を避けるため、高さ20メートルほどの木製の壁が設けられていたという研究もあります。
もちろん、この作戦がもたらした米国側の被害は小さくありません。アメリカ西海岸では山火事が発生し、1945年5月にはオレゴン州ブライ近郊で不発弾に触れた民間人6人が亡くなる痛ましい事故も起きました。日本国内でも当時は軍事機密として詳細が伏せられていましたが、戦後に史料や証言が次々と公開され、発射の実態と成果、そして兵器としての性格が徐々に明らかになってきました。

現在の一宮町では、町史編さん事業などを通じて風船爆弾の歴史を冷静に伝える取り組みが進められています。戦後80年に当たる今年は、中央公民館2階ロビーで企画展示「戦後80年 一宮町の“戦争”」(7月25日~12月22日)が開催されています。さらに11月22日には、風船爆弾研究の第一人者・明治大学の山田朗教授を迎えて「風船爆弾とは何だったのか~その狙いと作戦の実態」と題した講演会も開かれる予定です。(詳細は一宮町教育委員会まで。平日:0475-42-1416)
今ではサーフィンの聖地として国内外から多くの人が訪れるこの砂浜が、かつては戦争の狂気に染まった作戦の舞台であったことを、私たちは忘れずに語り継ぎたいと思います。