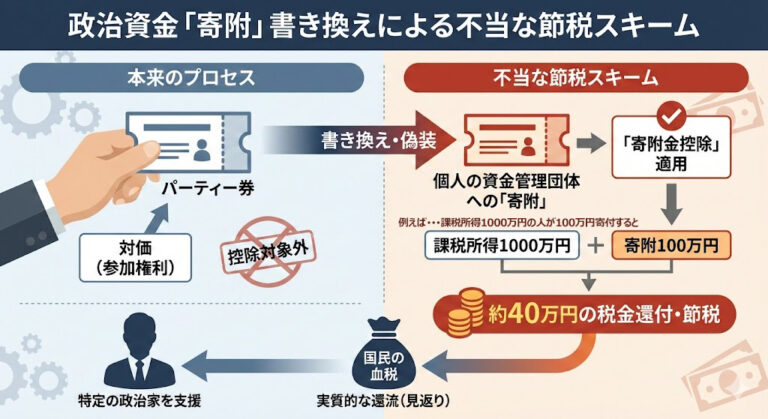高市総理がトランプ前大統領をノーベル平和賞に推薦する意向を示したという報道が波紋を呼んでいます。
この件について、「故・安倍総理も2019年に推薦状を出していたのだから、高市総理だけが批判されるのはおかしいのではないか」という声も寄せられました。
たしかに、同じ“推薦”という行為のように見えますが、当時の安倍総理のケースと今回の高市総理のケースとでは、背景も手続きの段階も大きく異なります。
今回の発端は、トランプ氏の訪日に合わせた日米首脳会談の際に、高市総理が「トランプ氏をノーベル平和賞に推薦する意向を伝えた」とアメリカ側が発表したことでした。
つまり、まだ推薦状を正式に提出した段階ではなく、これから手続きを進めるという「意向表明」の段階にあります。
一方、2019年の安倍総理の場合は、トランプ氏自身が「安倍首相から推薦状のコピーを受け取った」と公言したことから始まりました。
ノーベル平和賞の推薦には50年間の守秘義務があるため、安倍総理は国会で問われても肯定も否定もできず、説明に制約がある中で批判だけが先行しました。
しかし今回の高市総理は、その“守秘の壁”に入る前の段階で動いているのです。
だからこそ、当時の安倍総理以上に、「どのような判断で、どのように進めようとしているのか」を明確に説明する責任があります。
推薦の判断が誰によるものなのか、政府内で正式な手続きを踏むのか(閣議決定の有無)、そして日米関係の中でどのような意義を持たせたいのか。
これらは守秘義務の対象外であり、説明できるはずの内容です。

外交は密室の中だけで完結するものではありません。
民主主義国家においては、国民の理解と信頼を前提に進められるべきです。
今回の推薦意向を「日米同盟の良好さを示すシンボリックな動き」と評価する声もありますが、であるならばこそ、隠す必要も後ろめたさもなく、その意義を堂々と語るべきです。
トランプ大統領は訪日直後に「核実験再開の検討」を公言し、実際にその準備を指示しました。
人類の安全と恒久平和に背を向けるような姿勢を見せた指導者に、ノーベル平和賞の資格があるとは到底思えません。
核抑止の名のもとに核実験を再び容認することは、世界の平和に逆行する行為であり、日本の立場から見ても看過できないものです。
日本の外交は、常に国民とともに歩むべきものです。
高市総理の今回の一件は、外交のあり方と説明責任をあらためて問い直す機会であるとともに、私たちが「平和とは何か」を再確認する契機でもあります。
国民の信頼を得ながら進める外交こそが、真の意味での「平和への貢献」につながると私は考えます。