12月9日に開催された県議会保健福祉委員会で、井手よしひろ県議は、県内の国民健康保険の現状について質問しました。
日本はすべての国民が健康保険制度に加入する「国民皆保険制度」(「こくみん・かい・ほけん」と呼びます)をとっています。この国民皆保険制度は、会社員や公務員を対象とする被用者保険とその他の者を対象とする地域保険である国民健康保険制度によって成り立っています。
さらに、被用者保険は、主に大企業の被用者を対象として企業・業種ごとに設立される組合管掌保険(いわゆる社会保険)と組合健保以外の被用者を対象として、政府により運営される政府管掌保険に分けられます。国保、組合健保、政管健保の3制度で国民の9割をカバーしています。
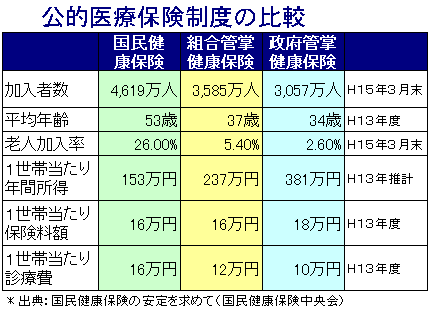
国保加入者は、平均年齢が高く、所得も低くなっています。一般的に、年齢が高くなるに比例して医療費が増高する傾向が見られ、国保の財政を圧迫しています。また、国保はほかの保険制度と異なり、保険料が報酬からの天引きとなっておらず、納付率が低いという特徴もあります。(H16年度で90.09%)
そのために、全国の保険者(市町村)のうち、7割以上が赤字となっています。(H15年度3144保険者のうち2289保険者が赤字)
井手県議は、こうした現状を踏まえた上で、茨城県内の国保保険料の納付率とその向上策を質しました。畑岡国民健康保険室長は、県の納付率は平成16年度で89.73%、全国平均(90.09%)を下回り、全国38位であることを示しました。
また、滞納者への対応として、まず有効期間が短い「短期被保険者証」(有効期限は3ヶ月または6ヶ月が多い)が発行され、その後も特別な理由なしに納付期限から1年以上未納状態が続くと、被保険者の返還が求められ、かわりに「被保険者資格証明書」が交付されます。この証明書で病院にかかると、窓口でいったん全額を払い、その後保険負担分が払い戻されるようになります(償還払い)。短期被保険者証の発行数は、平成17年6月1日現在で41,754件でとなっており、3年間で3.1倍になっています。被保険者資格証明書の発行数は、同じく6月1日現在で6532件で、2.1倍に増えています。
出産一時金と未納保険料の相殺はやめられないか
さらに、井手県議は、少子化対策の一環として行われている出産一時金と未納保険料の相殺について論究しました。現在、国民健康保険の加入者が出産をした場合、一時金として30万円が支給されています。しかし、保険料の未納があった場合、その額と相殺され、全額が支給されない場合があります。井手県議は、出産の祝い金という意味合いもあり、未納保険料との相殺を行わないよう提案しました。それに対して、畑岡室長は「心情的には理解できるが、法令で未納保険料を相殺することが定められており、市町村の独自に判断で出産一時金を全額支払うことは出来ない」と答えました。
井手県議は、出産一時金の意義を再確認し、国等にも法令の改正を求めるよう重ねて要望しました。



