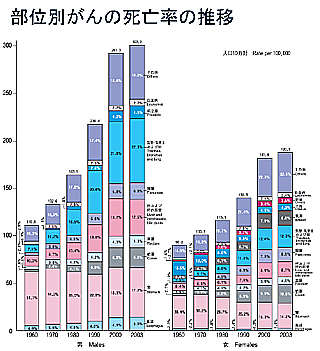 がん対策の基本は、現在、日本国内でどのようながんが多く発生し、発病から治療、治癒または死亡に至るまでの統計的なデータの蓄積です。諸外国では戦略的ながん対策を行うために、「がん登録」制度が確立しています。がん登録を実施している国の約半数では、「がん」を法律・条令によって「届出しなければならない疾患」と位置づけ、登録を義務付けています。
がん対策の基本は、現在、日本国内でどのようながんが多く発生し、発病から治療、治癒または死亡に至るまでの統計的なデータの蓄積です。諸外国では戦略的ながん対策を行うために、「がん登録」制度が確立しています。がん登録を実施している国の約半数では、「がん」を法律・条令によって「届出しなければならない疾患」と位置づけ、登録を義務付けています。
一方、日本では、国のがん対策におけるがん登録の位置づけは明確になっていません。国からの予算的措置もなく、厚生労働省による「健康審査管理指導事業実施のための指針」に基づき、地方自治体が主体となって、「地域がん登録制度」が実施されています。
しかし、地域がん登録制度は、すべての都道府県で行われているわけではありません。平成18年4月時点では、34の都道府県で行われているにすぎません。
2002年から施行された個人情報保護法の影響で、病院からの情報提供が得られない自治体もあります。厚生労働省は「がん登録は個人情報保護法の適用外」と通知していますが、がん登録の公益性が理解されないジレンマがあります。
また、わが国の地域がん登録は道府県政令市の事業であり、その方法、作業の概略、情報の流れ、実務担当部局の体制などは自治体によって異なります。この方法の違いは、整備されるがん統計の内容とその信頼性に大きく影響しています。
5月23日に、自民・公明の両党が提出した「がん対策基本法案」には、がん登録制度について、地域がん登録の取り組みを支援することが盛り込まれました。こうした法案の主旨をより具体化し、がん登録を国家レベルのがん戦略と位置づけ、標準的な方法でがん登録が実施されるための整備が喫緊の最重要課題となっています。
茨城県内に居住する住民に発生したすべてのがん患者を把握すると共に、その発病から治癒、死亡に至るまでの全経過を収集し、整理、保管解析するシステム。
【地域がん登録の目的】
登録された情報を基に、罹患率、受療状況、生存率などを測定し、がん対策の企画・評価の資料とする。
【実施主体】
茨城県
【登録実施方法】
①対象は、茨城県内に居住する入院・外来のがん患者
②対象医療機関は、県内の全医療機関(平成4年10月から実施)
③情報収集方法:医療機関が届け出で用紙に記入し、県保健予防課に郵送する「届出方式」。がん登録室が人口動態死亡小票から、がん死亡者を抽出して登録。
④収集情報の内容:
・がん患者の情報(氏名・生年月日・性別・住所)
・診断情報(部位・診断月日・検査方法等)
・治療情報(治療方法・手術内容・入院の有無等)
・死亡情報(死亡月日・死因・解剖の有無)
⑤集計・解析:登録情報を基に、暦年単位で部位別、年齢階級別、地域別に、罹患率の測定・受療状況の把握・生存率の測定を行う
 参考:茨城県のがん情報
参考:茨城県のがん情報


