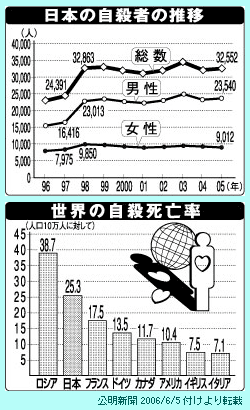 自殺者が8年連続で3万人を超える中で、国や自治体が自殺防止へ必要な手を打つことを責務とした自殺対策基本法案が今国会に提出される運びとなり、超党派の議員立法として成立する見通しとなりました。
自殺者が8年連続で3万人を超える中で、国や自治体が自殺防止へ必要な手を打つことを責務とした自殺対策基本法案が今国会に提出される運びとなり、超党派の議員立法として成立する見通しとなりました。
2005年、1年間の自殺者は、前年より227人多い3万2552人となり、8年連続で3万人を超えたことが6月1日、警察庁のまとめで分かりました。
自殺者数は統計を取り始めた1978年以降、約2万人台で推移してきましたが、98年に急増して3万人を超えて高止まりし、交通事故死者の約4倍以上に上ってます。
警察庁のまとめによると、遺書や生前の様子などに関する家族らの証言から判断した動機については「健康問題」が前年より228人多い1万5014人で全体の約半数を占めました。続いて「経済・生活問題」が全体の約4分の1を占める7756人と、4年連続で7000人を超えています。
年齢別では、全体の約6割を占める50歳代以上の自殺者が2年連続で減少した一方で、30~40歳代の世代が自殺するケースが目立ち、30歳代は過去最多となりました。
2002年にWHO(世界保健機関)が発表した資料によると、日本の自殺死亡率(人口10万人あたり)は、25.3と、国際的にも主要先進国の中で極めて高いことが分かます。欧米では「社会の努力で避けることのできる死」として、国レベルでの自殺予防対策を推進しています。
自殺対策基本法、国・自治体の責務を明記
事業者に従業員の心の健康保つ措置求める
今国会に提出される自殺対策基本法案では、自殺対策を「国と自治体の責務」と明記。自殺が個人の問題だけにとどまらず、その背景に過労や倒産、いじめなどの社会的な要因があることを踏まえ、「社会的な取り組み」として対策を実施すべき課題と掲げています。
自殺対策基本法は「自殺の防止」と「自殺者の親族などに対する心のケアの充実」を目的とし、特に近年、サラリーマンが経済苦や残業、職場での悩みなどで自殺するケースが増えているため、事業主に対して、従業員の心の健康を保つために必要な措置を取るよう求めています。
また、政府に対しては、自殺対策大綱の策定と、国会への年次報告を義務付け。内閣府に内閣官房長官を中心とした「自殺総合対策会議」も設置します。
さらに「政府は必要な法律上、財政上の措置を取らなければならない」として、国、自治体の基本的な施策として(1)自殺防止に関する調査研究や情報収集(2)人材育成(3)自殺の恐れがある人が受診しやすい精神科などの医療提供体制の整備(4)自殺未遂者など自殺の危険性が高い人の早期発見システムや発生回避(5)自殺未遂者と自殺者の親族に対する心のケア(6)市民団体やNPO(非営利団体)など民間団体への支援(7)自殺防止に関する教育、広報活動の推進――などを打ち出しています。
さらに、これまで個々に活動を実施してきた国、自治体、医療機関、学校なども連携して相互間の連携を取るよう求めています。
自殺者の約8割が抑うつ病状態だといわれています。社会にうつ病に関する知識をもっと広めると同時に、イメージ(印象)を変えていかなければなりません。地域や職場で、心の悩みが大きい人や、うつ状態に陥っている人を早期に発見し、適切な相談や専門家を紹介し治療することができるネットワーク体制を構築して、素早い対応を行うことが必要です。また、地域住民に対する自殺に関する教育や啓発運動、心の電話相談などを充実させていくことが重要です。
こうしたことに注目し、自殺対策に効果を上げている自治体もあります。秋田県では、地域住民を巻き込んだ自殺防止対策を実施し、効果を挙げています。地域別の自殺死亡数を見ると、北東北3県(秋田、青森、岩手)が全国上位3位を占めています。中でも、自殺率(人口10万人あたり)が11年連続で全国1位の秋田県は、2000年度から県や秋田大学、民間団体と協力して自殺予防事業をスタートさせました。
同対策の柱は、(1)情報提供や啓発(2)民間ボランティアなど各相談機関とのネットワーク体制の充実(3)うつ病対策(4)自殺予防モデル事業の推進(5)予防研究――の五つです。
秋田県内6町を順次、自殺予防のモデル地域に選定し、うつ病の可能性が高い人には専門家が面接に当たるなど取り組んだ結果、一昨年(2004年)、昨年(2005年)と2年連続で自殺率を減少させることができました。また、自殺やうつ病への理解を深めようと、シンポジウムを開催したり、リーフレットを作成し全戸配布するなど、きめ細やかな対策が奏効しています。
自殺対策基本法成立をキッカケとして、国と地方自治体が連携した、自殺防止への積極的な取り組みが望まれます。
「自殺率10年トップ」返上へ 秋田県が緊急対策
朝日新聞(2005年09月28日記事から)
自殺率が10年連続で国内最悪の秋田県は自殺予防事業を徹底させるための補正予算案(572万円)を組み、28日の県議会福祉環境委員会で詳細を説明した。全国の年間自殺者は7年連続で3万人を超えている。いち早く予防事業に乗り出した同県では昨年、増加傾向にあった自殺者数が減少に転じたが、今年は再び増加傾向にあり、追加対策を急いだ。自殺予防の「秋田モデル」は全国の自治体が注目しており、成否は国の総合対策にも影響を与えそうだ。
同県は00年度、本格的な自殺予防事業を始め、地域に応じたきめ細かいケアを続けてきた。効果はすぐには出ず、03年には年間の自殺者が500人を超え、自殺率も全国平均の1.7倍の44.6人(10万人当たり)に達したが、昨年は前年比67人減の452人にとどまった。減少傾向が続くかどうかがカギだったが、県警のまとめで今年8月末までの自殺者が前年同期を13人上回る328人に上ったことが分かり、県は危機感を強めた。
緊急対策では10月以降、経済苦からの立ち直りがテーマの講演会や、職場での「メンタルヘルス研修会」を開く。自殺予防のチラシを県内全世帯に配布し、「生活経済問題」「病苦」などをテーマにフリーダイヤルの電話相談も受け付ける。さらに、地域を限って集中的に自殺予防策を進めてきたモデル事業を、初めて市部に広げる。
 参考:秋田県のとりくみ「こころの健康づくり 自殺予防対策 うつ病対策」
参考:秋田県のとりくみ「こころの健康づくり 自殺予防対策 うつ病対策」



