出産費用として、親に現金支給されている「出産育児一時金」の支払い方法について、保険者から直接、医療機関に分娩費を支給する方式に改める改善策を厚生労働省がまとめました。今年(2006年)10月には都道府県知事に通知し、市町村など健康保険の運営者に改善を求めていく方針です。
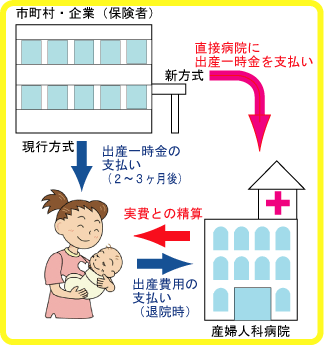 現在の制度は、出産後に請求し、赤ちゃん一人につき30万円(10月から35万円に増額)の一時金を受け取るまでに1カ月近く掛かる仕組みです。一時的ではあっても、高額の分娩費を親がいったん立て替える必要があるため、制度の改善を求める声が数多く寄せられていました。
現在の制度は、出産後に請求し、赤ちゃん一人につき30万円(10月から35万円に増額)の一時金を受け取るまでに1カ月近く掛かる仕組みです。一時的ではあっても、高額の分娩費を親がいったん立て替える必要があるため、制度の改善を求める声が数多く寄せられていました。
そこで公明党は、子育て支援策の一つとして、出産の家計負担を軽減するため、今年(2006年)4月に発表した「少子社会トータルプラン」の中で、出産費用の総額から出産育児一時金を差し引いた金額を支払うだけで済む「受領委任払い制度」のさらなる普及を提唱したほか、少子化対策に関する政府・与党協議会でも議論を重ね、一時金の支払い方法の改善策をまとめました。
新たな改善策は、出産予定日の1カ月前から被保険者による事前申請を受け付け、出産後に、保険者である市町村などが医療機関に直接、分娩費を支給します。
分娩費は医療機関によって違いがありますが、一時金が35万円に増額された10月以降、35万円を上限に支給します。
例えば、分娩費が30万円だった場合、保険者が30万円を医療機関に支払い、残りの5万円を親に支給する仕組みです。
また、分娩費が40万円掛かった場合は、保険者が医療機関に35万円を支払い、差額分の5万円を親が医療機関に支払うことになります。
この改善策は、今年(2006年)10月以降に厚労省からの通知を受け、保険者と医療機関が同意したところから順次、実施することになります。ただ、強制ではなく、各保険者の任意での実施となるため、市町村などでの改善策の実施に向けた積極的な取り組みが望まれています。
各医療機関は、被保険者などから出産費用が回収できない事例もあり、今回の制度改正案には概ね賛成の意向です。



