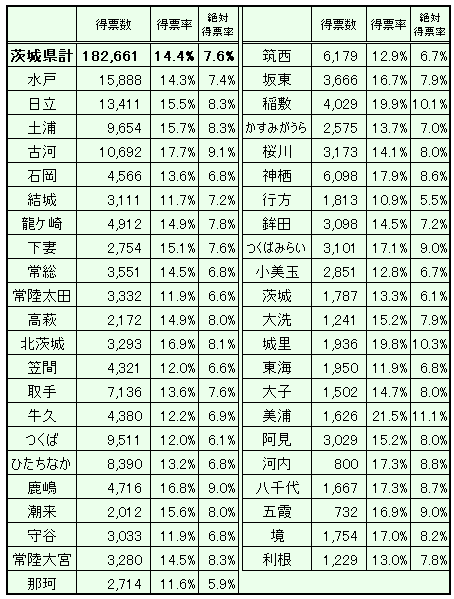最低賃金の大幅引き上げ
民主党参院選マニフェスト2007より
現行の最低賃金は年に1円から5円しか上がっておらず、地域によってはフルに働いても生活保護水準を下回るなど、ワーキングプア(働いても生活が困窮する状態)を生み出す要因のひとつとなっています。民主党は、まじめに働いた人が生計を立てられるよう、最低賃金の大幅引上げをめざし、「最低賃金法改正案」を提出しました。
主な内容は、①最低賃金の原則を「労働者とその家族を支える生計費」とし、②すべての労働者に適用される「全国最低賃金」を設定(時給800円を想定)、③全国最低賃金を超える額で各地域の「地域最低賃金」を設定、④中小企業における円滑な実施を図るための財政上・金融上の措置を実施する――ことなどで、3年程度かけて段階的に地域最低賃金を引き上げ、全国平均を時給1,000円にすることをめざします。
日本を支える中小企業の実態を無視した暴論
 最低賃金制度とは、昭和34年に定められた最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとされている制度です。
最低賃金制度とは、昭和34年に定められた最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとされている制度です。
仮に最低賃金より低い賃金を労働者、使用者双方の合意の上で定めても、それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同様の定めをしたものとされます。したがって、最低賃金未満の賃金しか支払わなかった場合には、最低賃金額との差額を支払わなくてはなりません。
最低賃金は、地域別、産業別に定められています。例えば、地域別の茨城県の最低賃金は655円ですが、東京は719円となっています。全国平均は673円です。(平成18年10月1日改訂)
民主党はマニフェストで、全国最低賃金として800円、3年以内に全国平均を1000円にするとうたっています。これは、働く者にとってとても耳障りの良い提案です。茨城県では1.5倍に引き上げられるのですから、フリーターなどにとっては非常にありがたいことです。
最低賃金引き上げは重要な課題ですが、問題はその中身が実現性があるかが問題です。例えば、時給700円の人に対し、時給1000円を支払わないといけなくなれば、その人にかかる人件費は1.4倍以上にも膨れあがります。その結果、企業は経営が悪化しないように雇用を抑制することになりかねません。それでは元も子もなくなってしまいます。
さらに、全国一律の最低賃金は、特に地方の中小・零細企業に過大な負担を強いる。民主党は「政権政策の基本方針」で「中小・零細企業の支援」を明記しているが、その具体像は一切示していません。その中小・零細企業を苦しめる内容の最低賃金を平気で打ち出しているのには驚かされます。民主党が、大企業の労働組合を背景とする所以でしょうか。
実際、中小企業経営者の多くが所属する日本商工会議所の山口信夫会頭も民主党案に対して「論外。現段階では不可能だ」(3月2日付「日経」)と断言し、現実的でないとの見方を示しています。
景気回復の恩恵が地方や中小企業にまで十分、行き渡っているとはいえない現実を直視すれば、いきなり平均1000円の最低賃金というのは実現性のない暴論に他なりません。
最低賃金について公明党は、生活保護との整合性を考慮して水準を引き上げるべきと主張しています。
国民受けを狙った政策を打ち出したとしても、それが実現できなければ絵に描いた餅にすぎません。