この4月1日からメタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)に着目した特定健診・保健指導(メタボ健診)が始まります。メタボ該当者やその予備群に生活習慣改善を促すことで、生活習慣病の発症や悪化を予防し、医療費削減を目指す制度です。保険者(市町村県)に目標を定め、目標が達成できない保険者には、後期高齢者医療制度への財政負担が最大10%加算されることになるという、ペナルティも課せられるこの制度に注目が集まっています。
生活習慣病の患者減が目標、40~74歳を対象
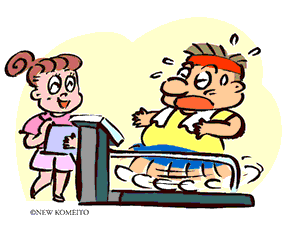 メタボ健診は「内臓脂肪の蓄積が糖尿病や高血圧、脂質異常などの共通の原因となっている」との考え方に基づく新たな生活習慣病対策です。日本内科学会などが2005年に発表したメタボリックシンドロームの診断基準が基本となっています。腹囲、BMI(体格指数)などが基準を超えたメタボ該当者・予備群などに対して保健指導を実施します。
メタボ健診は「内臓脂肪の蓄積が糖尿病や高血圧、脂質異常などの共通の原因となっている」との考え方に基づく新たな生活習慣病対策です。日本内科学会などが2005年に発表したメタボリックシンドロームの診断基準が基本となっています。腹囲、BMI(体格指数)などが基準を超えたメタボ該当者・予備群などに対して保健指導を実施します。
厚生労働省によると、生活習慣病の医療費は国民医療費の3分の1を占めます。生活習慣の変化などから、脳卒中や心筋梗塞などの発症のリスクが高くなる糖尿病患者らが急増しています。医療費削減のためにはこうした疾患の発症や悪化予防が欠かせないとして、国は2015年までに糖尿病などの生活習慣病患者・予備群を2008年度比で25%減を目標としています。
そこで「内臓脂肪型肥満」の削減をポイントに置いた政策が導入されました。内臓脂肪を薬ではなく、食生活の改善や適切な運動などによって減らすことで、内臓脂肪蓄積の結果として起こる血糖や血圧、脂質の異常が解消しようとする試みです。それによって、その人の生活の質の向上につながるとともに、医療費抑制の実現が期待できます。
このメタボ健診は医療保険者(市町村や健康保険組合など)に実施が義務づけられます。対象は40~74歳の医療保険加入者約5600万人です。市町村国保加入者には市町村が実施し、健康保険加入者には職場健診と兼ねて実施します。
またこのメタボ検診は、検診による健康状態の改善の実績そのものが評価されます。従来の健診や保健指導は、さまざまな病気の早期発見を目指し、その実施回数や参加人数など「実施した」という実績を評価していました。しかし、一方、新制度では、生活習慣を変えた方がよい、内臓脂肪が蓄積している人をいち早く見つけ出し、実際に改善に結び付けることが目標となります。評価方法も「本当に生活習慣病患者、予備群が減ったか」という結果を評価することになります。
各保険者(市町村や健保組合)とも12年度までに、メタボリックシンドローム該当者や予備群を10%減少させることなどが目標とされています。達成できない保険者には、後期高齢者医療制度への財政負担が最大10%加算されることになります。この場合、結果的に保険料の値上げなどが必要になって保険加入者の負担増につながる懸念もあります。
特定検診から特定保健指導へ、「積極的支援」「動機付け支援」「情報提供」に3分類
特定健診の項目は、従来の住民健診(基本健診)項目に腹囲とLDL(悪玉)コレステロールを加えたものになります。腹囲はメタボ判定に特に重要な項目で、内臓脂肪の蓄積の程度を反映するとされています。
健診では、◎血圧測定、◎血液検査(脂質、肝機能、血糖)、◎尿検査(尿糖、尿たんぱく)、◎身体計測(身長、体重、腹囲)のほか、問診や身体計測(身長、体重、腹囲)を実施する。腹囲かBMI(肥満度の判定方法の一つで、ボディ・マス・インデックス指数のこと。体重(kg)/身長(m)2で求められ、標準値は22.0。25以上が肥満と判定されます)が基準を超え、他の検査に一定の異常があった人は、特定保健指導の対象になります。
前年度の健診で血圧、血糖、脂質、肥満(腹囲かBMI)の4項目すべてが基準以上になった人は、心電図検査や眼底検査を受ける場合もあります。医師の判断で貧血検査を行うこともあります。
特定保健指導には、継続して具体的に生活改善の方法を指導する「積極的支援」と、自分自身で改善できるよう助言などをする「動機付け支援」が行われます。国のルールに基づき、一部の検査結果のうち基準以上の項目が多い人が「積極的」、少ない人が「動機付け」の対象となります。腹囲やBMIが基準未満の場合は「情報提供」として、生活習慣見直しのきっかけとなるような資料が送付されます。
メタボ健診への疑問と課題
世界でも類例を見ない政策として注目されるメタボ健診ですが、様々な課題も指摘されています。
メタボ健診は、内臓脂肪型肥満が原因の生活習慣病を主なターゲットとしています。腹囲やBMIが基準値未満だと、血糖や血圧などに異常があっても、食事や生活習慣の改善を指導する保健指導の対象にもしていないため、健診の質の低下が懸念されています。
福岡県内のある市の試算では、保健指導の対象者は国保加入者のわずか3%にすぎません。血糖などに異常があっても、腹囲は基準以下という人も多いからです。この市の担当者は「メタボだけに焦点を当てては、国が掲げる『生活習慣病有病者・予備群の25%削減』は達成できない」と批判しています。
がん検診と住民健診を同時に実施してきた自治体にとっては、がん検診の受診率低下も心配されています。従来は両健診とも市町村が全住民を対象に実施してきました。しかし、市町村のメタボ健診は原則として国保加入者だけが対象となり、国保加入者以外はがん検診を別に受ける必要が出てきます。がん検診受診者が減れば、がんによる医療費増につながりかねません。
また、保険者に対するペナルティの問題も深刻です。市町村の場合、2012年度までに、◎健診実施率65%、◎指導対象者に対する保健指導実施率45%、◎メタボ該当者・予備群の減少率10%--を達成できないと、後期高齢者医療制度への財政負担が最大10%加算されることになっています。
健診実施率や指導実施率の目標達成も容易ではありません。05年度の住民健診受診率は全国平均43.8%で、65%には程遠い状況です。市町村国保の過半数は赤字で、ペナルティーによって保険料値上げが必要になる自治体が出る恐れもあります。目標を達成できないと住民が連帯責任を負わされる形になります。



