10月24日、井手よしひろ県議は日製日立総合病院に岡裕爾院長を訪ね、産婦人科の医師確保問題について現状を聴取しました。日製日立総合病院は、この8月から来春4月以降の分娩予約を中止しています。6名いた産婦人科医が派遣元の東大病院に戻されることになり、10月には既に2名の医師が日立を離れています。来年3月には残り4名も移動することになっています。
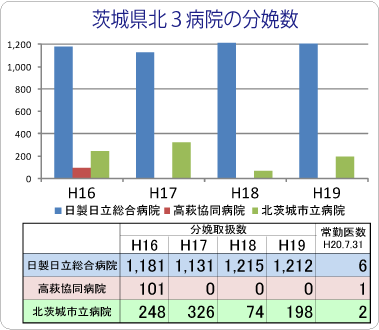 日製日立病院は、県北地域の周産期医療を一手に担ってきたと言っても過言ではありません。毎年、2400例ほどある分娩の半分以上を日製病院が行っています。茨城県での分娩扱い数は最大となっています。
日製日立病院は、県北地域の周産期医療を一手に担ってきたと言っても過言ではありません。毎年、2400例ほどある分娩の半分以上を日製病院が行っています。茨城県での分娩扱い数は最大となっています。
しかし、その現場は”過酷”の二文字であったようです。2月8日付の読売新聞には、日製病院の産婦人科主任医長山田学先生が紹介されています。
24時間勤務 最高で月20日、「体力の限界」開業医も撤退
読売新聞(2008/2/8)
「このままでは死んでしまう」。茨城県北部にある日立総合病院の産婦人科主任医長、山田学さん(42)は、そう思い詰めた時期がある。
同病院は、地域の中核的な病院だが、産婦人科の常勤医8人のうち5人が、昨年3月で辞めた。補充は3人だけ。
しわ寄せは責任者である山田さんに来た。月に分娩(ぶんべん)100件、手術を50件こなした。時間帯を選ばず出産や手術を行う産婦人科には当直があるが、翌日も夜まで帰れない。6時間に及ぶ難手術を終えて帰宅しても夜中に呼び出しを受ける。自宅では枕元に着替えを置いて寝る日々。手術中に胸が苦しくなったこともあった。
この3月、さらに30歳代の男性医師が病院を去る。人員の補充ができなければ、過酷な勤務になるのは明らかだ。山田さんは、「地域の産科医療を守ろうと何とか踏みとどまっている。でも、今よりも厳しい状態になるようなら……」と表情を曇らせた。(略)
日製日立病院では、この9月から里帰り出産の受付を中止しました。岡院長を先頭に、産婦人科医の人数確保に全力を挙げてきましたが、現在の段階では、具体的な進展は全くみられません。既に、医師を派遣してきた東大病院では、日製日立病院から産婦人科医師を全員引き上を前提で、来年度の医師の配置を決定しているといわれています。東大病院自体が深刻な産婦人科医師不足に曝されているのです。
行政も手をこまねいて見ているわけではありません。9月上旬、日立市長と県の担当者は、東大病院を訪れ、医師の残留を直訴しました。しかし、これは一蹴されたと言われています。
 井手県議ら公明党も、8月以来いち早く行動を起こしました。党員・支持者に署名を募り、9月17日には厚労省に舛添要一大臣宛の要望書を提出しました。9月県議会では、代表質問でこの問題を取り上げ、橋本知事に積極的な対応を強く求めました。
井手県議ら公明党も、8月以来いち早く行動を起こしました。党員・支持者に署名を募り、9月17日には厚労省に舛添要一大臣宛の要望書を提出しました。9月県議会では、代表質問でこの問題を取り上げ、橋本知事に積極的な対応を強く求めました。国や県は、日製日立病院の産婦人科を守るということでは、強い意思を明確にしています。公明党は日立市並びに県に対して、医師確保に対して財政的な支援を行うよう、来年度予算要望を行うことを決めています。
しかし、行政からの財政支援や医師の緊急派遣制度などを活用しても、現状の6人の体制を守ることは非常に難しいと言わざるを得ません。
岡院長との意見交換では、院内助産院の設置など、病院側で出来る最大の努力を行うとの強い決意を聞くことができ来ました。県北地域の周産期医療を守るとの責任感を感ずることができました。公明党としても全力を挙げて病院を支援していきたいと思います。
(写真は、9月17日厚労省で日製日立病院の産婦人科医の確保を要望する井手県議ら公明党議員団)
井手よしひろ県議の代表質問:県北地域の周産期医療体制確保(2008/9/9)
次に、地域医療の諸課題について伺います。
昨年来、危惧されていた日立製作所日立総合病院の産婦人科医師の確保問題が、いよいよ表面化してきました。8月8日、日製日立病院は、来年4月以降の産婦人科医師の確保が不透明であるとして、分娩予約の一時中止を公表しました。
平成18年の日立医療圏の出生数は2257人ですが、日製日立病院は、このうちの半数超の1215人の出産を手掛けています。この分娩取扱数は、茨城県内では最大で、県北地域の周産期医療は日製日立病院によって守られている状況です。
現在、日立医療圏で、出産が出来る医療機関は、病院が3、医院1、助産院1の5施設しかありません。その基幹病院が深刻な医師不足に曝されています。
日製日立病院の常勤産婦人科医は現在6人。産科医は24時間体制の宿直や休日当番、緊急の呼び出しなどがあり、過酷な労働条件の中働いています。来年の4月以降、医師を派遣している東京の大学との交渉が不透明な状況になっているようです。
万が一、日製日立病院での出産が出来なくなった場合の影響は、多大なものがあります。県北地域の周産期医療環境を守るため、知事はどのような取り組みをされようとしているのか、お尋ねいたします。
昨年来、危惧されていた日立製作所日立総合病院の産婦人科医師の確保問題が、いよいよ表面化してきました。8月8日、日製日立病院は、来年4月以降の産婦人科医師の確保が不透明であるとして、分娩予約の一時中止を公表しました。
平成18年の日立医療圏の出生数は2257人ですが、日製日立病院は、このうちの半数超の1215人の出産を手掛けています。この分娩取扱数は、茨城県内では最大で、県北地域の周産期医療は日製日立病院によって守られている状況です。
現在、日立医療圏で、出産が出来る医療機関は、病院が3、医院1、助産院1の5施設しかありません。その基幹病院が深刻な医師不足に曝されています。
日製日立病院の常勤産婦人科医は現在6人。産科医は24時間体制の宿直や休日当番、緊急の呼び出しなどがあり、過酷な労働条件の中働いています。来年の4月以降、医師を派遣している東京の大学との交渉が不透明な状況になっているようです。
万が一、日製日立病院での出産が出来なくなった場合の影響は、多大なものがあります。県北地域の周産期医療環境を守るため、知事はどのような取り組みをされようとしているのか、お尋ねいたします。

産科医の確保日製病院難航
読売新聞(2008/10/29)
来年4月以降の分娩(ぶんべん)の予約受け付けを「一時中止」している日立市の日立製作所日立総合病院の産科医確保が難航している。病院や同市によると、産科医の派遣元大学の「全員引き揚げ」の姿勢に変化がないという。
日製病院産婦人科の産科医は全員、大学から派遣を受けており、5月下旬に大学から「産科医全員を引き揚げるかもしれない」と伝えられた。2人が9月で引き上げ、現在の産科医は4人。病院と県、市などは派遣継続を要請しているが、大学側は「開業医になる医師が増えて、医師を派遣する余力が大学にもない」などと説明したという。
日製病院は、産婦人科を閉鎖しない方針を固めており、派遣元の大学以外のルートでの産科医確保、正常分娩を扱う院内助産所の開設も探っているが、結論は12月ごろになる見込みだ。
同市の樫村千秋市長は28日の記者会見で「来年4月以降に産科医がゼロになることは避けたい」とする反面、「もう少し様子を見るしかない」と述べるにとどまり、市の対応に手詰まり感をにじませた。
日製病院は、県北地域の中核的な周産期母子医療センターに位置づけられ、年間に約1200件の出産を担っている。



