深刻さ増す派遣社員の2009年問題、一斉に契約期間が終了
失業者の増加に拍車かける恐れ
相次ぐ規制緩和の結果、製造業は2006年に大量の派遣社員を受け入れました。その3年間の契約期間が今年、一斉に更新時期を迎えるからです。世界的な景気低迷で、各メーカーは減産を進めており、契約期間が切れた派遣社員の大量失業が懸念されている。これが製造業で働く派遣社員の「2009年問題」です。
バブル経済の崩壊後、日本企業は、パート、派遣、契約社員などの非正規雇用者を増やすことで経営体質の強化を図りました。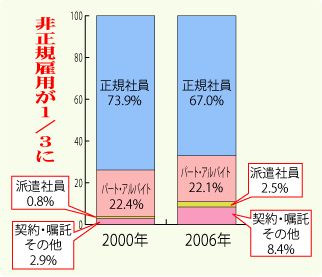 非正規労働者数は、バブル期の1987年に711万人でしたが、バブル崩壊後の97年に1152万人、2007年には1732万人に増加しており、03年以降、労働者全体(役員を除く)の3割を超えています。
非正規労働者数は、バブル期の1987年に711万人でしたが、バブル崩壊後の97年に1152万人、2007年には1732万人に増加しており、03年以降、労働者全体(役員を除く)の3割を超えています。
製造業は当初、「技術力が低下する」などの懸念から、派遣社員の受け入れは労働者派遣法で認められていませんでしたが、その後の法改正で、04年3月から最長1年間の期限付きで解禁。契約期間は07年3月から最長3年に延長されました。
こうしたなか、“偽装請負”が社会問題化した06年半ば以降、多くの企業が非正規雇用の形態を「請負」から「派遣」に転換しました。厚生労働省の調査では、06年度の派遣労働者数は、前年度比26%増の321万人(うち製造業は24万人)に膨れ上がっています。この時に派遣社員になった人たちが今年、一斉に契約期間を終えることになります。
「2009年問題」は当初、企業側の問題として受け止められていました。(08年金融危機が発生するまでの2009年問題の視点は、ダイヤモンド・オンライン「製造業が直面する『2009年問題』の深刻度」にわかりやすく掲載されています)
派遣社員の契約期間が短いのは、派遣労働が「正規労働などへのつなぎ」と位置付けられているからです。
契約期間が切れた派遣社員に対し、企業は(1)3カ月超のクーリング期間(その派遣先・業務で働かない期間)を置いた後、再び派遣契約を結ぶ、(2)契約期間の制限がない請負に雇用形態を変える、(3)正社員や期間社員として直接雇用する、(4)契約を打ち切る――の4つの選択肢の内一つを選ぶことになります。
請負に切り替えると、仕事の指示・命令系統が、それまでの受け入れ企業から請負業者に移るため、企業は従業員に指示・命令をしなくても済むよう、業務の習熟度を上げる研修などを行う必要が出てきます。直接雇用にすればコスト増に直結してしまいます。クーリング期間を設けると、その間の労働力不足から、製造現場が機能不全に陥りかねない現状があります。
しかし、米国発の金融危機による世界経済の急速な悪化で、自動車メーカーをはじめ各製造業は昨年夏以降、需要の激減に直面し、軒並み減産体制に突入。その結果、「派遣切り」といわれる人員整理が始まり、09年問題は深刻な労働者問題としてクローズアップされるようになりました。
厚生労働省は昨年12月26日、期間満了での「雇い止め」や期間途中での中途解除・解雇で職を失う非正規労働者が、08年10月から今年3月までの半年間で8万5000人に上るとの調査結果を発表しました。このうち派遣社員は5万7000人と7割近くに上り、業種別では、製造業が96%を占めています。
これに加え、09年問題が控える。既にトヨタ自動車九州では、06年度に受け入れ、09年度に3年を迎える派遣社員を中心とした、全派遣社員約1100人について、09年度中に雇い止めにする方針を固めています。契約期間を終える派遣社員の大量発生は失業者の増加に拍車を掛ける懸念があります。
住宅確保・雇用の維持・雇用の確保・職業訓練の充実の4つの視点で具体的対策展開
雇用不安が社会問題化するなか、政府・与党は新雇用対策を昨年12月9日に決定し、既に実施に移しています。主な対策は次の通り。
【住宅の確保】
◆事業主が雇い止め・中途解除した派遣社員などに対し、離職後も引き続き住宅を無償で提供する場合への助成。
◆住宅からの退去を余儀なくされた離職者に対し、入居初期費用(上限50万円)、家賃補助費(上限月額6万円、6カ月まで)、生活・就職活動費(上限100万円)を貸し付け。
◆雇用促進住宅(1.3万戸)への入居促進。
【雇用の維持】
◆企業が教育訓練・出向・休業措置により、雇用の維持を図った場合に賃金・手当の一定割合を助成する雇用調整助成金について、雇用期間が6カ月未満の非正規労働者も対象に追加。
◆派遣社員を直接雇用に切り替えた場合、その派遣先事業主に対し労働者一人あたり100万円(期間雇用、大企業には50万円)を支給。
【雇用の確保】
◆「ふるさと雇用再生特別交付金」(仮称)と「緊急雇用創出事業」(仮称)で、合わせて4000億円規模の雇用創出のための基金を創設。
◆非正規労働者就労支援センターを開設し、離職した派遣社員などの再就職を応援。全国のハローワークでも相談支援を実施。
【職業訓練の拡充】
◆離職者訓練を各都道府県で追加実施するほか、来年度は、今年度より4万人増の約19万2000人規模に拡大。介護など、今後成長が見込まれる分野の長期間の訓練も実施。
◆訓練期間中の生活保障給付制度を創設。一定要件で返還が免除される仕組みで、額も従来の4・6万円(貸し付けのみ)から10万円に拡充。扶養家族を持つ人は12万円に。



