11月30日の参院本会議で、与党と公明党などの賛成で「肝炎対策基本法」が成立しました。肝炎対策基本法は、患者団体の要望を受け、公明党が自民党とともに与党時代に議員立法で提出した法案をベースにしています。国内最大の感染症である肝炎の対策が、すべての患者の救済をめざして大きな一歩を踏み出しといえる快挙です。
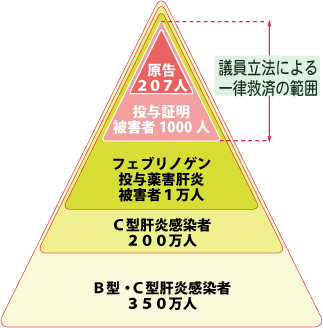 肝炎は、適切な治療を行わないまま放置しておくと慢性化し、肝硬変、肝がんに進行する場合もある病気です。昨年1月には公明党の主導で「薬害肝炎救済法」が成立しました。しかし、薬害肝炎救済法は、薬害C型肝炎の被害者だけが対象でした。
肝炎は、適切な治療を行わないまま放置しておくと慢性化し、肝硬変、肝がんに進行する場合もある病気です。昨年1月には公明党の主導で「薬害肝炎救済法」が成立しました。しかし、薬害肝炎救済法は、薬害C型肝炎の被害者だけが対象でした。
今回は、すべての肝炎患者の救済をめざした法律である。全国で約350万人と推定される肝炎患者や家族、および関係者の長年の悲願であった「全員救済」への確かな道が開かれたことを評価します。
特筆すべきは、法律の前文に「国の責任」を明記した点です。肝炎ウイルスが混入した血液製剤を投与されて発生した薬害C型肝炎事件や、集団予防接種の際、注射器が連続使用されたことによるB型肝炎ウイルスの感染拡大について、その被害を防止できなかったことを「国の責任」と明記しました。
その上で、国や地方自治体が講じる基本的施策として、(1)肝炎医療の提供などを行う医療機関の整備と医師の育成(2)肝炎患者の経済的負担の軽減(3)肝炎患者の医療を受ける機会の確保――などを挙げています。また、肝炎から進行した肝硬変、肝がんについても必要な支援を行うことを盛り込みました。施行日は平成22年1月1日となっています。
肝炎対策について公明党は、薬害肝炎全国原告団(山口美智子代表)らと連携を取りながら、薬害肝炎救済法をはじめ、治療費の助成制度の実現などを一貫してリードしてきました。
肝炎対策基本法を受け、原告団の山口代表は「公明党が党派を超えて(法案成立を)呼び掛けていただいたおかげで、ここまで来られた」と述べました。
これに対し、公明党の山口那津男代表は、原告団の長い活動に敬意を表した上で、「皆さんの願いが実を結んだ。私たちも一層(今後の活動を)お手伝いしたい」と応じています。
今後の課題は、差別や偏見の排除や治療費助成制度の普及
しかし、肝炎対策基本法は肝炎の総合対策の理念や枠組みを定めたもので、今後は患者支援策の具体化が課題になります。当面は患者負担の重いインターフェロンなどに対する治療費助成の予算措置など、政府がどのような支援策を打ち出すのかが焦点です。
一方、肝炎対策基本法では「肝炎に対する正しい理解が、国民すべてに定着しているとは言えない」としています。病気を理由に解雇されたり、離婚を迫られるといった差別や偏見の排除も課題として挙がっています。
また、国と都道府県がインターフェロンの予算枠を確保したにもかかわらず、治療実績が期待された程上がっていないという現状も無視できません。
茨城県では平成20年度の予算にインターフェロン治療助成金として5億7900万円を計上しました。しかし、実際に助成された金額は1億8171万円と3割程度しか消化できませんでした。受給者の人数は1055名でした。この結果は、充分に治療費助成の制度が患者さんに知らされていないことと、治療のための肉体的負担(インターフェロン治療には強い副作用がある場合もあります)、時間的負担(治療には定期的なインターフェロン投与が必要になります)が多きことが原因と思われます。
肝炎患者への情報提供を進めると共に、インターフェロン治療が出来る医療金の拡充など負担軽減を一層図る必要があります。



