最近、県の来年度予算編成に関する要望を伺うと、一番多いご意見が治療の充実ということです。特に、救急医療、産婦人科医療、小児科医療に関しては、悲鳴に近い声が寄せられます。民主党は、そのマニフェストで、医学部の定員を1.5倍に引き上げることを公約しました。
●医師養成数を1.5倍に増加
崖っぷち日本の医療、必ず救う!(民主党医療政策の考え方)より引用
医療崩壊をくい止めるため、また、団塊世代の高齢化に伴い急増する医療需要に応え、医療の安全を向上させるため、医師養成の質と数を拡充します。
当面、OECD諸国の平均的な人口当たりの医師数(人口1000人当たり医師3人)を目指します。
大学医学部定員を1.5倍にします。新設医学部は看護学科等医療従事者を養成する施設を持ち、かつ、病院を有するものを優先しますが、新設は最小限にとどめます。地域枠、学士枠を拡充し、医師養成機関と養成に協力する医療機関等に対して、十分な財政的支援を行うとともに就学する者に対する奨学金を充実させます。
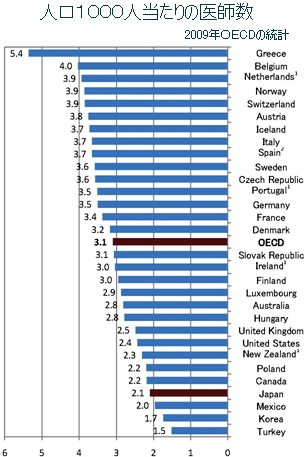 この公約に対して、平成22年度の予算では何の手立ても打たれなかったことは、大変残念です。それどころか、自民・公明の前政権が補正予算に計上した「地域利用再生基金」を、3100億円から3分の2にカットするなど、公約と実際に行っている施策とのギャップが大きくなっています。
この公約に対して、平成22年度の予算では何の手立ても打たれなかったことは、大変残念です。それどころか、自民・公明の前政権が補正予算に計上した「地域利用再生基金」を、3100億円から3分の2にカットするなど、公約と実際に行っている施策とのギャップが大きくなっています。補正予算の見直しによって、各都道府県には25億円規模の再生基金事業が2つずつ交付されました。
「寄付講座」に22億円、30名以上の医師確保を目指す
茨城県では、医学系大学の講座に県が予算を支出する「寄付講座」を中心として、県外の医科大学とも積極的な連携を図り、見返りに優先的に医師を派遣してもらいう政策を重点的に行います。
人口300万人を抱える茨城県には、医学部のある大学が筑波大学一校しかありません。医師の絶対数が足りない最大の要因となっています。
一方で、県内には東京医科大の付属病院・茨城医療センターや、東京医科歯科大の最大の教育病院となっている土浦協同病院のように、県外の医学系大学と結び付きの深い病院も存在しています。
そこで茨城県は、県内外の医学系大学との連携を強化し、優先的に医師を派遣してもらう組みづくりに、平成22年度から取り組み、5大学との連携に約22億円を計上しました。
具体的には、筑波大学に7億5000万円の予算を投じ寄付講座を開講します。県立中央病院を教育拠点として位置づけ、医師8人、後期研修医の派遣を目指します。
東京医科歯科大学には、6億6000万円の予算で、小児、周産期医療の寄付講座を開講。遠隔医療システムを整備するなどして、土浦協同病院に医師11人、後期研修医の派遣などを求めます。さらに、土浦協同病院から医師不足が深刻化する地域の中核病院に医師を再派遣する計画です。この方法で、派遣医師は指導医のいる土浦協同病院の所属となり、学会認定医などの資格取得や診療技術の向上など多くのメリットが得られます。
東京医科大学には、3億7000万円を投じ、寄付講座と東京医科大学付属病院・茨城医療センターに医師を増員します。また、それによって後期研修医の指導体制を強化します。
日本医科大学には2億円の予算で、寄付講座を設けます。筑西市民病院や神栖済生会病院などに5名の医師の派遣を目指します。
自治医科大学にも2億3000万円の予算を計上し、寄付講座を開設。県西地区の病院に4名の医師確保を進めます。
「地域枠」の拡大で15名の医師増員
寄付講座を中心とする地域医療再生計画とは別枠で、県が医学部の学生に奨学金を出す見返りに卒業後の一定期間、茨城県内の医師不足地域に勤務する推薦入学枠=地域枠も7人分拡大しました。内訳は、筑波大学2名、東京医科大学2名、東京医科歯科大学2名、杏林大学1名となっています。地域枠の予算額は1億3000万円です。
なお、地域枠はすでに増員済みの筑波大5名、東京医科大3名とと合計すると15名となり、増員数では全国一となりました。
当面は寄付講座で、長い目では奨学金による地域枠拡大を
こうした県の医師確保策について、県医師会の原中勝征会長は次のように語っています。「寄付講座は、本来は間違った政策だ。医大には相当国民の税金が使われている。お金をやるから医師を回せという態度自体が間違いだ。しかし、そこまでしないと医師が足りないという現状を認めないといけない。茨城県は人口当たりの医師の数が下から2番目だったのが、新しい調査によると、去年は最下位になった。それを考えると何としても医師を派遣してもらわないといけない。この県からよその県の医大に行く人たちに奨学金制度が作られた。あれは正しい。例えば医師一人当たりにして自治医大の負担金の10分の1以下で済む。奨学金制度は始め、8人募集したが20人の応募があり20人全員に支給した。学生は夏休みになると県内の大きな病院で研修を受けている。大成功だと思う」と、寄付講座と地域枠について、厳しい医師不足の現状を克服するためには、必要な政策と是認しています。



