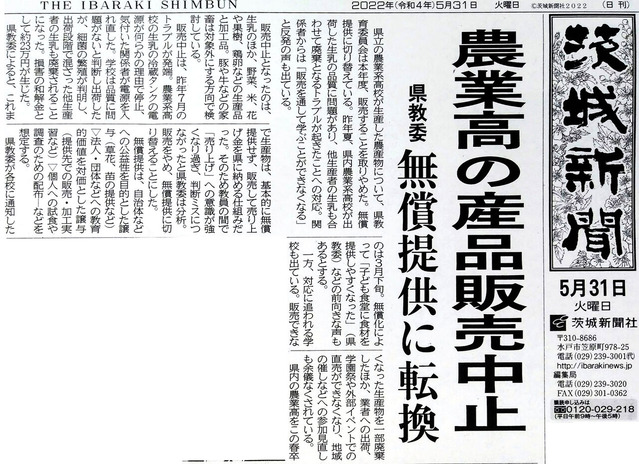公明党アンケート結果に表れた戸別所得補償制度への失望感
 鳩山政権が農業政策の柱としているコメ農家に対する「戸別所得補償モデル対策」の参加申請が、この4月1日よりスタートしました。多くの農家が同制度に対する疑問や不満を抱いたままの出発となりました。
鳩山政権が農業政策の柱としているコメ農家に対する「戸別所得補償モデル対策」の参加申請が、この4月1日よりスタートしました。多くの農家が同制度に対する疑問や不満を抱いたままの出発となりました。
公明党茨城県本部が農家を対象に行ったアンケート結果(3月19日公表)によると、補償制度導入で「農業経営が良くなる」と評価したのは9.8%にとどまり、12.8%が「悪くなる」と回答しています。「現状と変わらない」は74.1%と大多数を占めています。また、農業後継者が増えるかとの問いについては、「増える」がわずか3.1%だったのに対し、「減る」は23.5%。補償制度に対し、農家が極めて厳しい目を向けている実態が浮き彫りになっています。
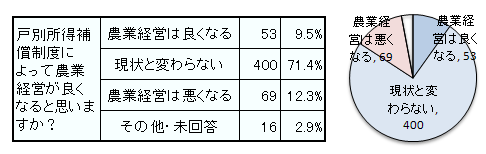
補償制度の開始に際して、赤松農水相は「(制度は)農山漁村に暮らす人々が将来に向けて明るい展望を持って生きていける環境を作り上げていくための施策」との談話を発表しましたが、農家の評価との落差は極めて大きいといえます。
戸別所得補償制度は、一定の生産数量目標に従う農家に対し水田10アール当たり全国一律に1万5000円を支給した上で、販売価格が下落した場合に生産コストを賄う水準を上乗せし、補償する仕組みです。
この制度導入で、コメ政策は生産調整(減反)から農家の直接支援へ約40年ぶりの転換となりました。しかし、農家には政策転換に対する周知が十分でないことなどから、混乱が見られ、政府の準備不足が露呈しています。
さらに政府は、補償制度の本格実施を盛り込むはずだった「食料・農業・農村基本計画」について、財源確保のメドが立たないなどの理由で、開始年度や具体的な対象品目などを示さないまま先月末に閣議決定しました。
補償制度の開始をコメ農家に限定し、農家間の不公平感や不満が生じたためか、鳩山首相は今月4日の農業関係者との懇談で11年度からコメ以外の農作物の補償制度導入へ意欲を示しましたが、一貫性を欠く政府の対応に農家の期待感は後退するばかりです。
 公明党県本部のアンケート結果によると、戸別所得補償制度が全国一律で実施されることに対しては、48.3%が「全国一律を見直すべき」と回答しました。耕作条件が地域ごとに違うのもかかわらず、補償額が一律であることに強い不満が寄せられています。
公明党県本部のアンケート結果によると、戸別所得補償制度が全国一律で実施されることに対しては、48.3%が「全国一律を見直すべき」と回答しました。耕作条件が地域ごとに違うのもかかわらず、補償額が一律であることに強い不満が寄せられています。
また、県内には野菜や果樹農家が数多く存在するものの、これらの作物への補償は行われないことから、59.8%が「コメ以外に戸別補償がないのは不公平」と考えていることが分かりました。
茨城農業の改革のためには、地域ごとのきめ細やかな農業政策の展開が必要です。首都圏という日本最大の消費地に直結する茨城では、多様な農業がその特徴です。農地の拡大と費用低減のために、担い手への農地集積が必要であるという一般的なロジックは、茨城には通用しないと考えます。
むしろ、こうした生産者側の視点ではなく、消費者のベストパートナーを目指し、「喜んで買ってもらえる農産物づくり」「買ってもらえる米づくり産地の育成」「マーケティング戦略に基づく産地育成」が何よりも必要です。これは、民主党の推し進める戸別所得補償制度とは、まさに対極をなす政策です。地域農業者と行政とが農業の将来展望を描きながら、独自の補助制度や支援制度を組み立てることが必要です。
また、農業後継者問題や海外からの研修生問題など、農業労働力をどのように確保するかという問題が深刻になっています。アンケートの有効回答の年齢分布は、70歳以上が23.1%、60歳以上が58.3%と過半数を遙かに超えています。いかに農家の高齢化が進んでいるかを物語っています。あと、10年後には最後の一線で持ちこらえていた高齢者の一斉リタイアによる『地滑り的変動』が引き起こされる可能性があります。限られた時間内に、農業の労働力不足への具体的な対応が強く望まれています。
(写真上:筑西市内の農家で意見交換した長沢ひろあき党政策審議会副会長、写真下:常陸太田市内の耕作放棄地対策を視察する太田昭宏前党代表)