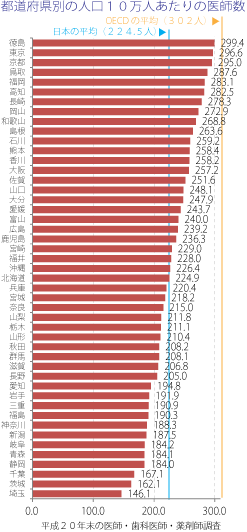 茨城県の医師不足をどのように解消していくかは、県政の重要な課題の一つです。人口10万人当たりの医師数を厚労省の「平成20年末の医師・歯科医師・薬剤師調査」で比較したものが、右のグラフです。
茨城県の医師不足をどのように解消していくかは、県政の重要な課題の一つです。人口10万人当たりの医師数を厚労省の「平成20年末の医師・歯科医師・薬剤師調査」で比較したものが、右のグラフです。
医師の数は、どちらかといえば「東高西低」のようになっているのがわかります。古くは明治維新で薩長側の地域に医学部が優先されて整備されたとか、国の一県一医学部政策から小さな県が多い西日本の都道府県が結果的に医師数が増えたとか、その理由は説明されています。
しかし、国際比較でみれば、OECD諸国平均が302人であり、一番医師が多い徳島県でも、このレベルには達していません。
さらに、それだけでは医師不足問題は語れません。実は医師数は毎年増え続けているのです。厚生労働省によれば、国内の総医師数は、2008年時点で28.7万人。ここ20年で5割も増えているのです。人口10万人当たり医師数は、20年前は164人で、現在の224人と比べると、36%も増えている計算になります。
1996年の統計で茨城県の人口10万人当たりの医師数は133.7人。東京が260.9人。全国が191.4人です。
一方、2008年は、茨城が166.2人(24.3%増)、東京296.6(13.7%増)、全国224.5(17.3%増)となり、茨城県の医師数はむしろ全国平均よりも、東京都よりも伸び率は高いという統計が出てしまいます。
であるならば、地方の医師不足はなぜ起こっているのか、そこをもう一度冷静に考えてみることが必要です。そこで行き着く結論は、産婦人科や小児科、救急専門の医師など特定の診療科目の医師であると結論づけざるを得ません。
速効性がある医師不足解消策
こうした分析の上に、短期的に不足する医師を茨城県に補充する策は、2つあります。その一つは、県内の唯一医学部「筑波大学」との連携強化。二つ目に、東京近郊に集中する大学の医学部から優先的に医師を派遣してもらいことです。
筑波大学との連携強化では、県の病院事業管理者に筑波大学病院の副院長であった金子道夫氏を迎え、県立中央病院を核とする医師確保と再配分の仕組みを構築しようとしています。
東京の医学部との連携では、いわゆる“寄附講座”を開設し、東京医科大学、東京医科歯科大学など財政的な支援を行い、医師の派遣を行ってもらっています。
こうした医師の数そのものを増やす方法とともに、有効は方策が2つあると考えています。一つは、昨年7月から稼働したドクターヘリなどを活用して、より広域に、より短時間で患者を設備の整った病院に搬送できるシステムを充実させること。
もう一つは、遠隔医療の取組を県をあげて進めることです。遠隔医療には、テレパソロジー(遠隔病理画像診断)、テレラジオロジー(遠隔放射線画像診断)、テレケア(遠隔健康管理)などの3分野があると言われています。




茨城県が率先して日本の遠隔医療を担ってほしいものです。アメリカなどではもはや当たり前になっている遠隔地からの手術や複雑な医療行為を遠隔医療システムを通じて行って地球の裏側にいる患者まで診療することができるようになる日がすぐ来るでしょうね。