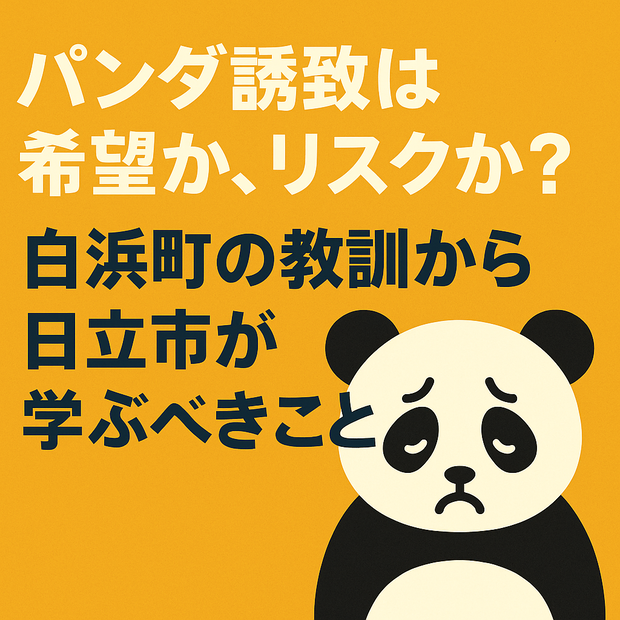
日立市が進めている、かみね動物園へのジャイアントパンダ誘致。大井川県知事のリーダーシップで、県を挙げた熱心な取り組みにより、中国・陝西省との友好覚書が結ばれ、夢の実現が一歩近づいたかのようにも見えます。観光の起爆剤としての期待も高く、地域経済への波及効果は年間50億円規模と試算されており、多くの市民が明るい未来を描いています。
しかし今、和歌山県白浜町で起きている「その後の現実」は、私たちに冷静な判断を求めています。
白浜町は、アドベンチャーワールドにおいて長年にわたりパンダの飼育と繁殖に成功し、「パンダのまち」として国内外から高い注目を集めてきました。ところが、今年(2025年)6月末、飼育されていた4頭すべてのパンダが中国に返還されることが決定。町には大きな動揺が広がっています。町長は「パンダ依存の観光地だった」と率直に語り、その反動の大きさをにじませました。
白浜町の人口は約2万人。観光業が町の経済を支える柱であり、パンダの存在はまさにシンボルでした。令和7年度の町の予算は146億円を計上しているものの、大規模な公共事業も控える中、パンダなき観光施策の再構築は急務です。

ここに、私たち日立市が見過ごしてはならない重要な教訓があります。それは、「パンダ誘致はゴールではなく、始まりに過ぎない」ということです。
パンダは中国からの貸与であり、いずれは返還される運命にあります。多額の整備費用をかけたとしても、その経済効果が恒常的に持続する保証はありません。上野動物園でさえ、パンダのために22億円規模の施設を整備しています。財政規模が限られる日立市が、持続可能なかたちでその維持・運営を担えるのか。市民や観光客の期待に応え続けられる体制を、本当に構築できるのか。疑問は尽きません。
さらに、かみね動物園では令和7年度から月曜休園が導入されるなど、運営方針にも変化が見られ、市民の信頼にも揺らぎが出ています。理念や説明責任が伴わない誘致活動は、のちに“空白”や“失望”を生む可能性すらあるのです。
もちろん、パンダには人を惹きつけ、地域に夢や希望をもたらす力があります。しかしそれはあくまで「手段」であり、「目的」と取り違えてはならないのではないでしょうか。観光の再生、地域の魅力発信、経済の底上げ――それらを支えるのは、日立の自然、文化、そして人々の営みそのものです。
今、私たちは白浜町の現実を“対岸の火事”として見てはいけません。日立市が本当に目指すべき未来を、市民と共に問い直す時が来ています。夢の実現に向けて足元を固め、持続可能で、地域に根ざした魅力あるまちづくりを進めることこそが、パンダ誘致に勝る成果を生むかもしれません。



