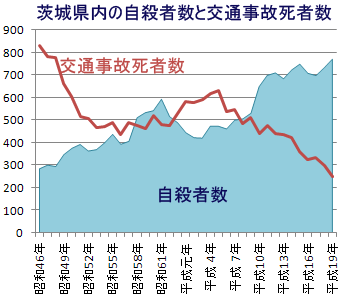 わが国は、年間の自殺者数が13年連続で3万人を超える憂慮すべき事態に陥っています。
わが国は、年間の自殺者数が13年連続で3万人を超える憂慮すべき事態に陥っています。
自殺者数が高止まりを続けている現実と向き合い、希望溢れる社会への転換を急がなければなりませんらない。
昨年1年間で自殺した人の動機に関する警察庁調査によると、うつ病などの健康問題が最多を占め、経済・生活問題のうち「就職失敗」が増加し、仕事や家庭問題も増えています。
自殺は、こうした要因が絡み合って引き起こされます。それだけに、多角的に対策を講じていくことが欠かせません。自殺防止は社会を挙げて取り組むべき課題といえます。
特に、年度末、学年末のこの3月は年間を通じて最も多く自殺者が発生する時期です。今月が「自殺対策強化月間」と定められているのも、このためです。
これから多くの企業が決算期を迎え、年度末の資金繰り対策に頭を悩ませる時期となります。景気停滞や失業率の高止まりなどによって、自殺率が高まる傾向も否定できません。政府は経営基盤の弱い中小企業への資金繰り対策などに真摯に取り組むべきです。
また、3月は人事異動の時期です。環境変化に適応できず、自殺に至るケースもあります。職場での相談体制の導入など、従業員のメンタルヘルス(心の健康)対策が重要となります。事業者に対しても、きめ細かい対応を求めたいと思います。
一方、自殺の動機として最も多いのが心の病ですが、この時期は「木の芽時」と呼ばれ、長い冬からの開放感で張り切る気持ちになるものの、天候が不順で心身に不調をきたしやすいことも事実です。
公明党は、深刻化する自殺者の増加に対応するため、自殺対策における国や自治体、事業者の責務を明記した自殺対策基本法の制定(2006年)をリードしてきました。
また、公明党は自殺との関連が強いうつ病対策について、薬物だけに頼らず、患者自身が持つ否定的な思考を改善する「認知行動療法」の保険適用を昨年4月に実現しました。
しかし、その保険点数が低いことや専門家が少ないため、茨城県内ではまだまだ希望者が気軽に、認知行動療法を受診できる体制には至っていません。
まずは、県立こころの医療センターなどで先導的な診療体制の確立を図っていきたいと考えています。
若年者の自殺の原因に「境界性パーソナリティー障害」
3月3日夜のNHK“クローズアップ現代”で「境界性パーソナリティー障害」が紹介されました。それによると、若い世代の自殺に、境界性パーソナリティー障害という精神疾患が深く関わり、自殺リスクがうつ病より高いと見られることが最新の調査で明らかになってきました。この精神疾患は、身近な人から見捨てられることへの強い不安が特徴。突然激しい怒りをあらわにするなど感情の起伏が大きく、リストカットや過量服薬を繰り返します。患者への接し方が難しいことから診療をためらう医師も多いといわれています。
治療法は、薬物療法と精神療法の併用が基本になります。薬物療法は、抗不安薬、抗うつ薬、抗精神病薬などが使われます。また、精神療法については、精神分析療法、認知行動療法、行動療法などが使われます。カウンセリングが中心になるため、費用や回復までの期間がかかり、専門家も不足していることから、治療体制の整備が急がれます。



