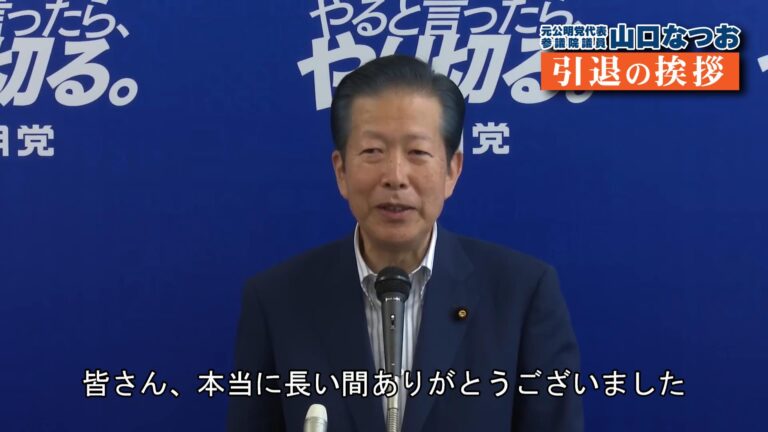3月4日、井手よしひろ県議は県議会代表質問に立ち、橋本知事に県政の諸課題を質問しました。この動画は、その中でも新たな茨城のIT戦略を提案した部分です。
引き続き、「新たなIT戦略について」質問いたします。
私がこの県議会で、“インターネット”という言葉を初めて紹介したのは、今から16年前の1995年でした。その年の夏、茨城県は全国の都道府県に魁けてホームページを開設しました。
以来、茨城県は、積極的にIT戦略に取り組んできました。日本トップレベルの「いばらきブロードバンドネットワーク(IBBN)」の整備や、県全体を網羅した「県域統合型GIS」の運用が開始されました。また、総務省提唱の地域情報プラットフォーム仕様に準拠した「共通基盤システム」を全国に先駆け構築し、汎用機を廃止するなど、システムの最適化とコスト削減にも取り組んできました。
また、茨城県は、昨年6月に「県のブロードバンド・ゼロ地域の解消を達成した取組」が評価され、総務省から表彰されました。こうした中で、この2月9日には、県IT戦略会議が、知事に対して「未来につながる 地域にひろがる スマートいばらき」との提言書を提出しました。
そこで、私はIT戦略会議の提言などを踏まえて、今後のIT戦略に対して3点の提案をさせていただきたいと存じます。第1に自治体クラウドの推進、第2に医療分野でのITの高度利用、第3に住民の孤立化を防ぐツールとしてのIT活用の3点です。
第1の自治体クラウドとは、「クラウドコンピューティング」の技術を自治体で活用することを意味します。英語で「雲」を意味するクラウドは、コンピュータ同士がネットを介してつながった状態を、専門家が雲に見立てたことに由来します。これまでは、システムごとに高額な機器やソフトウェアを一台ずつ整備しなければならなかったものが、クラウドであれば、ネット上のサーバーに、セキュリティの高いシステムを一括して安く、迅速に整備することが出来ます。
こうしたクラウドの長所を生かし、税の徴収や人事、予算、危機管理のシステムなど、自治体業務のあらゆる局面で活用できる、自治体クラウドを整備する必要があります。
一例を挙げれば、口蹄疫で甚大な被害を受けた宮崎県では、殺処分したおよそ29万頭の家畜データの整理に、クラウドが威力を発揮しました。その利用を検討してから10日間でシステムの導入を完了し、ネットにつながるパソコンがあれば、どこでも使え、刻々と変わる情報を職員間でスムーズに共有することができました。
茨城県においても、自治体クラウドを活用し、コストの低減と新サービスの提供を推進する必要があります。県は、市町村のニーズを明確に把握し、どのようなシステムから自治体クラウドの構築をスタートさせるか、早急に見極めるべきだと提案します。
第2には医療分野での活用です。医師の偏在など、茨城県の脆弱な医療基盤を補完するために、ネットを活用した電子画像の伝送、テレビ会議による診療支援・研修会・症例検討会の開催などを行えるIT環境を整備する必要があります。
また、WEBベースの電子カルテシステムの普及を図ることは、地域の医療資源を有効に活用する上で、大きなメリットがあります。さらに将来的には、こうしたシステムが医療支援ロボットなどを活用した遠隔医療の研究にも資すると考えます。
第3の視点は、住民の孤立化を防ぐツールとしてのITの活用です。今年2月、私ども公明党議員会では、厳冬の北海道白老町を現地調査しました。白老町では、総務省の補助金を活用して高齢者用の携帯電話“らくらくホン”を活用した見守り・買い物支援システムの実証試験が続けられています。このサービスは、携帯電話のボタンを押すだけで、独り暮らしの高齢者などが地域の支援ボランティアとの相談や、119番通報を簡単に行うことができます。また、携帯電話のモーションセンサーなどの機能を活用し、安否確認も行うことができます。前にも述べましたが、無縁社会といわれる日本社会の構造変化の中で、こうしたITの活用は、行政の積極的な取組が必要となる分野であります。
また、どうしてもこの機会に指摘しておかなければならないことがあります。それは、こうしたIT戦略上の取組は、かならず県庁それ自体の制度の改革、改善と同時並行でなければならないと言うことです。
お隣の韓国では、海外からも転出届などの手続きをインターネット経由で行うことが出来ます。日本からインターネットで韓国の電子申請ポータルサイトに接続し、国民IDや暗証コードとともに、転出先の住所を入力することにより、一瞬のうちに手続きが完了します。さらに、驚くべきことは、「ほかに運転免許証や年金、医療保険の住所変更など、やるべき手続きが7つあるが、それらを自動で処理して良いか」と、ネット上で尋ねられ、ボタン一つで、各種手続きが同時に処理される仕組みが、すでに韓国では出来上がっています。つまり、韓国における行政事務の電子化とは、単なる事務処理をコンピュータで行うという次元のものではなく、その事務処理自体の改革、改善と一体になっているということです。
こうした改革無くして、茨城県のIT化も、県民にとって真に利益になるものとはなりません。
以上、3つの提案と電子県庁構築の基本的な視点を踏まえて、知事にいばらきの新たなIT戦略の基本的な方向性をお伺いいたします。