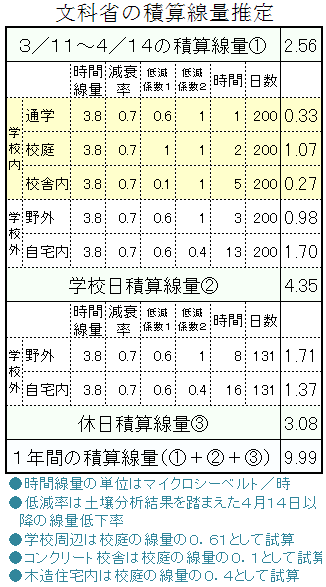 5月27日、文科省の高木義明大臣は記者会見で、「今年度学校において児童生徒等が受ける線量について、当面年間1ミリシーベルト以下を目指すこととして、また校庭等の土壌に関して、児童生徒等の受ける線量を低減する取組みに対して、学校施設の災害復旧事業の枠組みで財政的支援を行うことといたしました」と発表しました。これまで、年間20ミリシーベルトとしていた放射線量の基準を年間20ミリシーベルトから1ミリシーベルトに、実質的に引き下げるという内容であり、児童・生徒を持つおやごさんの不安に応える内容と思われました。
5月27日、文科省の高木義明大臣は記者会見で、「今年度学校において児童生徒等が受ける線量について、当面年間1ミリシーベルト以下を目指すこととして、また校庭等の土壌に関して、児童生徒等の受ける線量を低減する取組みに対して、学校施設の災害復旧事業の枠組みで財政的支援を行うことといたしました」と発表しました。これまで、年間20ミリシーベルトとしていた放射線量の基準を年間20ミリシーベルトから1ミリシーベルトに、実質的に引き下げるという内容であり、児童・生徒を持つおやごさんの不安に応える内容と思われました。
しかし、同じ記者会見の場で同席した鈴木副大臣は、「(財政的支援をする)対象につきましては、土壌に関する線量低減策が効果的ということとなる校庭・園庭の空間線量率が毎時1マイクロシーベルト以上の学校とし、これは6月1日ごろからこの測定を再度全校について行いまして、その結果に従って、この1マイクロシーベルト以上の学校ということを見極めていきたいというふうに思っております」とかたり、今回の時間当たり線量の目安は、「毎時1マイクロシーベルト」ということ明らかにしています。
今までの暫定的な学校利用の放射線量の境界値の計算は、以下のように考えられていました。
(時間当たり線量)×(学校にいる時間:8時間)+(時間当たり線量)×(自宅の木造住宅にいる時間:16時間)×(木造住宅の場合の放射線の低減率:0.4)=(一日当たりの線量)
(一日当たりの線量)×365日=(1年間の線量)
この式に、新たな基準である1マイクロシーベルト/時間を当てはめると、年間の線量は5.256ミリシーベルトに上り、「1ミリシーベルトを目指す」との発言と矛盾することになります。
文科省が示した1ミリシーベトという数字に注目して、鋭い指摘をしたのが公明党の斉藤鉄夫幹事長代行です。5月31日の衆議院東日本大震災復興特別委員会で、「20ミリシーベルトの大枠を変えず、学校生活での被ばく量を1.7ミリシーベルトから1ミリシーベルトにするだけの話であり、20ミリシーベルトが1ミリシーベルトになったと誤解を与える発表だ」と批判しました。その上で「20ミリシーベルトの枠そのものを低い値、1ミリシーベルトにすべきだ」と訴えました。
ここで、斉藤幹事長代行の質問の背景を少し詳しく見てみたいと思います。
5月17日、文科省は「校庭の空間線量率3.8マイクロシーベルト/時の学校の生徒の生活パターンに基づく生徒が受ける積算線量のより現実的な推計について」との資料を公表しています。
これによると、3月11日より1年間の児童生徒が浴びる放射線量を学校開始日(4月14日)以前と、15日以降とに分けて試算しました。
まず、3月11日~4月14日までの34日間の積算線量を2.56ミリシーベルトとしました。
そして、4月15日以降については、学校がある日200日間と休日などの131日間に分けて計算しました。
毎時3.8マイクロシーベルトの線量がある場合、学校がある200日間に関しては1日21.73マイクロシーベルト、休日131日は1日23.53マイクロシーベルトと試算。4月14日までと学校日、休日を全て足して、年間の線量を9.99ミリシーベルトとしています。さらに、学校内での被爆線量は1.67ミリシーベルトとしているのです。
実はこの1.67ミリシーベルトを、文科省は1ミリシーベルトに下げるといっているに過ぎません。学校外の被曝については、全くその責任放棄した数字だったのです。




茨城県には多くの川や用水路があります
小さな川や農業用水路を利用したマイクロ水力発電も最近は可能だと思います
風力発電だけではなくマイクロ水力発電も検討してほしいです
また水力発電が水車小屋風のもあるとか
これってかっこいいと思います