 6月25日、東日本大震災の被災地の復興ビジョンを検討していた政府の復興構想会議の提言がまとまり、菅直人首相に提出されました。
6月25日、東日本大震災の被災地の復興ビジョンを検討していた政府の復興構想会議の提言がまとまり、菅直人首相に提出されました。
提言の冒頭には、復興構想の原則として、以下の7項目が掲げられています。
- 失われたおびただしい「いのち」への追悼と鎮魂こそ、私たち生き残った者にとって復興の起点である。この観点から、鎮魂の森やモニュメントを含め、大震災の記録を永遠に残し、広く学術関係者により科学的に分析し、その教訓を次世代に伝承し、国内外に発信する。
- 被災地の広域性・多様性を踏まえつつ、地域・コミュニティ主体の復興を基本とする。国は、復興の全体方針と制度設計によってそれを支える。
- 被災した東北の再生のため、潜在力を活かし、技術革新を伴う復旧・復興を目指す。この地に、来たるべき時代をリードする経済社会の可能性を追求する。
- 地域社会の強い絆を守りつつ、災害に強い安全・安心のまち、自然エネルギー活用型地域の建設を進める。
- 被災地域の復興なくして日本経済の再生はない。日本経済の再生なくして被災地域の真の復興はない。この認識に立ち、大震災からの復興と日本再生の同時進行を目指す。
- 原発事故の早期収束を求めつつ、原発被災地への支援と復興にはより一層のきめ細やかな配慮をつくす。
- 今を生きる私たち全てがこの大災害を自らのことと受け止め、国民全体の連帯と分かち合いによって復興を推進するものとする。
さてこの提言を読んで、現に塗炭の苦しみを被っている被災者はどのような感想を持つでしょうか。
一読すると、美辞麗句で色づけされた名文に感心させられます。しかし、復興への具体的な道のりは、なにも見えてこないのが残念です。
前文には、「今回の震災における被災者には、果たして何色が印象づけられたであろうか。それはあるいは海岸からおし寄せた濁流うずまくどすぐろい色かもしれぬ。いやそれは津波が引いた後のまちをおおいつくす瓦礫の色かもしれぬ。パニックに陥ることなく黙々とコトに処する被災した人々の姿からは、色味はどうであれ、深い悲しみの色がにじみ出ていた。その彼等のよき振舞いを、国際社会は驚きと賛美の声をもって受けとめた。そして国際社会からの積極的支援を促すこととなった。そこへ、色も臭いもなく、それが故に捉えどころのない原発被害が生ずる。国内外に広がる風評被害を含めて、今回の災害は、複合災害の様相を呈するのだ。したがって復興への道筋もまた単純ではなく、総合問題を解くに等しい難解さを有する。複合災害をテーマとする総合問題をどう解くのか。この「提言」は、にこれに対する解法を示すことにある。被災地の人たちは、「つなぐ」行為を重ねあうことによって、まずは人と自然の「共生」をはかりながらも、「減災」を進めていく。次いで自らの地域コミュニティと地域産業の再生をはたす。「希望」はそこから生じ、やがて「希望」を生き抜くことが復興の証しとなるのだ」と、記載されています。
提言の方向性に異を唱える人は少数派に止まるでしょう。反面それは、具体的な復興の姿を示さぬ『逃げの姿勢』が提言全体に流れているからです。
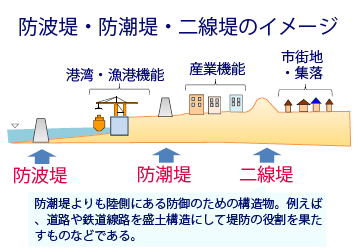 「復興に際しては、地域のニーズを優先すべきである」と、地域の重要性を強調する。しかし、これは国責任逃れではないでしょうか。東北の各地を視察してみて、「地域地域に零細漁業者や加工業者などが点在する地域性の中で、すべての漁港や漁業関連施設を復興させることが財源的に可能なのか、東北の再生のためにそれが得策なのか」との、疑問の声を多く伺いました。復興格差という大きな問題に、国が主体的に動くという決意が感じられません。
「復興に際しては、地域のニーズを優先すべきである」と、地域の重要性を強調する。しかし、これは国責任逃れではないでしょうか。東北の各地を視察してみて、「地域地域に零細漁業者や加工業者などが点在する地域性の中で、すべての漁港や漁業関連施設を復興させることが財源的に可能なのか、東北の再生のためにそれが得策なのか」との、疑問の声を多く伺いました。復興格差という大きな問題に、国が主体的に動くという決意が感じられません。
「今回の復興にあたっては、様々な土地利用計画制度の調整が必要となる。しかし、調整に時間を要すれば、地域の復興が遅れる懸念がある。そこで、復興事業を円滑かつ迅速に進めるためには、復興計画の実施に必要な都市計画法、農業振興地域整備法、森林法等に係る手続きを市町村
中心に行われるよう一本化し、土地利用の再編等をすみやかに実現できるような仕組みが構築されねばならない」。こんなことは、わざわざ提言を受けなくても分かっていることです。その調整をどのように行うかを提言する“場”が復興構想会議であったはずです。
「医療サービスについては、特に被災市町村が医師等の不足している地域である点を考慮し、医療機能の集約や連携が行われるべきである」。そもそも、深刻医師不足に陥っている地方の医療の現状からみると、何ら提言の形をなしていません。東北にどのように医師を派遣するか、看護師を供給するか、その姿が示されなければ、何の実効性もないのです。
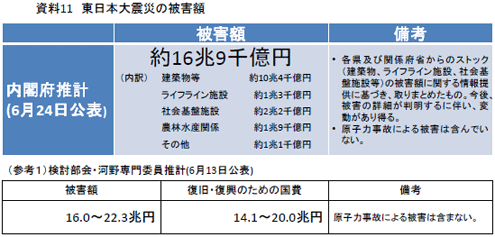
反面、財源に対する記述は、妙に具体的です。「復旧・復興のための財源については、次の世代に負担を先送りすることなく、今を生きる世代全体で連帯し、負担の分かち合いにより確保しなければならない。政府は、復興支援策の具体化にあわせて、既存歳出の見直しなどとともに、国・地方の復興需要が高まる間の臨時増税措置として、基幹税を中心に多角的な検討をすみやかに行い、具体的な措置を講ずるべきである。この点は、先行する需要を賄う一時的なつなぎとして「復興債」を発行する場合には、日本国債に対する市場の信認を維持する観点から、特に重要である」。マスコミ各社が、この復興構想が以下に財務省主導で行われたかを示す証拠でもあると論評しています。
復興構想会議の提言でスッポリ抜けてしまった点をいくつか指摘しておきたいと思います。
その第一は、「忘れられた被災地」というわれる茨城県の復興計画の方向性です。総額2兆5000億円と言われる第4の被災額。農業や漁業の被害は深刻です。数千戸を超える液状化被害の住宅など、茨城県の位置づけは、当初から復興会議の議論からは除外されていました。茨城県には復興特区は適用されるのか、そんな基本的なことも示されていません。怒りにも似た感想を持っています。
その第二は、“震災復興基金”の考え方が全く示されていないということです。民地の二次被害への対応、液状化被害への支援、鉄道などの公共性が高い民間施設の復旧などには、震災復興基金の創設が不可欠です。提言で言う国の交付金だけは、乗り越えられない課題が山積みです。復興基金の一言も出てこない提言に、強い違和感を感じています。
第三には、復興のための基盤整備が抜けているように思われます。三陸道の全面開通、復興道路としての国道45号線の機能強化、鉄道の早期普及など、津波被害を受けた沿岸部を縦貫する交通網の整備は絶対に必要と実感しています。こうした圏域を超えた、基盤整備に国は主体的に動くことが必要で、その基本構想が盛り込まれていないのは大いに不満です。
 参考:東日本大震災復興構想会議
参考:東日本大震災復興構想会議



