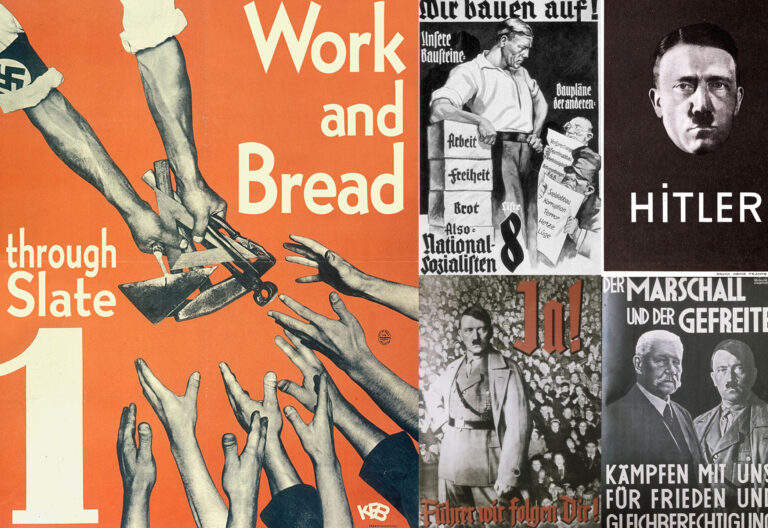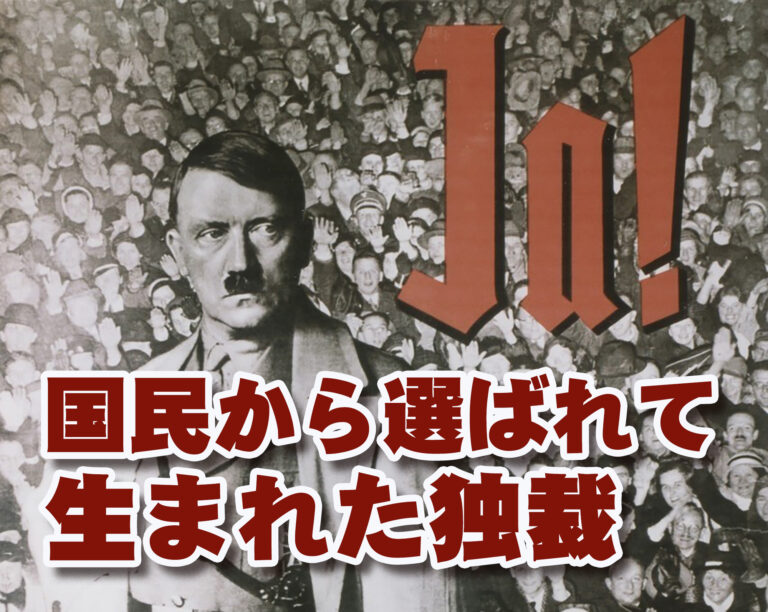11月5日、井手よしひろ県議は取手市内で開催した県政懇談会で、参加者からの質問に答え、「TPP交渉参加は日本の国益に反し、交渉参加には反対する」との見解を、重ねて明らかにしました。
11月5日、井手よしひろ県議は取手市内で開催した県政懇談会で、参加者からの質問に答え、「TPP交渉参加は日本の国益に反し、交渉参加には反対する」との見解を、重ねて明らかにしました。
環太平洋経済連携協定(TPP)交渉参加について、野田総理は前の臨時国会の所信表明の中で「しっかりと議論し、できるだけ早期に結論を」と語り、今回の所信表明では「引き続き、しっかりと議論し、できるだけ早期に結論を」と、全く同じ事を繰り返しました。一体50日もの間「何をやっていたのか!」と、情けなさを通り越して、怒りすら覚えます。
一方で、先月29日には、「野田首相、TPP交渉参加の意向固める」という報道が流れました。さらにG20では、「党で議論をどこかで終結していただき、最終的に政府・民主三役会議で決定することになると思うが、いずれにしても私の政治判断が必要になると思う」とも語り、首相の独断専行でTPP参加を決めることも示唆しました。
これは国民への裏切りに他なりません。議論もなければ、情報開示もない、何より拙速過ぎます。国民が不安を強くするのは致し方ないことです。
TPPが日本が生き残る道だと野田総理など推進派の人たちは言います。しかし、本当にそうなのでしょうか?
例えば、TPP参加交渉で公的医療保険は、議論の対象になっていないと政府は説明していますが、アメリカが民間保険や医薬品のあり方などで日本に門戸開放を求める可能性は十分あります。その国民の心配に、どう対応するかという政府の基本姿勢をもっと説明するべきです。国際ルールによって、日本が世界に誇る“国民皆保険”制度に箍がはめられるような事態になっては、本末転倒です。
TPPを米国と日本の実質的な貿易ルールだと考えると、TPPだけが選択肢なのかどうかも考えないといけません。
また、アジアを含めた国際社会の中で、日本がどういう戦略で貿易ルールを整えていくのか。その大きな戦略の中でTPPがどんな位置付けを果たすのか、もっと説明しなくては、国民は納得できません。
日本がアメリカ中心のTPPに組み入れられることによって、TPP協定から排除された国のリアクションも考慮する必要があります。TPPは実質的に中国を経済的に排斥するものです。経済的な側面で中国敵視政策に加担するのは、きわめて危険な判断です。
さらに、ロシアも、インドも、ブラジルも、南アフリカも、このTPP協定に枠外にあることを知らなければなりません。いつまでもアメリカ追従をしていて良いわけがありません。
TPPに参加しているニュージーランドのオークランド大学のジェーン・ケルシー教授は、今年7月12日、仙台で公演しました。その中で、TPP研究の第一人者であるケルシー教授は、TPPに参加するためには以下のような事項を承認することが求められると述べています。
*文書は協定に署名するまで全て非公開とする
*協定は脱退しない限り永続する
*規則や義務の変更はアメリカ議会の承認が必要
*投資家は政策的助言に参加し、規則を受ければ投資家が加盟政府を控訴することが出来る。
つまり、独立国の関税自主権を放棄させ、国家主権よりも協定が優越するというTPP。他の加盟国はアメリカの植民地とか従属国に、結果的に成り下がることになる。こうした危険性を充分に認識すべきです。
(写真は、朝霧の中の稲のおだ掛けの様子。こうした伝統的な米作りはTPP協定とともに無くなってしまうかもしれません。岩手県遠野市で撮影)
 参考:ジェーン・ケルシー教授講演会
参考:ジェーン・ケルシー教授講演会