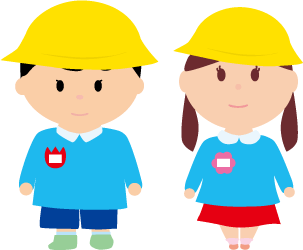 民主党野田政権が掲げる目玉政策の一つとして小宮山厚生労働大臣イチオシの「総合こども園」の創設に、赤信号が灯り始めました。
民主党野田政権が掲げる目玉政策の一つとして小宮山厚生労働大臣イチオシの「総合こども園」の創設に、赤信号が灯り始めました。
政府は、社会保障と税の一体改革のうち子育て支援策について、待機児童を解消するため、幼稚園と保育所の機能を一体化させた施設「総合こども園」を創設することなどを法案に盛り込んでいます。しかし、公明党は現場の目線から、待機児童の解消につながらないとして、現在ある「認定こども園」を増やすなど、現行制度を基に改善を図るべきだと主張しています。
 これについて小宮山厚生労働大臣は、「『総合こども園』の創設で盛り込みたかったのは、就学前の必要なすべての子どもに質のよい学校教育、保育をするということや、待機児童にしっかり対応することなど3つの大きな柱で、理念は一切曲げていない」と述べました。そのうえで小宮山大臣は、「子育て支援をしっかりやり、財源を確保しようという方向性は各党で一致している。法律の形式や仕組みについては譲り合って、修正協議がまとまり、今の国会で法案が成立するよう全力を挙げていきたい」と述べ、待機児童対策など、政府案の理念が確保されるのであれば、「総合こども園」の創設には必ずしもこだわらないという考えを示しました。(小宮山厚労相のコメントはNHKのニュースより引用)
これについて小宮山厚生労働大臣は、「『総合こども園』の創設で盛り込みたかったのは、就学前の必要なすべての子どもに質のよい学校教育、保育をするということや、待機児童にしっかり対応することなど3つの大きな柱で、理念は一切曲げていない」と述べました。そのうえで小宮山大臣は、「子育て支援をしっかりやり、財源を確保しようという方向性は各党で一致している。法律の形式や仕組みについては譲り合って、修正協議がまとまり、今の国会で法案が成立するよう全力を挙げていきたい」と述べ、待機児童対策など、政府案の理念が確保されるのであれば、「総合こども園」の創設には必ずしもこだわらないという考えを示しました。(小宮山厚労相のコメントはNHKのニュースより引用)
自公政権が進めた認定こども園に変わって、民主党政権は総合こども園の法案を提出しています。これは、幼稚園と保育所を一体化した施設を増やしていこうというものです。
現在、小学校入学前の子どもを受け入れる施設は、都市部では待機児童が多く、保育園に入れないという課題がある一方で、地方では、子どもが減って、幼稚園が定員割れてしているという現実があります。
このミスマッチに対して、現行制度では、幼稚園と保育園、そしてその両者の機能を兼ね備える認定こども園という態勢で対応しようとしています。
幼稚園は、3歳以上の子どもたちが、一日4時間通園する施設です。文部科学省が所管し、学校教育を意識した活動が多い傾向があります。
一方、保育所は、共働きなどの家庭の0歳からの子どもたちが、朝から夕方・夜まで過ごす施設。親が仕事などで日中子どもの世話が出来ない、つまり保育に欠けることが入所の条件。以前は、家庭に代わって子どもを育てる養育の傾向が強くありました。所管は厚生労働省です。幼稚園で子供たちを教える人を「幼稚園の先生」と一般的に呼びますが、保育園で「保母さん」と呼ぶのもこうした背景があります。
自公政権下、この両方の機能をもった施設として、幼稚園と保育所の子どもを一緒に預かる「認定こども園」という施設ができました。
文科省、厚労省、内閣府にまたがる子育て支援体制?
民主党政権では、この認定こども園をバージョンアップさせて、今ある幼稚園と保育所を、認定こども園のような「総合こども園」に移行させていこうという構想をぶちあげました。
民主党案では、*今の認可保育所のように、0~5歳の子どもが通う総合こども園、*3~5歳の幼稚園児と保育園児が通う総合こども園、0~2歳の保育所、3~5歳の幼稚園と、大きく4つに分けるとしています。
さらに、総合こども園の所管は、文科省でも厚労相でもなく、内閣府にするといっています。まさに支離滅裂な案です。
民主党は「子ども家庭省」という役所をつくって、子どもの施設も担当の役所もひとつにまとめると言っていましたが、党内調整や霞が関の官僚との調整がまとまらず、いわば暫定的な形で内閣府が担当することになってしまいました。
市町村の保育実施義務がなくなる?
また、民主党案では、これまで市町村に課せられていた保育の実施義務がなくなります。「これまでは市町村が保育所を施設を探してくれていたが、これからは保護者がいくつもの施設を回らなければならず、時間に余裕のない保護者には大きな負担となる」「障がいなどで特別な支援が必要な子どもの施設も保護者が自力で探さなければならなくなる上、こども園側は手のかかる子どもの入所を拒否するのではないか」などという切実な声です。
施設が不足する場合は、市町村が斡旋するとしているが、施設が足りず、斡旋されない場合、そもそも市町村には責任がなくなってしまいますから、積極的に施設を確保したり、人員を充実させたり、誰が中心的に進めていくのか、責任の所在が全くわからない制度設計になっています。
一方、学校として位置付けられる総合こども園への株式会社の参入を認めたことにも、大いに問題です。安易な事業撤退や、営利主義による人件費の圧迫が起こらないと言えるのか疑問が残ります。
こうした中途半端な総合こども園の案を早々と撤回することは、結果的に良いことだと思います。
現行制度で、待機児童を無くす政策の強化を
まず、現行制度の中で都市部の待機児童を減らす対策に全力を上げるべきです。
その上で、時間をかけて議論を煮詰めて「子どものためになる一本化を」目指すべきだと思います。
共働き世帯の増加や、急速な少子化を考えれば、幼稚園の経営が成り立たなくなるのは時間の問題で、いずれ幼稚園と保育所を一つにする必要があります。幼稚園・保育所の先生たち、それに親も、互いの慣習や考え方の違いを乗り越えて、どうしたら、幼稚園と保育所の良さを生かせる、本当の意味での「一本化」ができるのか、時間をかけて考える必要があります。現場の意識改革が何よりも重要だと考えます。



