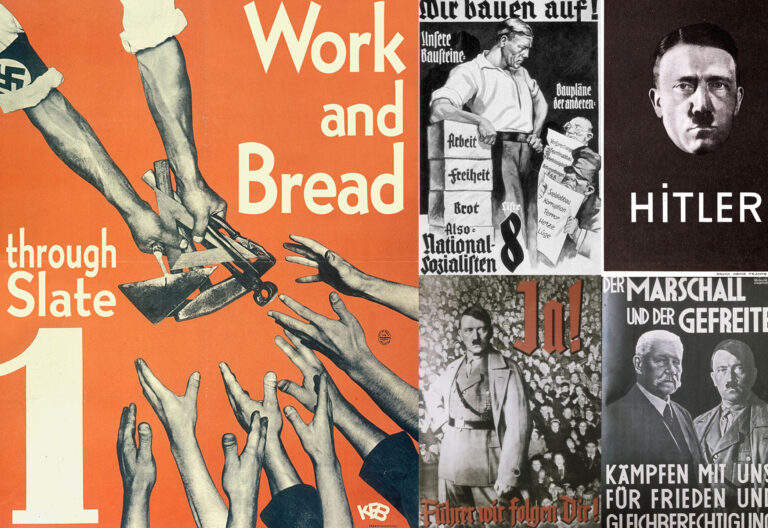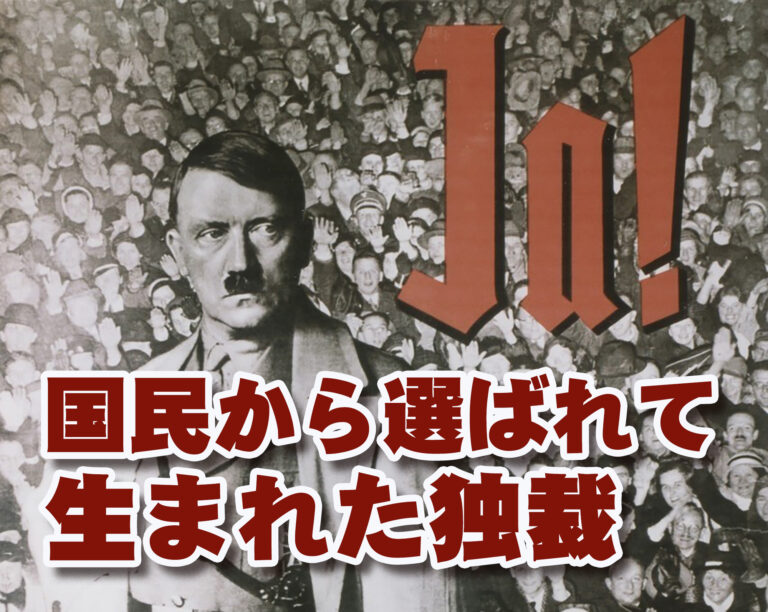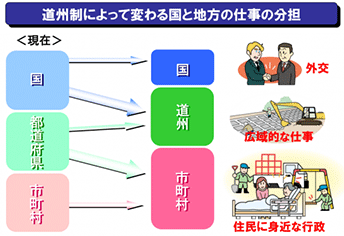 現在の都道府県制度を廃止して、複数の都道府県を統合し、広域的な行政体を作る「道州制」への議論が活発化しています。
現在の都道府県制度を廃止して、複数の都道府県を統合し、広域的な行政体を作る「道州制」への議論が活発化しています。
茨城の県議会議員として、県内をつぶさに歩き回ってみると、県際地域の活性化が大きな課題となっていることに気づきます。常磐線やTXで千葉、東京と直結した県南地域。埼玉、埼玉、栃木と県境を接する古河市を中心とする県西地域など、茨城県という狭い枠組みで考えるより、茨城・千葉・埼玉・栃木という広域的な対応が求められていると実感します。
また、医療のしくみを考える時も、ドクターヘリの広域運用や陽子治療など高度先進医療等を効率よく整備するためにも、県境を越えた発想が不可欠になっています。
さらに、茨城空港や茨城港などの利用を促進させるためにも、茨城県単独で取り組むより、より広域にその活用を考えたほうが効率で効果的である事は明らかです。
言うまでもなく、現在の47都道府県の区割りは、100年以上前の明治時代の状況を反映させたものです。 しかし、現在は高度に交通・通信網が発達し、防災、観光、産業、医療など、県の枠を越えた広域政策が必要とされている時代です。この広域行政の要請が道州制導入の第1の理由です。
第2の理由は日本を真に「地方分権国家」に導くためです。中央集権型の全国一律の公共サービスは既に行き渡っています。結果的に権力が集中する東京の一極集中が進み、東京だけが肥大化してしまいました。
そのディメリットは、今後必ず起こるであろう大規模震災への対応など、危機管理の面で最も顕著になっています。
東京一極集中という弊害を排除し、それぞれの地域が持つ特性を生かし、独自の政策で多様性に富んだ地域ができるよう地方主権国家を目指すベきなのです。
道州制を目指す第3の理由は、日本の財政再建を図るためです。
今年度末の国債と地方債の発行残高は、1000兆円を突破することが想定されています。財政の無駄を省くためには、公務員の人件費を削減することが最も効果的です。公務員の規模では、国家公務員より圧倒的に地方公務員の数が多くなっています。ここに手を入れなくては、行財政改革は実現できません。
都道府県を再編成して、その地方公務員の仕事そのものを見直しを図らない限り、人員の抜本的削減はできません。ある専門家の指摘によれば、道州制への移行で、都道府県の職員は3割削減できると言われています。
また、当然都道府県の知事などの特別職や議員の数も大幅に削減できることになります。
道州制に移行し、国の多くの業務を道州に移行することができれば、国は国防や外交、年金などその役割を特化し、結果的に“小さな政府”を作ることが可能になると期待します。
一方、道州制のディメリットとして指摘されるのが、地域住民の声が行政に届きづらくなるということです。しかしながら、よく考えてみると現在の都道府県は、市町村と国との中二階的な存在で、住民の声をしっかりと受け止めているかどうかは甚だ疑問です。住民に近い事は市町村が行い、道州はこれまで国がやってきた産業、農林水産省、国土保全や厚生労働などの政策を行うようになれば、むしろ現在より、住民との距離は近くなるはずです。
地域の活性化、より充実した行政サービスを実現します。そのために、これまでの中央集権的な日本の統治機構のあり方を一新。「国―道州―基礎自治体」の三層構造へと改革する道州制の導入を推進します。
国の権限を広く移譲する分権改革によって、効率的で国際社会の変化に戦略的に対応できる行政を推進します。さらに、国家公務員および国会議員の大幅削減など大胆な行政改革・国会改革につなげます。 その第一歩として、早期に「道州制基本法」(仮称)を制定。内閣に道州制推進本部を設置します。
2.「道州制国民会議」で、幅広い意見を集約
国民的議論を経た道州制移行を推進するため、道州制推進本部長(内閣総理大臣)の諮問機関となる「道州制国民会議」を設置します。約3年かけて幅広い議論を集約した上で、その後2年をめどに移行に向けた必要な法的措置を講じます。