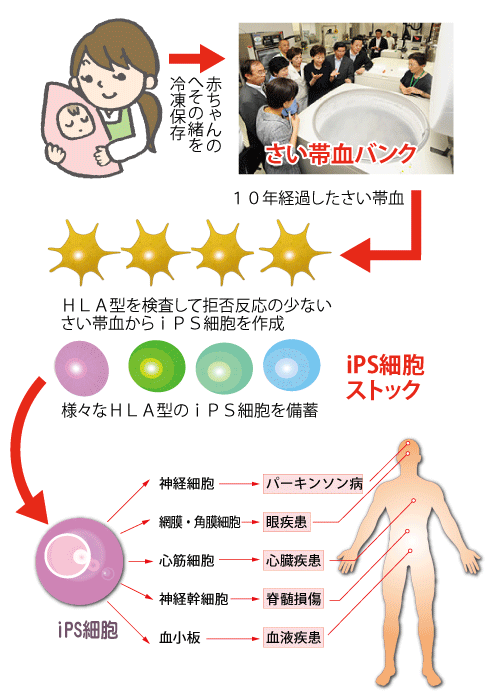8月6日、NPO法人「兵庫さい帯血バンク」は、兵庫県庁で記者会見し、ノーベル賞を受賞した山中伸弥教授が所長を務める京都大学iPS細胞研究所から依頼を受けていた、iPS細胞(人工多能性幹細胞)ストック事業へのさい帯血の提供を承認したことを明らかにしました。
8月6日、NPO法人「兵庫さい帯血バンク」は、兵庫県庁で記者会見し、ノーベル賞を受賞した山中伸弥教授が所長を務める京都大学iPS細胞研究所から依頼を受けていた、iPS細胞(人工多能性幹細胞)ストック事業へのさい帯血の提供を承認したことを明らかにしました。
臍帯血は胎盤やへその緒にあり、赤血球などを作る造血幹細胞を含んでいます。出産時に採取され、白血病治療などに活用されています。全国8カ所に臍帯血を不特定多数の患者に提供する公的なバンク(さい帯血バンク)があります。
再生医療で移植を受ける患者自身の細胞からiPS細胞を作ると時間や費用が嵩むという欠点があります。そこで、事前に他人の細胞からiPS細胞を作製して備蓄し、治療に役立てるのがiPS細胞ストック事業です。他人から作るため、移植される患者が拒絶反応を起こすリスクがあります。
このため、拒絶反応を起こしにくい白血球の型の人のiPS細胞を集めることが重要です。京大iPS研究所によると、特定の75種類の細胞を集めれば、日本人の約8割をカバーできることから、全国の臍帯血バンクに協力を求めていました。
兵庫さい帯血バンクは、採取後10年経過しても使われなかった臍帯血を対象に、母親と子どもの同意を得て提供する方針です。10年経過後の臍帯血の中に、拒絶反応が起きにくい白血球の型を複数確認しています。今後は母子に書面を郵送するなどして同意が得られれば、京大iPS研究所に提供します。
再生医療、さい帯血保管に、公明党がリード役務める
公明党は2012年9月、さい帯血を研究目的に利用できる規定を盛り込んだ「造血幹細胞移植推進法」の成立を推進しました。今年4月にはiPS細胞等の実用化を進める「再生医療推進法」も実現させました。昨年11月1日、山中教授はノーベル賞受賞後の公明党国会議員への講演の席上、このiPSストック事業の重要性を強調しました。
 参考:再生医療用iPS細胞ストックとは?
参考:再生医療用iPS細胞ストックとは?