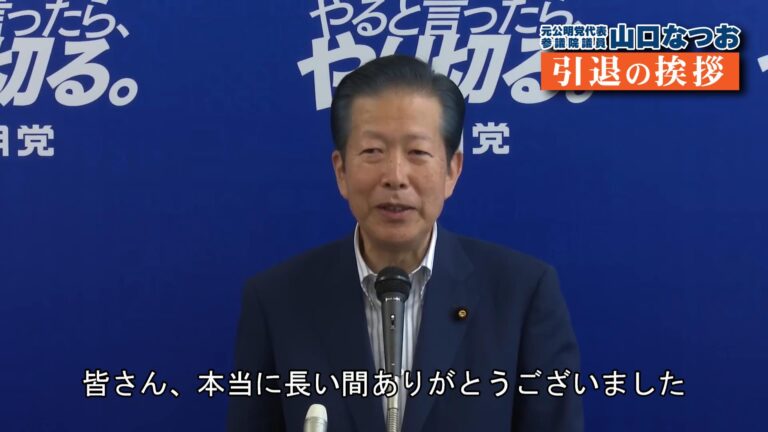3月3日、井手よしひろ県議は公明党を代表して、橋本昌知事に代表質問を行いました。
この動画は、「大規模災害に対するレジリエンス強化について」について質問した箇所です。
「地域・県民の防災力の向上」「防災情報ネットワークシステムの再整備」「被災者生活再建支援制度の拡充」 「農家の大雪被害への支援」の4つの視点から、橋本知事の答弁を求めました。
(1)地域・県民の防災力の向上
公明党の井手義弘です。会派を代表して、橋本知事にお伺いいたします。
東日本大震災の発生から3年目を迎えようとしています。東日本大震災は、死者1万8703人、行方不明2674人、負傷者6220人というと甚大な被害をもたらしました。更に未だに避難生活を余儀なくされている方が27万人、震災関連死は2916人にのぼっています。茨城県内では死者24人、行方不明1人、関連死41人となっており、東日本大震災は日本の経済、社会にとって大きな影響を与えています。
また、つくば市内で発生した竜巻や伊豆大島の土石流など、災害や異常気象による被害が深刻化しています。
こうした自然の脅威に「いかに備えるか」「危機に直面した時にどう対応し、どう回復を図るのか」との観点に基づいた取り組みが急務であり、社会の「レジリエンス」を高める必要性が叫ばれるようになってきました。
レジリエンスとは、元来、物理学の分野で、外から力を加えられた物質が元の状態に戻ろうとする“弾性”を表す用語です。その働きを敷衍(ふえん)する形で、環境破壊や経済危機のような深刻な外的ショックに対して “社会を回復する力” の意味合いでも用いられるようになりました。
災害の分野においては、防災や減災のように「抵抗力」を強め、被害の拡大を抑えていく努力と併せて、甚大な被害に見舞われた場合でも、困難な状況を一つ一つ乗り越えながら、復興に向けて進む「回復力」を高めることを重視する考え方と言えます。
「強力な社会的レジリエンスの存在するところには、必ず力強いコミュニティが存在する」と、識者が指摘するように人的側面への注目が非常に重要です。地域に住む人々のつながりや人間関係のネットワークなどのような、ソーシャル・キャピタルを日頃からどう育むかという点が、重要な鍵を握っています。その意味では地域の住民の協力による自主防災組織の充実や地域コミュニティの再生が大きな課題となっています。
釜石の奇跡で有名になった群馬大学の片田敏孝教授は、茨城県砂防協会での講演で、防災に関する過度な行政への依存を否定して、「内発的な自助」の重要性を語っています。内発的自助とは、「親として家族を守りたい、地域の若者としてみんなで安全を守り抜きたい、そのような内なるものとして沸々と湧いてくる自助のことです」と片田先生は説明しています。
また、最近「アメリカ式の防災教育」が、さまざまな地域で注目を浴びています。
現在、日本の学校教育で行われている避難訓練は、集団で行動し避難することを目的として行われています。しかし、子供が家に独りでいる時に火災に遭遇した場合、果たして速やかに避難行動を取ることが出来るのでしょうか。そこで着目したのが、アメリカ式の防災教育です。「Stop Drop and Roll」自分の体に火が燃え移ったら、その場で止まって、倒れて、転がれという意味です。まさに、アメリカ式の防災教育は個人の防災力を高めようというプログラムに他なりません。
こうした事例をもとに、大規模災害へのレジリエンスを強固にするため、地域の防災力の強化や子どもたちへの教育、訓練、さらには県民一人一人の防災意識の高揚などの課題にどの様の取り組まれようとしているのか、知事におたずねいたします。
(2)防災情報ネットワークシステムの再整備
次に、防災情報ネットワークシステムの再整備に関して質問します。
現行の防災情報ネットワークは平成9年から10年に整備され、稼働後14年が経過しています。東日本大震災では、自治体間や消防本部などとの情報伝達に一定の効果を発揮しました。
しかし、課題も多く残されました。現行システムはアナログ回線で運用されていますので、文字データのやり取りや画像のやり取りに対応していませんでした。また、システムを稼働させる電力の供給が長時間止まったために、非常用電源の確保が出来なかったところもありました。
震災の影響で市町村や消防本部の建物自体が壊れたり、衛星回線のパラボラアンテナが損傷したりして、ネットワークが確立できない場所もありました。庁舎自体が大規模なダメージを受けた場合の可搬式のシステムも不可欠であることが判りました。
私は震災の当日、一昼夜にわたり、県の災害対策本部でその対応状況を見ておりました。ガソリンなどの燃料事業者、トラック・バスなどの運輸事業者、NEXCO東日本、県医師会などとは回線が繋がっていなかったため、情報の収集や共有に問題があったと実感しています。
こうした総括を踏まえ、新たな防災情報ネットワークを、どのように構築されようとしているのか、知事にお伺いいたします。
(3)被災者生活再建支援制度の拡充
次に、「被災者生活再建支援制度」の拡充についてお伺います。
この制度は、被災者生活再建支援法に基づき、自然災害により住宅が全壊するなどの被災世帯に対して「支援金」を支給する制度です。東日本大震災でも県内で約9400世帯の方々が、この制度を活用し生活再建の一助とされています。
しかし、この支援法の適用は、10世帯以上の全壊被害が発生した市町村などを対象としているため、竜巻など局所的に被害が集中する災害には適用できない場合があります。
こうした状況から、国への制度改正の働きかけを強めるとともに、県独自の制度創設を検討すべきだと思いますが、知事のご所見をお聞かせください。
(4)農家の大雪被害への支援
2月8日、9日および14日、15日と2週続けての大雪と暴風により、県内の農家は大変な被害を蒙りました。
さる、2月27日、県議会農林水産委員会でも被災農家を現地調査し、様々なご意見を伺ってきたところです。
今回の大規模被害に関して、国は被災農家への支援として、災害関連資金の無利子化や農業用ハウス等の再建・修繕への助成を行うと発表しています。特に、壊れた施設の解体撤去の費用も含めて、再建に10分の3の助成を行う制度は、農家の経営再建におおきな後押しとなると思います。しかし、この助成も自己資金で解体、再建などを行う農家は対象になりません。主に融資を受けることが前提の制度です。高齢化した農家にとって、跡継ぎに借金を残すことはできない、こうした悲痛な声が聞こえてきます。
そこで、今回の大雪に関わる県内農家の被害状況と、その経営再建支援について、知事のご所見をお伺いいたします。