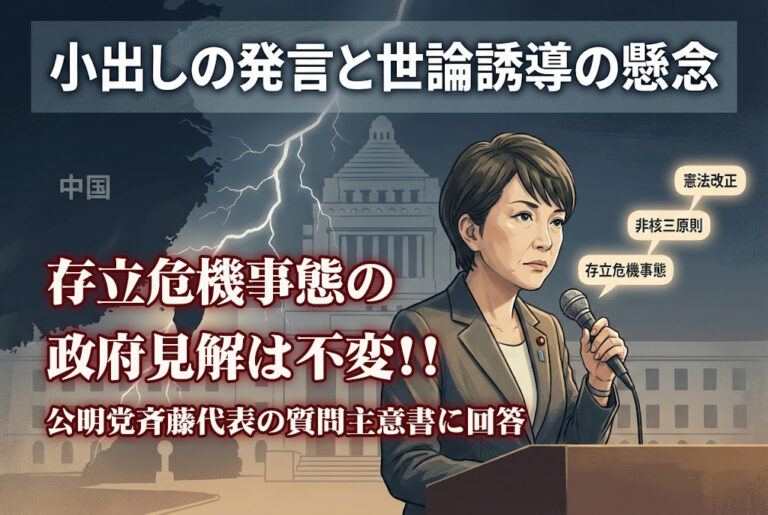3月17日、公明党の山口那津男代表は、東日本大震災で被災した茨城県鹿嶋市の新日鉄住金株式会社・鹿島製鉄所と、茨城県潮来市の「日の出地区」を訪れ、復旧状況を調査しました。
石井啓一政務調査会長(党茨城県本部代表)、斉藤鉄夫幹事長代行、伊佐進一衆院議員のほか、地元の県議、市議らが同行しました。
鹿島製鉄所で一行は、震災の大津波によってなぎ倒されていた製品の出荷時に使用する大型岸壁クレーンの現在の姿などを視察しました。また、第1高炉や第2製鋼製鋼工場、第2薄板工場なども視察しました。
新日鉄住金の栁川欽也常務取締役は、鹿嶋市が3・11発災時に震度6弱、その約30分後に震度5強と、二度にわたって大きな揺れに襲われたと説明。「幸運にも製鉄所で人的被害はなかったが、コークス(石炭を高温で蒸し焼きにした燃料)工場の爆発や水、ガスの遮断によって製造停止に陥った」と述べました。
鹿島製鉄所は、大型高炉2基を擁し年間粗鋼生産能力830万トン、自動車用に多く使われる薄板を中心に製造しています。
東日本大震災では、ここにも大きなつめ跡を残しました。Cガスホルダーというガスタンク2つが爆発し崩壊。地震には耐えた番ぺきの大型クレーンは、津波で漂流した原料船がぶつかり、5台が倒壊してしまいました。荷揚げ作業をしていたアンローダーも原料船が流されたことで引きちぎられ、製鉄所にあった3機とも破損してしまいました。
また、コークス炉の原炭槽の下部が挫屈、コークスガス配管も落下し破損、岸壁は液状化により高低差が生じるなど大きな被害を受けました。地震発生時に原料を高炉に投入するベルトコンベアも折れ曲がって使えなくなりました。
 しかし、被災わずか1週間後の3月18日には、震災復興に必要な素材であるプレハブ住宅用の溶接軽量H形鋼の生産を再開しました。20日と26日には2つの高炉で順次送風を再開。さらに、29日のコークス炉再稼働。4月3日には製鋼工場が動き粗鋼生産が再開しました。
しかし、被災わずか1週間後の3月18日には、震災復興に必要な素材であるプレハブ住宅用の溶接軽量H形鋼の生産を再開しました。20日と26日には2つの高炉で順次送風を再開。さらに、29日のコークス炉再稼働。4月3日には製鋼工場が動き粗鋼生産が再開しました。
所内の火力発電所(IPP)の操業再開も急ぎました。地盤沈下でコンベアが壊れましたが、3月26日には100%稼働、47.5万キロワットすべてを東京電力に供給しました。被災した火力発電所の中では、もっとも早い再稼働でした。
また、高炉ガスなど副生ガスを使って発電する東電との合弁会社である鹿島共同火力は1~4号機、各35万キロワットの能力を持っています。いずれも電力需要が逼迫した夏までには再稼働を果たしました。
これだけの被害に見舞われながらも、その復旧の早さには世界から驚嘆の声が寄せられました。復旧に要した費用は1000億円に達すると言われています。
栁川常務は、約3カ月後に製鉄所が早期に操業を再開できたことに関して、「日ごろからの危機管理の徹底や、ベテラン作業員の機転を利かせた好判断があった」と分析。現在も震災に備えて、地震発生から10分以内に1400人が大津波から避難できる施設を建設していると説明しました。山口代表らは、この津波からの退避施設の建設状況も車中から調査しました。
新日鉄住金・鹿島製鉄所は、鹿島臨海工業地帯の主力工場であり、地域経済や雇用に大きな影響を持っています。また、都市対抗野球や鹿島アントラーズなど、地域のスポーツや活力の源泉ともなっている企業です。今後も率直な意見・情報交換を約する、有意義な視察となりました。