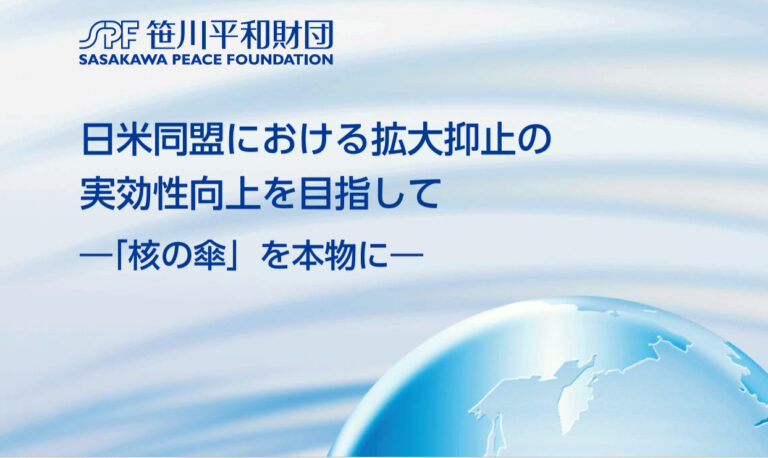今日5月3日、日本の平和と発展を支えてきた日本国憲法が施行後67回目の記念日を迎えました。
今日5月3日、日本の平和と発展を支えてきた日本国憲法が施行後67回目の記念日を迎えました。
現行憲法の骨格をなす恒久平和主義、基本的人権の尊重、国民主権主義の3原則は、人類の英知というべき優れた普遍の原理です。私は公明党の地方議員の一人として、この平和・人権・民主の憲法精神を、地域の隅々まで広く深く定着させ、花開かせるために、今後も努力してまいります。
憲法13条には、「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」、いわゆる幸福追求権が明記されています。また、25条には「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」との生存権が定められています。公明党は、自公連立による安倍政権の一翼を担い、連立合意の最優先課題である経済再生と東日本大震災の復興加速、さらには安心の社会保障の構築に取り組んでいます。発災から3年余が経過した大震災については、引き続き憲法の幸福追求権と生存権の理念に基づいた「人間の復興」をめざして全力を尽くしていかねばなりません。また、「核のない世界」に向けて国際社会が懸命な取り組みを続けている中で、唯一の被爆国としてのわが国の使命を果たすべく核廃絶への弾みをつける闘いを推進してまいります。
さらに、超高齢社会を迎えた今日。お年寄りも、障がいを持った方も、子どもさんも、女性も男性も、全ての方が生きがいに満ちた生活を我が地域で送ることができるよう、地方の現場で汗を流してまいります。
国会では、憲法改正の手続きを定めた国民投票法の改正案で与野党8党の幅広い合意が実現し、今国会で成立する見込みになりました。これにより国会で3分の2の賛成があれば憲法改正の発議ができる環境が整うことになります。施行から70年近くがたち、変化する時代に憲法はどう対応すべきかが問われる中で、今最も大事なことは、憲法の何を守り、何を改正するのかという真摯な論議を冷静に深めていくことであります。
憲法改正について、公明党は、現憲法は優れた憲法であり、平和・人権・民主の憲法3原則を堅持しつつ、環境権、地方分権など時代の進展に伴い提起されている新たな理念を加えて補強する「加憲」が最も現実的で妥当なものであると考えます。憲法9条については、戦争放棄を定めた第1項、戦力不保持を定めた第2項をともに堅持した上で、自衛隊の存在や国際貢献の在り方を「加憲」の対象とすべきかどうか検討を進めて行きたいと思います。
このところ憲法を巡り集団的自衛権の行使容認問題がクローズアップされています。集団的自衛権は、日本が攻撃されていないにもかかわらず日本と密接な関係にある他国を防衛する権利ですが、日本政府は長い間一貫して、わが国に対する急迫不正な武力攻撃から日本を守るための個別的自衛権の行使は合憲であるが、集団的自衛権については、「国際法上は保有しているが、憲法上は行使できない」と解釈してきました。政府のこの憲法解釈は、国民や国際社会に定着しており、この解釈を変えるのであれば、どんな理由で、どのように変えるのか、また、その結果が国民生活や国際社会にどのような影響をもたらすのかなどについて慎重に議論を尽くし、幅広い国民的なコンセンサス(合意)を形成するとともに、諸外国への説明努力が求められる、と考えます。
日本は立憲主義の法治国家です。内閣や国会の多数の人だけで、確立された憲法規範の解釈を根本から覆すことは、この立憲主義を否定することになります。憲法は内閣や国会という統治権力を縛り、国家が国民の人権を不合理に侵害することを防ぐためのものです。ですから、これを守るべき立場にある総理大臣や多数党が、自らの都合の良い方向に憲法の規定を勝手に解釈してしまうようなことは、絶対に許されるはずがありません。
仮に、集団的安全保障を容認する憲法解釈の変更を行いたいのなら、正々堂々と憲法を改正する手続き、すなわち、国民投票を行うべきだと主張します。
憲法は、政党や政治家だけが議論するのではなく、主権者である国民が決めるものであり、私ども公明党は、あるべき国の将来像を探る未来志向の視点に立って国民の皆さまとともに真摯に、かつ丁寧に落ち着いた憲法論議を進めてまいります。
(2014/5/3憲法記念日の公明党アピールを受けて、井手よしひろ県議の個人的な考えをまとめました)