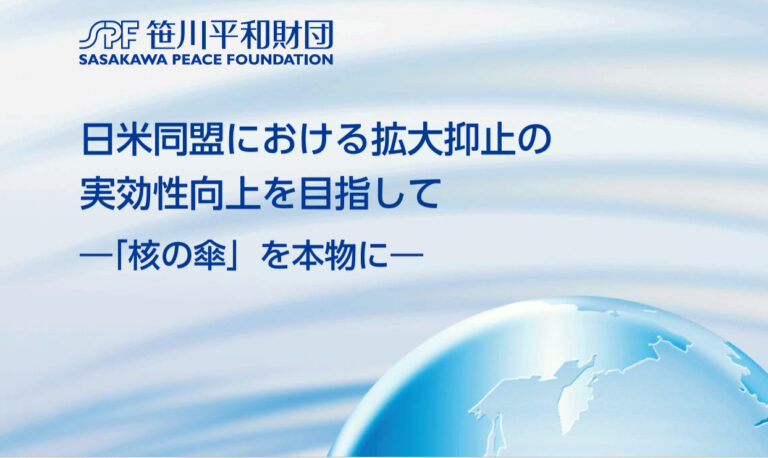5月8日井手よしひろ県議は、JR日立駅前で県議会報告を行いました。この日の県議会報告では、今、安倍首相が進めようとしている集団的自衛権の行使を憲法解釈の変更で容認しようとする動きに対して、公明党の基本的な考え方を説明しました。以下、その内容をご報告します。
5月8日井手よしひろ県議は、JR日立駅前で県議会報告を行いました。この日の県議会報告では、今、安倍首相が進めようとしている集団的自衛権の行使を憲法解釈の変更で容認しようとする動きに対して、公明党の基本的な考え方を説明しました。以下、その内容をご報告します。
【憲法9条を堅持し、自衛隊や国際貢献の「加憲」も検討】
憲法9条は、日本が直接侵略されない限りは武力行使しないという規定に他なりません。9条の下で、自衛隊は国際貢献活動や内外の災害の救援活動などで活躍し、国民の理解が非常に深まっています。そういう意味で、9条の精神は堅く堅持し、大切にしていかなければなりません。
公明党の憲法改正の基本的なスタンスは、素晴らしい日本国憲法の良さは、そのままにして、さらに必要な内容を加えていこうというポジティブなものです。一部には、日本国憲法は連合国から押しつけられてたもの、といったマイナスの評価からの改憲論もありますが、こうした議論とは全く一線を画するものです。
「加憲」の対象としては、9条の1、2項は残したままで、自衛隊の存在を明記し、国際貢献も含めて自衛隊の役割を書くことは議論してもいいのではないかとかんがえています。国民投票法改正案が8党共同で今国会に提出され、ようやく憲法改正の現実的、具体的な議論ができる環境が作られました。そういう中で、9条の問題も最初からタブーにせず、しっかり議論することは大変評価できると考えます。
【集団的自衛権の行使なくして、個別的自衛権や警察権の行使で対応できないのか】
歴代内閣が少なくとも40数年間、集団的自衛権の行使は憲法上認められないという解釈を続けてきました。これは重いものがあり、尊重しなければなりません。仮に解釈を見直すならば、従来の政府解釈との論理的な整合性や法的な安定性、自衛権(武力)の行使が適法かどうかの基準となる規範性が、きちんと説明できないといけません。
安倍首相の安全保障環境が大きく変化しているとの認識は是とします。しかし、安全保障上、どういう必要性があるかを具体的、現実的に議論していくことが必要です。そういう意味では、集団的自衛権の是非という言葉が独り歩きしているように思えます。具体的な必要性にどう対処すべきか、自衛隊にどういう役割を担ってもらうか、という議論を丁寧にしていかないと、国民の理解は得られません。
具体的な事例を想定すれば、集団的自衛権という言葉を出さなくても、個別的自衛権や警察権の行使で対処できる場合が相当あります。例えば、尖閣諸島周辺の問題です。現在、日常的には海上保安庁が警察機関として、警戒活動をしており、中国側からも警察組織が出てきています。不測の事態が起こらないような警察組織間のホットラインをつくることに努力するのが政治の役割です。また、仮に侵略があったとしても、尖閣はわが国の領土であり、個別的自衛権で対処する話です。
具体的な与党協議は、首相の私的諮問機関である「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」(安保法制懇)の報告書が来週にも出されると言われています。報告書が出た時点で、政府としてどう取り扱い、どう協議していくかということが示されるし、首相からも一定の見解が出されことになります。議論は決して結論ありきではないし、スケジュールありきではありません。国民的な議論をしっかりと詰めていくべきだと思います。
【集団的自衛権行使容認は日本国憲法の否定につながる危険性】
集団的自衛権行使容認は、憲法解釈の変更によって行うと言うことは、本来、憲法によって縛りをかけられる政府の側が、閣議決定という手法で、縛りをなくすことを意味します。しかも、そこには国民の意思を問う手続きもありません。集団的自衛権行使を容認するというのは、憲法の存在そのものを否定することにならないか懸念があります。
国際的にも、これまで集団的自衛権は、憲法上行使できないから、海外派兵はしないと、日本は言ってきました。しかし、集団的自衛権行使を認めれば、それが“誤り”だったと宣言することになります。これまでは、憲法9条2項があり、朝鮮戦争、ベトナム戦争、アフガン戦争にも日本は参加しませんでした。参加せずに済んだと言って方が適切かもしれません。しかし、こけからは、そうはいかなくなります。日本の自衛隊が国際的な武力の実行部隊に加わる道を開く事にならないでしょうか。
「戦争ができない国」から「戦争ができる国」に変えようというのが集団的自衛権行使の容認です。こうした意味での集団的自衛権の容認は絶対に許せません。個別であれ、集団で荒れ、日本人のいのちを守り、日本の領土を守ることが「自衛」なのです。
日本人や日本の領土が攻められていないのに、他国と交戦する集団的安全保障を認めるのであれば、憲法9条それ自体を改正する必要があると、私は認識しています。